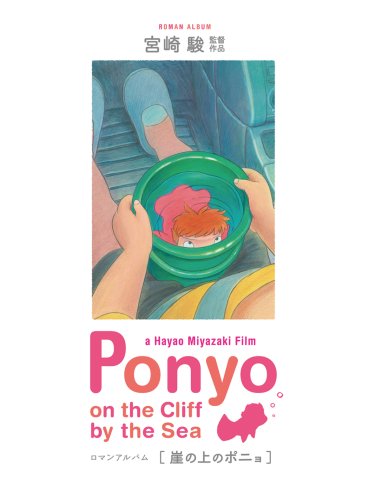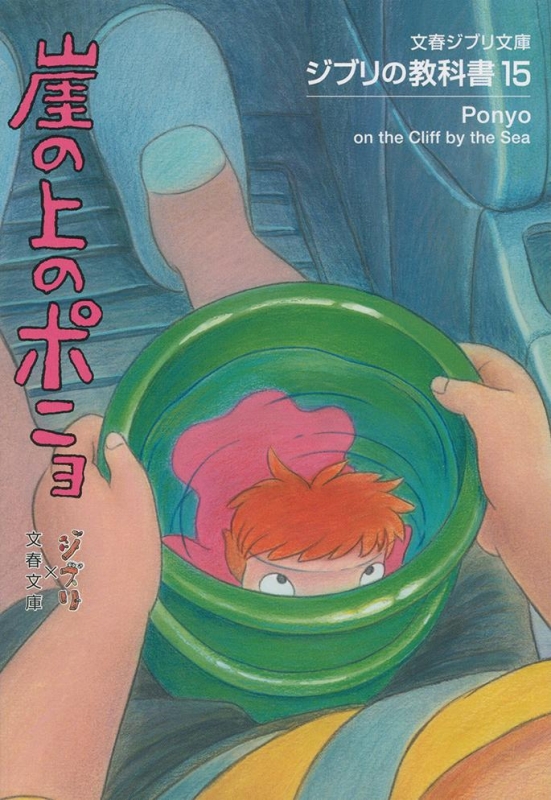Posted on 2014/11/22
ようやく『WORKS IV』関連をまとめることができました。そこから見えてくる2015年以降の久石譲音楽活動の方向性について。個人の解釈と考察で進めます。
先にお断りです。今回は口語体よりも文語体のほうがしっくりくるためその形式にて。偉そうに聞こえてしまうかもしれませんが、そういうつもりはありません。予めご了承ください。
新作『WORKS IV』ができてから -方向性-
『WORKS IV』をまとめ振り返るということは、2014年の久石譲音楽活動を総括することにもなる。そのくらい今年の久石譲は『WORKS IV』の一本柱だったと、改めて振り返りまとめてみた結果、行き着いた結論である。
それについての詳細は先述の 久石譲 新作『WORKS IV』ができるまで -まとめ- に譲る。
ここでは、その経緯と軌跡をふまえて、ある意味において”立ち止まった2014年”の久石譲の想いと、その先にある方向性について考察していきたい。
*1年をかけて完成版に辿り着いた『WORKS IV』収録曲
『WORKS IV』の収録曲のなかで、その目玉は「風立ちぬ 第2組曲」となる。2013年12月に《小組曲》として発表されて以降、改訂を加えた《第2組曲》が世界初演されたのは2014年5月台北コンサート。同じく「かぐや姫の物語」の音楽も、2013年12月に《飛翔》のみが新たなオーケストレーションで披露されて以降、2014年8月W.D.O.コンサートにて組曲として誕生した。さらには「Kiki’s Delivery Service for Orchstra」も、2014年1月台北にて改訂初演されている。つまり約1年をかけて音楽作品としての再構成を練り、コンサートで感触や響きを確かめながら、修正を重ねた結果が『WORKS IV』収録の完成版として記録されている。特に映画作品は、「一定期間が経過して自分で客観的な視点を持てるようにならないと音楽作品として取り組めない」と久石譲が語っているとおり、必然な必要な時間を経て完成版をみた作品たちが並んでいる。
2014年国内・海外で開催された久石譲の全8公演となるコンサートのうち、「風立ちぬ 第2組曲」が披露されたのは計5公演にも及ぶ(12月予定を含む)。多種多彩なコンサート・プログラムを各公演で実施したなかで、突出しているのは言うまでもない。ツアー・コンサート形式ではない単発企画の多い近年の久石譲コンサート活動において、これは何を意味するのか。
*立ち止まった2014年
2013年宮崎駿監督の長編映画引退発表が、久石譲にも大きく影響を与えたことは明らかである。約30年にも及ぶスタジオジブリとの関係、さらには全10作もの宮崎駿監督作品における音楽。久石譲の音楽活動はジブリと共に歩んできたと言っても過言ではない。その宮崎駿監督が引退する。さて、自分はこれからどういう方向性で音楽活動を進めていくか? と立ち止まったと考えるのはしごく自然な成り行きである。
”もう宮崎駿監督作品の音楽を担当することはない” そういった単純なことではない。宮崎駿監督と仕事をするということは、その時代ごとの音楽活動の節目であり、ネクストステップでもあった。そこから解き放たれたとき、つまりジブリという”制約”から解放されたときに、さてどんなビジョンを描いて進んでいくか?、そういったことを考えているのではないだろうか。もちろんここでいう制約とは、メリット・デメリットの両面性をもっている。
映画の仕事を見ても顕著である。2014年に関わった映画作品は『小さいおうち』と『柘榴坂の仇討』。これらは製作段階を起点にすると2013年の仕事になる。企画が決まり音楽制作に入る期間は少なくとも半年から1年を要する。つまりは、久石譲に宮崎駿監督の引退を伝えられた時点から、立ち止まる期間に入ったと言える。糸が切れたという表現はいささか稚拙だが、一旦の区切り、立ち止まって見つめなおすきっかけとなるに足り得る出来事であった。宮崎駿監督という存在がないなかで、他の映画作品の仕事をこれまで同様の延長線上で担当する、ということに対してもストップしたかったのではないか。それほどまでに宮崎駿監督の存在、宮崎駿監督との仕事が久石譲音楽活動の大きなウエイトを占めていたことは想像にたる。もちろんジブリ作品への久石譲音楽の貢献は大きい、だがしかし、久石譲の世に送り出された名曲たちは他分野にも多岐に渡り愛されている、ということもあえて念のため書きとめておく。
話を戻す。事実2015年、映画をはじめとしたエンタテインメント業界の仕事はほぼ白紙である。まだ公式に発表されていないだけかもしれないが、仮に今現在映画作品と距離を置いているとすれば、少なくとも2015年上半期、久石譲の新作映画音楽を劇場やCDで聴けることはないだろう。ほとんどの依頼を断り立ち止まった1年であり、その余波は2015年以降につづくことになる。エンタテインメント業界において久石譲音楽が聴ける機会が減る可能性があるということである。

*クラシック? 現代音楽? ミニマル音楽? 現代の音楽?
久石譲の音楽性を語る上で、その肩書きや表現が多岐にわたる。どれも似ているのだが、カテゴライズが違ったり、現在の解釈では意義が違うものもある。ここでは『現代の音楽』という言葉を使う。不協和音に象徴される昨今の現代音楽ではい。これについて久石譲は、「ミニマル・ミュージック以降の、ポストミニマルやポストクラシカルなどのジャンルでいうと、自分はポストクラシカルの位置にいると認識しています。そういう作品はいまも書き続けていくべきだと考えているし、力を注いでいる部分でもあります。現在つくっている音楽も、やはりベーシックはすべてミニマルです。それの発展系ですね。」と語っている。また別の機会には、「アルヴォ・ペルトという作曲家などは、不協和音も書いていたけれど、「原点に戻らないと音楽がダメになる」と先陣を切り、多くの音楽家がその方向に向かいました。その大きい動きの中に自分もいるという気がします。いま日本にいる、いわゆる「現代音楽」の作曲家と同じことをするのではなくて、僕がやりたいのは「現代“の”音楽」。エンタテインメントの世界にいるから、人に聴いてもらうことを何より大事に思っているんです。だから、現代にあるべき音楽というのを一生懸命紹介したり、書いたりしていきたい。」と。つまりは、『現代の音楽』という表現に統一、象徴されている。折に触れ自分の原点を突き詰めたくなるというミニマル・ミュージックを盛り込んだコンテンポラリーな作品、ということになる。また久石譲は”今日の音楽”という表現もしていることから、未来も含めたこの時代の音楽ということになる。
*「クラシックに戻す」の真意
「自分の本籍をクラシックに戻す」、11月の雑誌インタビューで語られた。実はこの発言遡ってみると、2013年8月にも同じことを述べている。「自分のベーシックなスタンスをクラシックに戻すつもりでいます。もともとは現代音楽の作曲家でスタートしているからね」と。後日紹介予定だが『風立ちぬ』公開記念の雑誌インタビューである。そう、1年以上前からすでにその指針は語っていたのである。これは単純に古典クラシック音楽を演奏する機会が増えるといったことではないだろう。前項の”現代の音楽”に通じる、まさにコンテンポラリーな作品の創作活動へとシフトしようとしている現れである。
興味深いことに2014年コンサートプログラムには、ある特徴がある。「バラライカ、バヤン、ギターと小オーケストラのための『風立ちぬ』第2組曲」をはじめとして、「混声合唱、オルガンとオーケストラのための~」「ヴァイオリンとオーケストラのための~」、「~for Orchestra」、「弦楽四重奏~」、「~for 2 Marimbas」、「弦楽オーケストラのための~」など。もうおわかりだろう、自作の新作および改訂版において、ほぼすべての楽曲に楽器編成・楽器構成が明記されている。いかにもクラシック音楽の表現方法のひとつである。つまりは、すでに久石譲のなかで”クラシックに戻した”音楽活動は始まっているのである。これから先さらに、シンフォニー、小編成、独奏楽器や特殊楽器を織りまぜた創作活動につながっていくのかもしれないという”クラシックを軸にした”方向性の現れではないだろうか。
”クラシックに戻す”とは、作曲家として、大きな流れにおいてポストクラシカルに位置していると認識し、ルーツであり原点であるクラシック、ミニマル・ミュージックによる現代音楽、さらにはエンタテインメント音楽として発表された楽曲を、コンサートなどにおいて古典クラシック音楽と並列しても遜色ないクオリティにまで磨き上げ、楽器編成を再構成し、音楽作品として昇華させる。そのすべてが作曲家久石譲による”現代の音楽”に帰結していくかのように。そしてこれこそが、久石譲が想い馳せる”現代にあるべき音楽”であり、後述する”アーティメント”なのだろう。
*2014年コンサートプログラム 考察① W.D.O.成熟期
今年のコンサート、とりわけW.D.O.名義や新日本フィル・ハーモニー交響楽団との公演が多い。さらには、同フィルとの共演プログラムすべてにおいて、コンサート・マスターであるヴァイオリンをフィーチャーした楽曲が選ばれている。8月W.D.O.では「ヴァイオリンとオーケストラのための『私は貝になりたい』」、10月長野公演では「弦楽オーケストラのための『螺旋』」(Vnソロはないが弦楽主体の意)、そして12月ジルベスター・コンサートでは「Winter Garden」が予定されている。加えるならば、当初プログラムから変更にこそなったが、長野公演で一時予定として挙がっていた「魔女の宅急便より『かあさんのホウキ』」も、2008年武道館公演で披露されたヴァイオリンの旋律が美しい楽曲である。2004年に発足した「久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ」(W.D.O.)が2014年の今年10年目を迎えた。久石譲と新日本フィルの関係性が親密であるのと同時に、確固たる互いの信頼関係において成熟期に入った証拠である。
*2014年コンサートプログラム 考察② 自作現代音楽
近年、自作と古典クラシック音楽を織り交ぜたコンサート・プログラムを展開してきた久石譲だが、今年はとりわけ自作のウエイトが幾分増えたばかりか、その内容にはポピュラーではない自作、つまり現代音楽を披露する機会が多かった。1月台北での「5th dimension」(藤澤守 名義)改訂初演、5月台北での「混声合唱、オルガンとオーケストラのための『Orbis』」、9月京都での「室内オーケストラのための『シンフォニア』」、9月東京での「弦楽四重奏曲 第1番 “Escher”」「Shaking Anxiety and Dreamy Globe for 2 Marimbas」ともに世界初演、10月長野での「弦楽オーケストラのための『螺旋』」(当初予定では「ピアノと弦楽オーケストラのための新作」というプログラム案もあった)、そして12月予定の「Winter Garden」。これもまたひとつの変化の兆しであると感じる。
興味のある方は、ここ数年のコンサート・プログラムの流れを読み解き、また前年以前との傾向の違いを見比べてみてほしい。 → 久石譲 Concert 2010-
*2014年コンサートプログラム 考察③ 現代の音楽を探る
②をもとに、「クラシックに戻る」発言も照らし合わせると、このようになる。自作とりわけ現代音楽の演奏機会を増やし、会場の感触、空気感、響き、そして観客の反応、これらを確かめるように実演を繰り返していく。後述するが、今後作曲家活動の先に、自作の普遍性と未来へつないでいくための楽譜出版にも力を入れていく予定という。その大きな流れの一環として、コンサートで演奏を重ね、まずは作曲家自身のものとして掌握することで、一旦の完成版をみる。そこからCD作品化や楽譜出版として形となり、他者が演奏する機会が用意される。そういった作品発表の機会、改訂や修正を重ね完成形へ近づける場としてコンサートが成立していくのではないだろうか。これは先に述べた『WORKS IV』収録曲の、約1年に及ぶ演奏会からCD作品化へという流れからみても、今後同じような経過を辿っていくことは考え得る。その範囲が大衆性を帯びた映画音楽から、芸術性を帯びた現代音楽へと広がりつつあるのである。
*アーティメントを語る
2014年久石譲が発信したキーワード”アーティメント”(アートメント)。アート+エンタテインメントを合わせた造語である。しかしちょっとした違和感があった。なぜ今”アーティメント”を語るのかと。久石譲の音楽活動においてエンタテインメント業界で活躍してきた大衆性(エンタテインメント)と、音楽的オリジナリティを追求してきた芸術性(アート)。これはいつも両輪であった。たとえば映画音楽を担当すればサウンドトラックを発表し、一方では制約から解放されたソロ・アルバムを発表してきた。両輪である。たとえば商業ベース、エンタテインメントの世界が求める音楽と、自分がつくりたいものとの葛藤やフラストレーション。常に音楽活動のなかでそのバランスをとるかのようにあらゆるアプローチで作品を発表してきた。両輪である。もっといえば、”WORKSシリーズ”や”Piano Storiesシリーズ”などは、まさに大衆性+芸術性をあわせもつ、格調高くドラマティックな音楽作品へと昇華させる、久石譲の真骨頂でありマイルストーン的役割を持っている。なのに、なぜ今改めて”アーティメント”なのか。
これには宮崎駿監督の引退が影響していると考察している。つまりは、これまでどれだけ前衛的で独創的な現代音楽を発表したとしても、一方には大衆性の最たるジブリ作品の音楽という仕事があった。過去の作品という意味ではなく、現在進行形での大きな大衆性と、突きつめた芸術性を維持できていた、音楽活動の道程ということである。その片輪が未来に対してなくなろうとしている。だからこそ”立ち止まった1年”だったのであり、”アーティメント”の土台を見つめなおす必要があった。
おもしろいことに、『WORKS IV』に収録された「風立ちぬ」も「かぐや姫の物語」も決して耳あたりがいい音楽ばかりではない。そこには重厚な不協和音も響いているし、ルーツであるエスニック・サウンドやミニマル色も強く盛り込まれている。つまり、これまでの”WORKS”シリーズで取り上げられたジブリ作品に比べて、格段に前衛的で独創的なアート性が増しているのである。付け加えれば、「私は貝になりたい」でもヴァイオリンの重音奏法から激しいミニマルのパッションという、これまでには考えられないほど、大衆性と芸術性の境界線が崩れてきている。
これこそが、今久石譲が語っている”アーティメント”(アート+エンタテインメント)のかたちではないだろうかと思う。作品ごとに映画なら大衆性、オリジナルなら芸術性ではなく、作品ひとつひとつに大衆性と芸術性を混在させてしまう、いやその領域まで昇華させると言ったほうが正しい。かつその方法論のなかには”クラシック”という大きな軸が存在する。一方では、ジブリ作品を例にとったその逆説的には、これから発表していくであろうミニマル・ミュージックをベースとした現代音楽が、これまでよりも聴きやすい、もしくは普遍性を帯びたものになるべく創作されるという見方もできるのである。久石譲の過去の作品から挙げるとするならば、まさに『メロディフォニー』や『ミニマリズム』を継承した、いやその次のステージに入った”久石譲のアーティメント音楽”が発表される可能性を秘めている。『WORKS IV』のリ・オーケストレーションされた映画音楽たちは、これまでのオーケストレーションの再構成とは違う、一歩先の”アーティメント”を追求した布石となる第1作目なのかもしれない。そして、次に待つのは映画音楽ベースではない、”現代の音楽”からの”アーティメント”追求なのかもしれないと。
久石譲の言葉も引用するとさらに説得力が出てくる。「時代や国境を越えて聴かれ演奏される音楽を制作したい。そのための時間を作る生活にシフトチェンジしている最中です。」「かつて、僕の作品は僕だけが演奏していました。それが今では、世界各国のオーケストラが僕の書いたオリジナルの楽譜で演奏しています。」
*未来につないでいきたい音楽
2014年W.D.O.の復活と同時に、新たに始動したのが「久石譲プレゼンツ ミュージック・フューチャー」コンサートシリーズ。まさに今久石譲が未来に残したいと思う音楽、多くの人に届けたい音楽を発信する場である。クラシック音楽ならびに現代音楽の厳しい現状を打破したいという思いもある。過去から現在に引き継がれた音楽がクラシックとするならば、未来へつなぐものも今日演奏されている古典クラシック音楽だけでいいのか、現代の音楽から未来へ引き継がれるべき作品があるのではないか。そういった想いなかで、その演目は自作のみならず、海外の現代作曲家の作品まで多岐にわたる。この傾向は8月W.D.O.にも及ぶ。さらには自作に関しても、9月に開催された同企画Vol.1においては世界初演2曲という異例のかたちとなった。これは来年以降のW.D.O.やオーケストラコンサート、ならびにミュージック・フューチャーにも引き継がれていくであろう。広義において”現代の音楽”を発信する場、”未来につないでいきたい音楽”を伝える機会として。自作の傾向詳細は、先の【*2014年コンサートプログラム 考察② 自作現代音楽】にて紹介している。
*人に聴いてもらう機会
”人に聴いてもらうことは何よりも大事”と久石譲は語る。これまでの流れから整理する。自作自演はCD・コンサート・メディア発信となり、自作他演は楽譜出版となり、他作自演はコンサートとなる。そして、その演目は、自作・他作問わず、”現代の音楽”であり”未来につないでいきたい音楽”である。またコンサートプログラムにおける自作の演奏機会が増えることも予想される。先の【*2014年コンサートプログラム 考察③ 現代の音楽を探る】の項にて述べた。8月W.D.O.コンサートにおける公式パンフレットにもこうある。「自分の曲をきちんと届けていくことから再開したい」と。今後の創作活動の内容に多分に影響されるところはあるが、少なくとも古典クラシック音楽主体のコンサートの機会は減るのではないだろうか。
もうひとつ、この発言には大事なキーファクターが隠れている。それは”アーティメント”である。先の【*クラシック? 現代音楽? ミニマル音楽? 現代の音楽?】の項にて、”現代の音楽”についての定義は述べた。そのなかの久石譲発言に、「自分はエンタテインメントの世界にいるから~」と続く。何を意味するのか。それは、あまりに芸術性を突き詰めすぎた現代音楽は、聴衆との大きな距離ができてしまう。だからこそ、あえて「ポストミニマルではなくポストクラシカルという線上に自分はいる」と語っているのである。つまりは、オリジナル創作活動において、本来は芸術性のみを追求すればいいところに、大衆性とのせめぎ合いや葛藤が生まれる。その昇華へ導く軸として”アーティメント”があるのである。久石譲の”アーティメント”の結晶が”現代の音楽”としてかたちとなり、”未来につないでいきたい音楽”として多くの”人に聴いてもらう機会”を得るのである。
*パーソナルな作品から普遍性のある作品へ
「作品として形にすることで、譜面を出すことにもなる」、または「今回の『WORKS IV』のように完成度を高めた楽曲は、楽譜をドイツに本拠を構えるショット・ミュージックから出版している」と語る久石譲。”アーティメント”を念頭に置いたときにこの発言の意味は大きい。つまりはアート(芸術性)とエンタテインメント(大衆性)をかねそなえた作品を発表することが、作曲家の手を離れて久石譲音楽が演奏される機会が増えることにつながるからである。また今年久石譲は、改めて自分の肩書きは作曲家であるということに触れている。「僕は肩書きで言ったら作曲家ですから。指揮もピアノもしますが、基本は曲を書く人です。それがないと自分の音楽活動は成立しません。だから作曲というのはどこまでも大事にしたいですね。」と。
楽譜出版をするこということは、音楽作品として作曲家自身が完成版として納得した証でもある。そのクオリティに行き着くための、コンサート演奏を繰り返すことでまずは自らが掌握する経緯は先に述べた。そして、同様に楽譜には模範演奏が必要である。ピアノ・ソロならまだしも、フル・オーケストラによるシンフォニー作品は、楽譜だけで作曲家の意図通りに実演することは難しい。ましてや、久石譲による楽器編成、音の強弱、テンポ、揺れなどは、作曲家自身が指揮者・演奏者となることであの独特な世界観をつくりあげているのである。久石譲の音楽が、本人から他者へ、国内から海外へ、現在から未来へ、その普遍性が帯びてくるということ、楽譜出版として形にするということは、イコール、CD作品化も同一線上にあると考えるのが妥当である。普遍性を導くには、まずは作品を形に残すことが前提条件であると考える。
一方で個人的な解釈である。楽譜出版による久石譲音楽の普遍性。もちろんそれもあるが、現時点で普遍性は確立されていると断言する。それは、久石譲の音楽が不特定多数の聴き手を相手にするのではなく、あくまでも聴き手が個人的に作品と向き合った時に感じる感動体験にひたらせる音楽だからである。それこそが、聴き手の集合体となり演奏者の拡がりとなり、今も未来も普遍的なのである。そこに”音楽作品としてのかたち”、すなわち音楽をつめ込んだCD作品、作曲家の息吹、意図や意思を忠実に表現したオリジナル音源がひとつでも多く残されていくことが望ましいとも思う。聴き手の日常生活のなかで、久石譲音楽を響かせ、こよなく愛し続けるためには、そういった”かたち”が必要不可欠なのである。これは無形としての普遍性も既にあると言い切ったうえで、それでもなお有形として残していってほしいという個人的願望である。
*勝手に曲想や構想を妄想
少し道をそれる。こういう作品化もあるのではないか、ということを勝手に妄想を膨らませていく。過去の名曲たちが新しいクラシック方法論によって甦る。【*「クラシックに戻す」の真意】と【*アーティメントを語る】の項を軸にして想像する。例えば、ジブリ作品でいうと、2008年武道館公演での演奏曲目や演奏編成などを参考にする。「混声合唱とオーケストラのための『崖の上のポニョ』」、「トランペットとオーケストラのための『天空の城ラピュタ』」、「吹奏楽とマーチングバンドのための『天空の城ラピュタ』」、「ソプラノ、混声合唱とオーケストラのための『もののけ姫』組曲」、「ピアノと金管四重奏のための『紅の豚』」などなど。
ほかにも過去コンサート演目や、未CD化作品および未演楽曲、コンサートでのみ披露されたバージョンや編成から多種多様なピースを思い描くことができる。例えば、「『二ノ国』組曲」、「『太王四神記』組曲」、「チェロとピアノのための『la pioggia』」、「管楽オーケストラのための『天地明察』」、「『この空の花』の主題によるボレロ幻想曲」、「2台のハープとオーケストラのための『海洋天堂』」などなど。これ以上やると妄想が過ぎる。また枚挙にいとまがない。そうなると久石譲ファンのなにか執念的なものが色濃く反映されてしまうためここでぐっと留める。それほどまでに久石譲の作品は、新作を待たずとも、音楽作品として昇華されるに値する、普遍性を帯びた名曲たちの宝庫である。現時点でも溢れ出るくらいの傑作たちがストックとして存在し、光り輝いている。さらに磨きあげられ眩く日が来るのか。これもまた、久石譲のこれからの”アーティメント”感性と、久石譲が思う”未来につないでいきたい” ”現代の音楽”なのか、という判断基準によって精査されていくのであり、すべては作曲家久石譲に委ねられている。
*来年に向けて 久石譲インタビュー
ここでは、2014年数々のインタビューで締めの質問として問われた「今後の予定は?」に対する、久石譲の発言をまとめる。「今年は依頼をほとんど断って、よく立ち止まるようにしているんです。来年からはもう一度、しっかりやりたいと思っていますよ。」、「まず来年など、ずいぶん先に委嘱されているものをきちんとつくらなければいけないし、それにはやはり手間暇がすごくかかるんです。自分の作品を書くことと、エンタテインメントの仕事と、そのあたりの時間の配分はかなり考えないといけない。」、「指揮だけを考えると、同じ曲でもシンフォニーなどは、5回10回と振っていくことで理解度が深まりますから、そういった経験は非常に重要です。なのでチャンスがあったらどんどんチャレンジしていきたいですね。」 ということである。
*来年に向けて 考察
久石譲インタビューで語られた抱負を受け止めるしかない、というのが結論ではある。ひとつだけ確定している創作活動としては、2015年3月「バンド維新2015」のために書き下ろす吹奏楽の委嘱である。その他映画をはじめとしたエンタテインメント業界での仕事、創作活動もコンサート活動も白紙である(2014年11月現在メディア発信されていない)。今回の『WORKS IV』での革新的なレコーディング方法もふまえると、どういった形で作品化されるかも想像の域を出ない。スタジオレコーディングされるのか、ライヴ録音をCDのクオリティーまで高めた作品として仕上げていくのか。そのすべての活動が白紙なのである。
ただ、これまであらゆる視点で考察したとおり、2015年以降は、”クラシック、ミニマル・ミュージックという久石譲の原点に戻る”ということよりも、さらに一歩推し進めた新しい展開が待っているような気がしてならない。それは次のステージへと突入した”クラシック”を軸とした新しい”アーティメント”のかたち、”未来へつないでいきたい” ”普遍性を帯びた” ”現代の音楽”。その序章としての位置づけが新作『WORKS IV』なのではないだろうか。久石譲の新しい創作活動への布石はこの『WORKS IV』であり、幕は開いたのである。
*おわりに
「言葉によって伝えることの大切さ」、これはひとつのキーワードである。たとえばこんなエピソードがある。映画『となりのトトロ』でトトロが登場する際に流れる7拍子のミニマル・ミュージックBGM。当初監督はこのシーンに音楽は必要ないと言っていたが、念のために作った久石譲の音楽を入れたとき、トトロという存在が確固たるものとなったと。また「弦楽オーケストラのための『螺旋』」というコンサートで数回演奏され、CD音源化されていない作品がある。このコンサート・パンフレットには、久石譲本人の解説が掲載されている。「曲は、8つの旋法的音列(セリー)と4つのドミナント和音の対比が全体を通して繰り返し現れる。もちろんミニマル・ミュージックの方法論で作曲したが、その素材として上記の12音的なセリーを導入しているため結果として不協和音が全体の響きを支配している。(以下省略)」
久石譲の活動や楽曲といった情報を探すために当サイトは存在する。そしてさらには、楽曲それぞれの時系列、変化、秘話、解説、背景もこぼすことなく記録していきたいと努めている。”言葉=動機付け”としたときに、上の二つの例をとってみても、その意義はあると認識している。”耳馴染みの”もしくは”お気に入りの”あの一曲のエピソードを知ることで、聴き方が変わってくるのではないか。そして、作曲家自身の言葉で知ることで、”聴いたことがない曲”であれば、CDを手にとってみよう、また”未CD作品”であればその希少性も増し次回はぜひコンサートに行こう、という好奇心へと突き動かされるのではないか。作品をより深く知るための味わうための情報や知識。興味を持つきっかけであり、紐解き掘り下げたくなる好奇心。そういった有益なサイトとなるように、今後も情報発信として許されると判断したものは、久石譲の歴史として刻んでいきたい。
当サイトでは、転記やあらゆる文献からの書き起こしも、忠実にオリジナルを残すことに意義があるという思いから、修正や加工、そして管理人の解釈とは区別して忠実に再現化していることをお許し願いたい。それでも約35年以上にも及ぶ久石譲の音楽活動を網羅するには程遠い。これからもライフワークとして築きあげていきたい。
最後に。
長文にわたってご清聴ありがとうございました。幾分簡潔にまとめるつもりが溢れてしまいました。2014年の久石譲の総括は年末にまたしたいと思っていますが、キーワードとしてはやはり”立ち止まった1年”でした。発表される作品やコンサート活動を見ると、2014年も精力的に動いて見えますが、いや実際動いています、でもその準備段階や制作期間、つまり種まきや創作活動の時期にはタイムラグが発生します。2014年世の中に発表されたものは、2013年に水面下で準備され創作されたものが花開く、という具合にです。
だからこそ”立ち止まった2014年”、その先にある2015年は、少し沈黙がつづくのかもしれません。ファンとしてはさみしい限りですが、それだけに次の創作活動への期待もふくらみます。”生みの苦しみ”という芸術家の性を、”待つ辛抱”という受け手の想いにかえて。最後に補足ですが、久石譲の発言は”方向性のひとつ”であり、私の考察もまた”推測の域を出ない”ものです。ここには出てこなかった新たな方向性へと2015年以降導かれるのかもしれません。それを承知のうえで発信していますし、そう受け止めていただければと思います。またいかなる発信にも責任はともないますので、あまりに筋違いな見解は控えているつもりです。2014年の久石譲音楽活動から見えてくる振り返りや方向性、ファンとしてマイルストーンを残すこともまた大切であり、こよなく愛しつづける音楽家へ敬意を表することのひとつだと思っています。
《後記》
あくまでも読みやすさを優先した(つもり)のため、久石譲発言の引用元や、楽曲・コンサートなどのリンク先URLは割愛しました。すべて2014年の情報から詰め込んだものですので、下記当サイトのバックナンバーやサイト内検索窓を活用してぜひ掘り下げてみてください。 ⇒ back number [ Information /Blog ]
Related page: