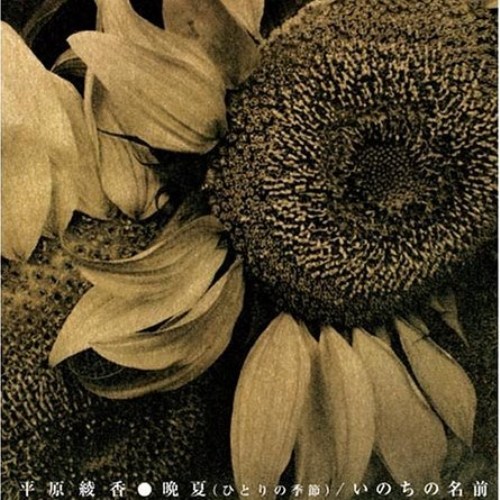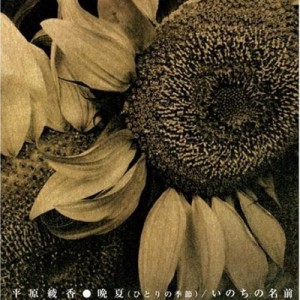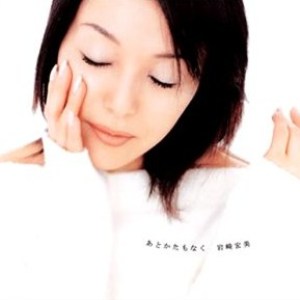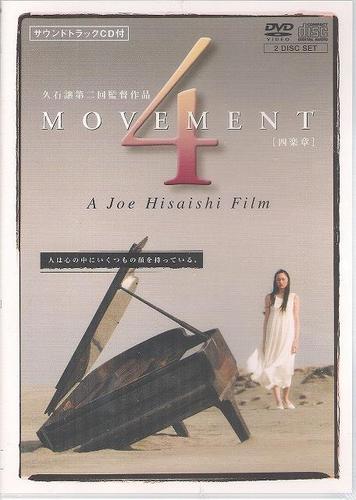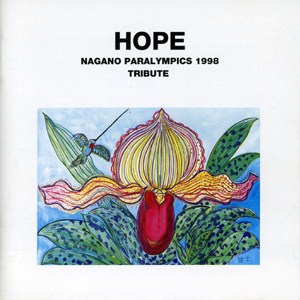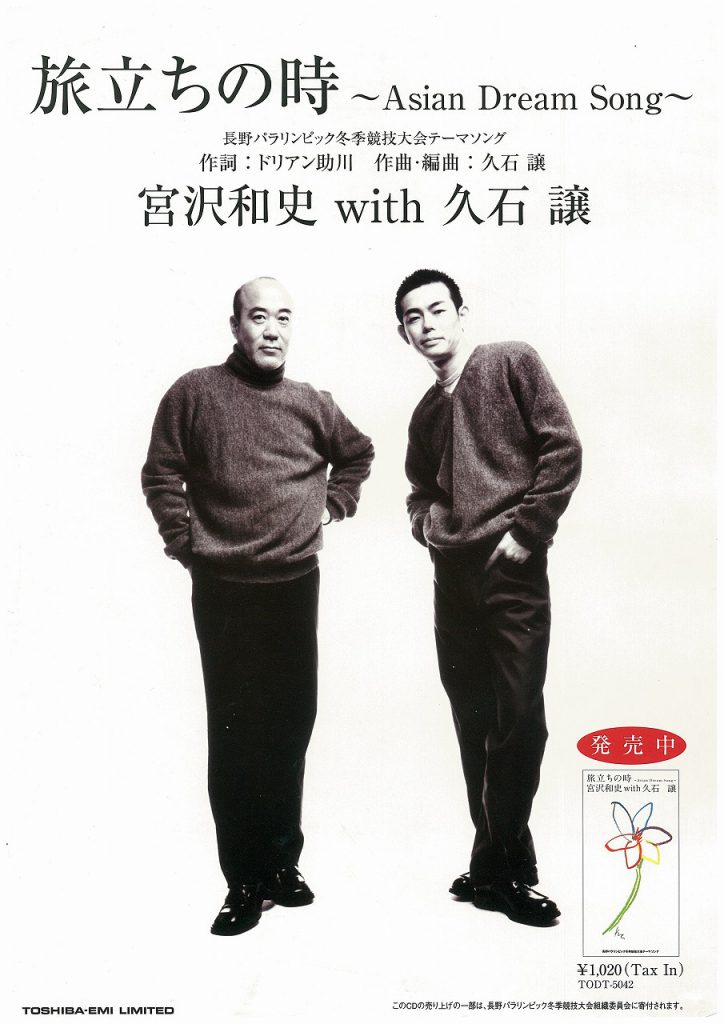2017年5月17日 デジタルリリース
2017年公開映画『たたら侍』(監督:錦織良成)主題歌
EXILE ATSUSHIと久石譲によるコラボレーションは2013年『懺悔』(日本テレビ開局60年「特別展 京都」テーマソング)につづく2作目である。
EXILE ATSUSHI コメント
■久石譲と楽曲を制作することになった経緯
以前、懺悔という作品でご一緒させていただいた時の衝撃が、いちアーティストとして胸の中にずっと残り続けていて、今回たたら侍の映画の主題歌のお話をいただいた時に、またもう一度、久石さんとご一緒させていただけたら、良いものができるのではないかという想いで、お願いすることになりました。
■久石さんの作った曲を最初に聞いたときの感想
前回の懺悔の時もそうだったのですが、音楽的に卓越し過ぎていて、僕の想像力を遥かに超えたところにゴールがある感じでした。信頼と確信の元に歌詞を綴り始め、その歌を歌ってみた時に初めて、こういう事だったのかと納得させられまして、久石さんの音楽家としての圧倒的な魅力に引き込まれていく感覚でした。
■歌詞に込めた想い
日本独自の文化や歴史など、いろいろなものからヒントを得ています。また音や言葉、記号やマークにはどんな想いが隠されているのか。それらに対する、人間の業や、人々の想い、嘆きは、またどんな意味を持つのか。そして最終的には、人間はどのようにして万物の霊長に成り得ることができるのかを問いかける意味にもなっています。そして何よりも、平和への願いが込めさせていただきました。
■主題歌に決まったときの率直な感想
題材がとても特別なものですし、日本独特なものでしたのですごく責任を感じましたが、同時に使命感みたいなものを感じ制作させていただきました。
■主題歌を通して、映画を観る方に何を感じてほしいか
いりいろなものが便利になった世の中で、僕たち人間たちが、肌で感じて、どんな想いで行動するべきなのか、それを考えなければならない時代が来ているのかもしれないということを、少しでも感じていただけたら、これ以上の幸せはありません。
(公式サイトコメントより)
楽曲を象徴するヴァイオリン。通常の4弦のよりも2本多い6弦エレクトリック・ヴァイオリンである。つややかさとあでやかさをもつその響きは、この作品の崇高で奥深い世界観の核となっている。特徴はアコースティック・ヴァイオリンの優美さに加え、アンプをとおしたディストーション(ひずみ)など表現の豊かさにある。また弦数が多いぶん音域も広くなり、通常のヴァイオリンよりも低い音域が可能となっている。
久石譲が最先端の”現代(いま)の音楽”を発信するコンサート・シリーズ「MUSIC FUTURE Vol.1」(2014)において、ニコ・ミューリー作曲「Seeing is Believing」がプログラムされた。日本では珍しい6弦エレクトリック・ヴァイオリンを独奏に用いた作品で、久石譲はこの演奏会のために楽器を調達している。
翌年「MUSIC FUTURE Vol.2」(2015)では、この楽器に刺激を受け自らの新作「室内交響曲 for Electric Violin and Chamber Orchestra」を書き下ろし披露。こちらは同名CD作品としてLIVE盤となり、久石譲公式チャンネルでもその斬新な野心作を見て聴いて体感することができる。(※2017年5月現在)
そして、今回ポップス・ミュージックでも響きわたらせてしまった。2014年のそれは同楽器日本初演奏であり、2015年の自作をふくめ6弦エレクトリック・ヴァイオリンを使った作品は世界においても数少ない。ということは、今作「天音」によってPOPS音楽で同楽器をフィーチャーするのは日本初ということになる、と思われる。
そんないわくつきの楽器の紹介をしたうえで、「天音」に耳を傾けてみる。
イントロから優美なヴァイオリンの音色、通常のヴァイオリンではなし得ない低音域、そしてザラザラした硬質なディストーション。イントロ数小節で6弦エレクトリック・ヴァイオリンの魅力を伝えきっている。曲の展開は進み中間部ではエレクトリック・ギターと聴き間違うほどの魅惑的なディストーション、エンディングまで一貫して奏でられるその響きは、この作品のもうひとつのコラボレーションと言ってもいいほどである。
そして、対位法的というか対照的なのが、主役であるEXILE ATUSHIの透明感ある包みこむような澄んだ歌声と、久石譲のピアノ。6弦エレクトリック・ヴァイオリンの独特な響きが、結果ふたつの主役を一層引き立たせていて、まさにふたつの白い光のような”天音”を浮かび上がらせているようにすら思う。
付け加えると、6弦エレクトリック・ヴァイオリンはそのものが多重な響きを醸し出している。そのため通常のヴァイオリンと異なり、ビブラートを効かせる奏法をあまりとっていないと思う。太く厚みのある音をまっすぐにのばすことで、ヴォーカルの遠く広がるビブラートとぶつかりあうことがない。ゆっくりと深く波打つヴォーカルのビブラートに改めて感嘆しながら、それを気づかせてくれたのはこの楽器との響きあいゆえ。実は歌曲と相性がいいのか、もちろんそこには表現力に優れた歌い手であることが求められる。それをも見据えた久石譲の音楽構成か、見事である。
小編成アンサンブルも楽曲に彩りをあたえ、アコースティック楽器とエレクトリック楽器の融合は本来容易ではないはずなのだが、そこは上記コンサートもふまえた実演と響きを熟知した久石譲の妙技といえる。
ほとんど6弦エレクトリック・ヴァイオリンをフィーチャーしたレビューとなってしまったが、それだけの存在感と重要な役割を担っている。それは”あったから使ってみた”のではなく、この楽器でなければならなかった必然性と久石譲の確信を聴けば聴くほどひしひしと感じる。
6弦エレクトリック・ヴァイオリンの特性を知ることで、聴いたことのない響きだけれど得も言われぬ心地のよい響き、ときに尖りときにしなやかに奏でる音色、広がりと深さをもって大きく包みこむ世界観。今まで体感したことのない新しい響きをきっと受けとることができる。
卓越した表現力をもったヴォーカリストとピアノ、そこに拮抗し独特な距離感と溶け合いをみせるヴァイオリン。それぞれ個の個性が強いからこその凛とした絡み合い。共鳴しあう至福を感じる楽曲である。三位一体なのかもしれない。
2019.4.26 追記
本楽曲初CD化
『TRADITIONAL BEST / EXILE ATSUSHI』CDライナーノーツより
Word:ATSUSHI
Music, Arranged & Produced by Joe Hisaishi
Conducted by Joe Hisaishi
Electric Violin:Tatsuo Nishie
Flute:Hiroshi Arakawa
Oboe:Satoshi Shoji
Clarinet:Kimie Shigematsu
Bassoon:Toshitsugu Inoue
Horn:Takeshi Hidaka
Trumpet:Kazuhiko Ichikawa
Trombone:Naoto Oba
Bass Trombone:Ryota Fujii
Percussion:Makoto Shibahara, Akihiro Oba
Piano:Febian Reza pane
1st Violin:Nobuhiro Suyama
2nd Violin:Tshkasa Miyazaki
Viola:Shinichiro Watanabe
Cello:Takayoshi Okuizumi
Contrabass:Tsutomu Takeda
Instruments Recorded by Hiroyuki Akita at Bunkamura Studio
Vocal Recorded by Naoki Kakuta at avex studio
Mixed by Suminobu Hamada at Sound Inn Studio
Mamipulator:Yasuhiro Maeda (Wonder City Inc.)
and more..

天音(アマオト) / EXILE ATSUSHI & 久石譲
作詞:EXILE ATSUSHI 作曲:久石譲