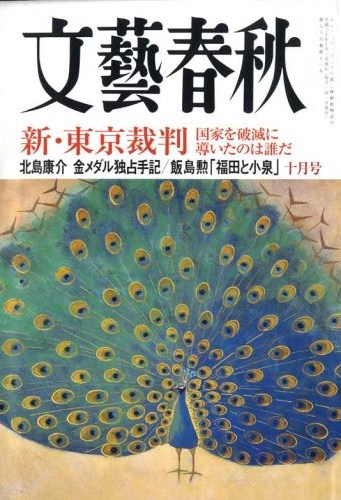Posted on 2015/2/2
「文藝春秋 2008年10月号」に久石譲インタビューが掲載されていました。
2008年 映画 『崖の上のポニョ』公開直後だけあって、もちろん話題の中心はポニョのお話です。そのなかにも久石譲の作曲家としてのスタンスや、創作するということの奥深さを感じることができる内容です。
「ポニョ」が閃いた瞬間 久石譲(作曲家)
2年前の秋、武蔵野の緑に囲まれたスタジオジブリの一室。宮崎駿監督が映画の構想を熱く語っている。その言葉に耳を傾けていると、僕の頭に突然メロディが浮かんだ。
ソーミ、ドーソソソと下がっていくシンプルな旋律。今夏公開され、大ヒットしている映画『崖の上のポニョ』のエンディングテーマだ。シンプルであるがゆえに、強い印象を残す曲になるだろうという予感は的中した。
多くの人から「あの『ポーニョ、ポニョポニョ』が頭から離れない」との感想を頂戴した。メロディも「ポニョ」という言葉も実に単純なものだ。ところが、それが一体になったことで、二乗、三乗、いや三十乗くらいの力を持って、誰の耳にも入りこんでいったのだろう。こんな奇跡のような出来事が起きたことは、音楽家として本当に幸せだ。
宮崎監督との最初の打ち合わせを思い出す。
台本の裏側に五線譜を引き、あの旋律を残した。
しかし僕はこのメロディをいったん忘れ、しばらく寝かせておくことにした。本当にこれが主題歌にふさわしいのか自信がなかったし、いろいろな可能性を検討してみたかったからだ。情感豊かなバラードはどうかと考えてみたり、二ヶ月ほど試行錯誤を繰り返した。しかし、最初に閃いたあの旋律が一番だという結論に至った。
ソーミ、ドーソソソの六音からなるこのフレーズは単純だけれども、だからこそさまざまにアレンジすることができる。この機能性は映画音楽では最高の武器だ。困ったらこのメロディに戻ればいいわけで、水戸黄門の印籠のようなものである。この瞬間、迷いは霧散した。
僕はこれまで50本を超える映画音楽を担当し、多くの監督と仕事をしているが、第一感がベストだったというケースが結果的には多い。
しかし、確信を持てないまま悩みに悩み、譜面を前にひたすら格闘しているうち、「あ、これでいいんだ」と腑に落ちる感覚が訪れる。この瞬間こそが僕にとって何ものにも代えがたい喜びであり、作曲という仕事の醍醐味でもある。
僕はソロでの活動も行っているが、その楽しさは映画音楽のそれとは大きく異る。ソロ活動は広いサッカー場に一人で佇んでいるようなもので、何の制約も受けないが、すべての判断を自分で下さなければならない。ところが、映画では座の中心に監督がいて、その意見は絶対だ。周囲には多くのスタッフがおり、音楽もさまざまな制約を余儀なくされる。しかし、彼らと時に激しく意見の交換をするうち、予定調和に終わらない、思わぬ発想を得ることもしばしばである。そこに共同作業ならではの面白さを感じるのだ。
また、私はこんなふうに尋ねられることがある。
「まったく作風の異なる監督(たとえば北野武と宮崎駿)の音楽を、なぜ作り分けることができるのか」、と。
しかし、僕からすれば、似たような音楽ばかり作ることのほうが難しいと思う。つねに目の前の作品に全力を尽くしていると、同じタイプの仕事を続けても、二番煎じの出しがらしか出て来なくなるものではないだろうか。
僕たちが日夜、心血を注いでいる作業は、一般に「創作」と呼ばれる。その言葉には無から有を生み出すようなイメージがある。だが、文字通りの無から有を生み出すことなどできるだろうか。
聞いたもの、見たもの、読んだもの。そうした経験を創り手の個性を通過させ、新たにできあがった結晶が作品と呼ばれるものなのだと思う。僕は自分の創作の多様性を担保するために、将来の仕事を見据えた勉強を欠かさないようにしている。
『崖の上のポニョ』は、世に送り出されたばかりなので、まだ冷静に総括できる状況にはない。しかし、この映画が提示する世界は、五歳の子どもからお年寄りまで、誰もが何かを感じることができる深いものだ。そこに音楽というかたちで自分も関与できたことが、とても嬉しい。宮崎駿監督に書いた僕の音楽の中で現時点で最高の作品だと思っている。
(「文藝春秋 2008年10月号」より)