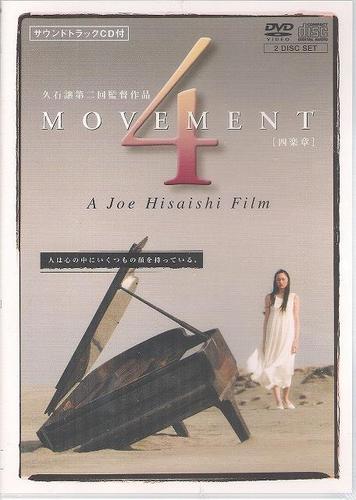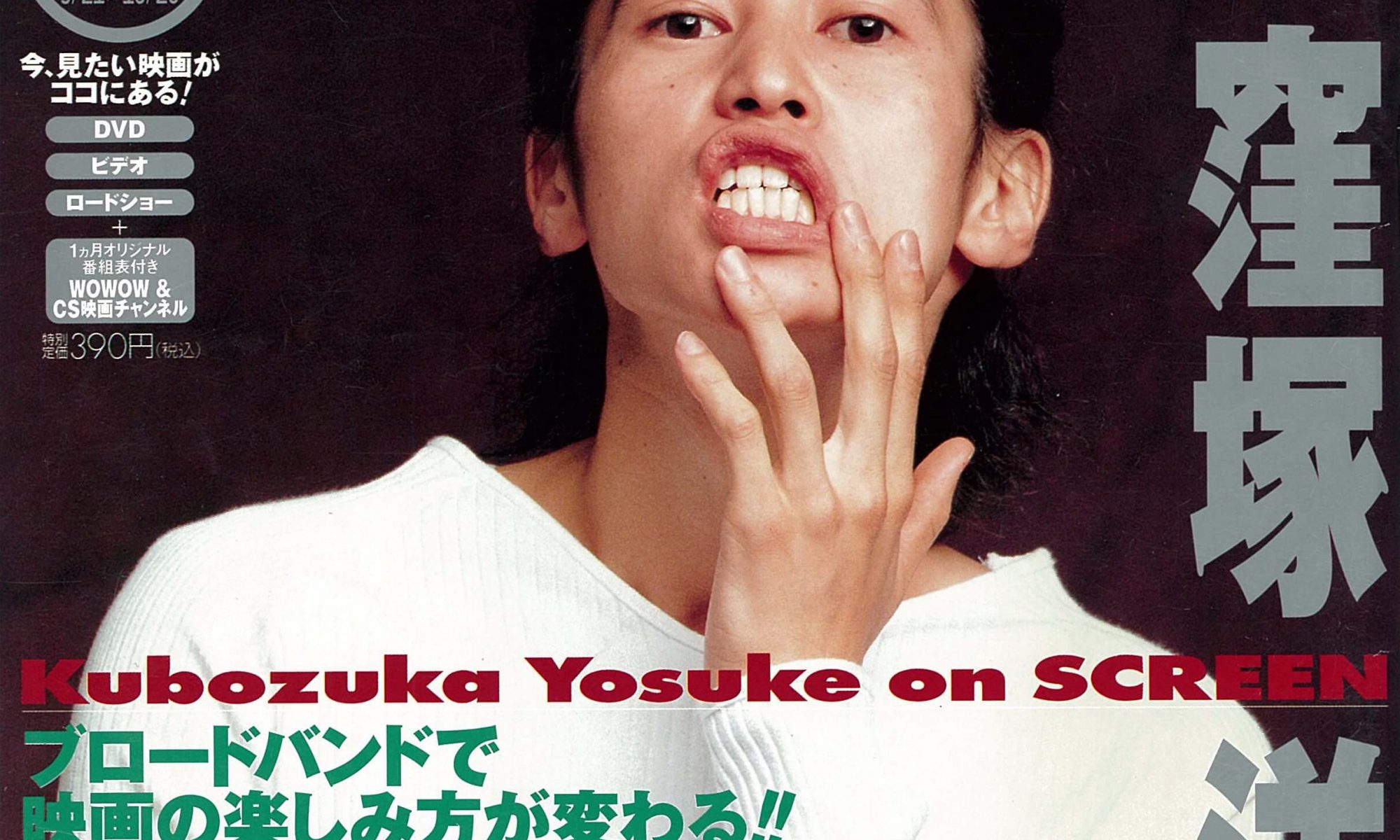Posted on 2019/03/16
雑誌「DVDビデオ・ぴあ 2001年10月号」に掲載された久石譲インタビューです。映画初監督作品『Quartet / カルテット』についてたっぷり語られています。
映画の作曲家が映画を撮るということ
久石譲インタビュー
宮崎駿、北野武、大林宣彦といった人気監督作品の音楽監督として、現代日本映画の最前線を突っ走っている久石譲が映画監督に初挑戦した。その「カルテット」は、弦楽四重奏団を組んだ若者4人を追った青春ドラマ。だが、ただの青春映画ではない。これは久石いわく「日本初の音楽映画」。映画の作曲家が映画を撮るとき、いったいそこには何が生まれるのだろうか。
取材・文=賀来タクト
監督挑戦に当たり、久石譲は映画音楽の作り手としての自身を基本に置いた。職業監督としてではなく、映画音楽へのより深い理解を得るための「経験の一つ」だというのだ。
「いろいろお誘いをいただいてきた中の一つが形になってきたときに、それならと思って引き受けたんです。あくまで僕は音楽家ですから、その僕が監督するなら、ドラマに対して音楽がいかに絡みきれるか、音楽がセリフ代わりにものを言うように作れるか、そういうことにこだわってみたかった」
言葉を超えた映像と音楽のジョイント。久石が目指した映画こそ「日本初の音楽映画」であった。そういう理想にかなった作品は海外でもそんなに見当たらないと、苦笑いが漏れる。
「あえていえば、ジョン・コリリアーノが音楽をやった『レッド・バイオリン』くらいかな。黒澤明監督が”映画的”なる表現をされていましたね。音楽と映像が深く絡んでいったときに、そういう映画にしかできないものに迫れる瞬間って必ずあると思うんです。そういうところに1シーンでもいいから到達したかった」
偶然と言うべきか、「レッド・バイオリン」さながらに、その初監督作品「カルテット」では弦楽器とドラマが巧みに絡みあった物語が展開する。学生時代、弦楽四重奏団を組んでいた若者4人がふとしたことで再会、それぞれ人生の転換期を迎えていた彼らが今一度カルテットのコンクールに挑戦するというもの。随所に描かれる演奏シーンのために、久石は撮影前に使用する楽曲40曲を全てオリジナルで書き上げ、それに合わせて撮影を進めた。
「全体の半分弱くらいが音楽シーンで、時間軸に固定されますから、構成自体は難しくなかったんです。でも、セリフの投げ合いで感情を引っ張りすぎると音楽シーンのパワーがなくなっちゃうから、芝居は極力抑える、カメラは引くって決めてましたね。そういう意味では、北野監督的なやり方だったんですよ。過剰に説明をせずに、どこまで引いて見せるかという意味ではね。武さんは僕が映画を撮るというのを知っていたんです。あるとき一緒にご飯を食べていて、武さんが大杉漣さんに話をしていたんですよ。”ラーメンをおいしく撮る方法って、いかに本当においしいかと見えるようなカットを撮らなくちゃいけないんだよ。たいがいの監督がしくじるのは、いかにうまいかという内容を説明しちゃうから。トンコツ味でとか昆布のダシでとかさ、そうするとトンコツが嫌いな人はそれを聞いた瞬間、半分引いちゃうんだよな”って。大杉さんに話をするフリをして、たぶん僕に言ってくれたんだと思う。それがすごく残っていて、大変なヒントをいただきましたよね」
ちなみに、撮影現場では主要スタッフに使用楽器の譜面が手渡された。小節ごとにカメラの動きやアングルを決めるなど、絵コンテ代わりに使ったのだ。必死だったのはスタッフばかりではない。役者陣は楽器の実演を余儀なくされ、場面によってはプロに眼前で演奏をしてもらう、その動きにならいながら演奏シーンを撮ったのだ。
「音楽映画と謳っていながら、役者さんが本当に弾いているように見えなかったらアウトじゃないですか。演奏で観る人を引かせないようにするのは難しい。日本でそれをうまくやっている映画ってあまりないですよね。なおのこと譜面を渡されたスタッフもパニクってましたけれども(笑)」
撮影を終えてしばらく経ったある日、主人公の第1バイオリン奏者・明夫を演じた袴田吉彦に問えば「僕にとって素に帰る映画になっちゃいました」という声が返ってきた。演奏シーンの大変さに加え、芝居も概ね任されていたことが自分の原点を見ざるを得ない結果になったというのだ。
「それはすごく嬉しいな。本当に袴田くんでなかったらこの映画はできなかった。袴田くんの役は、父親の想い出のために音楽を愛していながら恨んでもいるという矛盾した気持ちを抱えていて、最後の最後まで笑わない。そんな女性から見たら嫌みな男をどう魅力的に引っ張るかっていうことでは脚本の段階から悩みましたし、逆にステレオタイプに陥らない人間を描けたという満足感も大きいですね」
ドラマ自体に目を移すなら、そういった「引きの視点」がもたらした独特の味わいに注目すべきだろう。どこか喉越しのスッキリした「涼しい映画」になっているのだ。
「あ、そこのところ、太字で(笑)」
破顔一笑。
「そう、泣かそうと思えば、そういうシーンはいくらでもできる。でも、観る人の心に作品を残したいのなら、寸止めにするというか、過剰な情報や先入観を与えちゃダメなんです」
日本の空気とは思えないサラサラ感があると言おうか。「カルテット」には湿気の少ない空気感が確かにある。
「ありがたいなぁ。まずウェット感をどう取っていくかというね、日本的情緒をとにかく外していく作業に徹しましたよね。それを日本の風土で撮るのは大変なんです。スタッフには”なぜもっと芝居をさせないんだ”という気持ちがあったと思うんです。その中で初心を貫いていくことは精神的には大変でしたね。その辺は”初監督で何も知らないので”といって押し通しましたけれど(笑)」
あとで振り返っても「カルテット」には嫌みなクドさがない。
「この映画、2回観た人の反応がいいんですよ。芝居や何かを全部言葉でやっていると2回観たいとはあまり思わないですよね。でも、音楽は2度聴いても嫌にならない。その音楽が今回、セリフ代わりになってますね。リピートに耐える映画になったかと思うと、とてもうれしいですね」
実は撮影を1年前に終えてしまっている「カルテット」の後、久石は既に監督第2作を撮りあげていた。その「4 Movement」では、音楽映画という括りはなかった。つまり、音楽家としてではなく、より純粋に監督という立場で撮った作品になったといえるのだが……。
「音楽家として最低にやりづらい作品でした。画が全部音楽的なカットなんです。音楽でやるべきアクセントやリズムというものを画が全部やってしまっていて、それに音楽で上乗せするなんて過剰でしょ? 一番やりづらい監督は久石譲ですね(笑)」
映画監督を経験して「脚本の読み方が深くなった」と、再び顔が締まる。理想の映画音楽とは何かを探るための経験は、想像以上の結実を希代の作曲家にもたらしたようだ。
「映画って”映る画(うつるえ)”って書きます。武さんはそれを”1秒間に24枚の絵が映し出されるもの”という表現をされた。僕にとってはアクション、動くことなんです。『カルテット』では音楽シーンを格闘技ともいうべきアクションで考えていました。セリフのない『4 Movement』では人の動きの部分部分を追っていきました。その動きをつかまえるということを、もっとやってみたい。映画は全部が出ますから、もっと自分を磨いてね。そんな気持ちが残ったのは確かです」
映画監督・久石譲が再登場する日はそう遠くはなさそうである。
(DVDビデオ・ぴあ 2001年10月号 より)