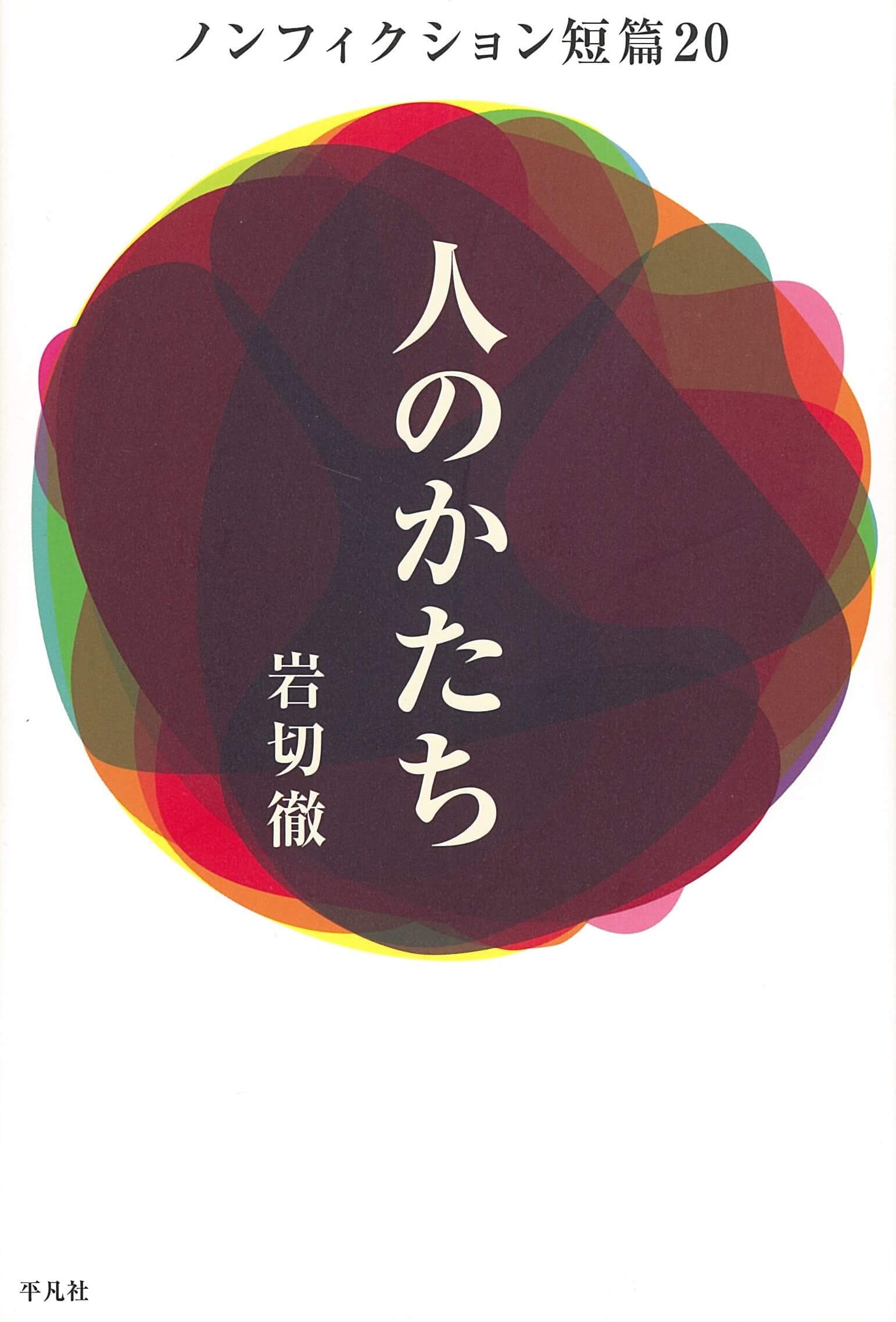Posted on 2015/1/15
遡ること5年前、2010年の雑誌インタビュー内容です。
雑誌「AERA」 2010年11月1日号 No.48 より
とても独特なタッチで書かれている久石譲論で、さらに掘り下げ方もおもしろい引き込まれる内容です。本文中にもありますが、時期的には、ミニマル・ミュージックを軸にフルオーケストレーションで華やかに昇華、新たな境地を開拓した『ミニマリズム』(2009年)から、ファン投票も募って親しみある久石メロディをシンフォニーとして彩った『メロディフォニー』(2010年)あたり。
この芸術性の『ミニマリズム』と大衆性の『メロディフォニー』の両軸をもって音楽活動をしている久石譲にぐっと迫った内容です。それは久石譲というペンネームから藤澤守という本名。名前や人格においても音楽活動で見え隠れする両軸。そして線引させたい本人の意向。いろいろな当時の模索や葛藤が見えてくる内容です。
芸術と大衆性のはざまで闘う全身音楽家
最新アルバム「メロディフォニー」では、自らの代表曲をロンドン交響楽団が演奏した。私たちの知っているあの歌が、まったく別の印象をまとって立ち上がる。作曲、編曲、指揮、ピアノ演奏-音楽のすべてに貪欲に、進化を続ける。
『笑っていいとも!』の「テレフォンショッキング」に久石譲(59)が出ていた。ご覧になった読者も多いだろう。映画『悪人』でモントリオール世界映画祭最優秀女優賞を受賞した深津絵里の紹介である。『悪人』の音楽を担当していたのが久石だ。所狭しと並んだ花輪の贈り主の中に同映画監督の李相日、主演の妻夫木聡、ほかにスタジオジブリの鈴木敏夫、SMAPなどの名前があった。
国民的作曲家である。宮崎アニメや一時期の北野映画はもちろん、最近の話題作『おくりびと』『坂の上の雲』といった映画、ドラマの作曲も手掛けている。『となりのトトロ』や『崖の上のポニョ』の主題歌♪ポーニョポーニョポニョ~も彼の作曲。SMAPの『We are SMAP!』にも楽曲を提供している。
一方、今年の彼はモーツァルトやブラームス、ドヴォルザークなどの交響曲を東京フィルハーモニー交響楽団で指揮し、母校の国立音楽大学で弦楽四重奏の講義を開催。去年発表したのが自ら作曲し、ロンドン交響楽団で収録したミニマル音楽のアルバム『Minima_Rhythm(ミニマリズム)』だった。そう、久石には強くエンターテインメントを志向する一面と、クラシックと現代音楽を深く掘り下げたいというコアな一面があるのだ。しかも彼の場合、その二面は相反していない。『笑っていいとも!』出演直後、久石本人から話を聞くことができた。
「音楽にはたぶん、いい音楽とそうでない音楽しかないんですよ。いい音楽はシンプルです。ベートーヴェンは最大のキャッチーな作曲家ですね。タタタターンでしょ。彼の『運命』は究極のミニマル音楽です」
-天才ですか。
「うん。閃きが傑出している」
-自分のことを天才と思うことは?
「まったくない。努力型ですよ、ぼくは」
理詰めと直感の試行錯誤でたどりつく「シンプル」
朝起きてコーヒーを飲んでからピアノの練習を始め、午後1時から深夜の12時まで作曲の仕事。家に帰って早朝までクラシックの研究をし、4時間寝た後、コーヒーを飲んでピアノの練習……と、久石はほぼ24時間音楽漬けの生活を送っている。
「いつもフル回転です」というのはユニバーサルミュージックの寺舘京子だ。「休んでるところを見たことがない。彼の音楽的な二面の一面がフル回転している間に片面は休む。そうやって交互に休んでいるとしか思えない。せっかちですよ。キキキキッと分刻みで移動する」
1990年代初頭、久石は3年ほどロンドンに住んでいたのだが、そこへ出張したレコーディングエンジニアの浜田純伸は「絶対ズルをしているはずだ」と思い、久石の生活を観察したことがある。「でもほんとに音楽漬けでした」と浜田。「人に厳しい人です。でもそれ以上に自分に厳しい」。同僚の秋田裕之が合いの手を入れる。「論理的。怒るときも論理的」。浜田「詰め将棋で詰まされるようなもんですね。それにとにかくタフ。納得するまで絶対諦めない。周りはヘトヘトです」。
久石によると「作曲の95%はテクニック」であるらしい。95%までは理詰めで緻密に構築していく。残りの5%が、いわば直感の領分なのだが、論理を超えた何かを掴むまで自分を追い込み、まだ形にならないアイデアを頭の底に泳がせておく。すると思わぬところでブンと、たとえばトレイや布団の中でメロディや音の形が浮かぶ。その後は95%の枝葉をばっさり切ったり、1音の上げ下げに何日も悩んだり、あらゆる試行錯誤を繰り返し、「これだ」と確信できてはじめて曲の誕生となる。2週間徹夜することもざらである。それだけの複雑を経由して久石はようやく自分の「シンプル」を手に入れるのだった。
-休まないんですか。
「休むと作曲の回路を再起動させるのが大変なんです」と久石。「それなら休まない方がいい」
作家性にこだわる人だだろう。『悪人』(2010年)で久石の胸を借りた監督の李相日は久石とがっぷり組んだ組み心地を「開きながらもプライドの高い方です」と語ってくれたが、そのプライドが彼の作家性である。「映像と音楽は対等」という構えを崩さない。注文通りの作曲なら95%ですむ。しかしそんな予定調和の仕事からは何のダイナミズムも生まれない。対等な関係で「監督のテーマをむき出しにする」のが彼の仕事であり、その作家性を担保しているのが彼の5%だった。
ミニマル音楽というのは最小限の音形を反復しながら微妙にズラしていく音楽だ。最初から最後まで主旋律がシンプルな四つの音だけで展開される「運命」が究極のミニマル音楽だというゆえんである。1960年代にアメリカで起こった。情感を催促しないそのスタイルは都会的で知的だが、民族音楽の影響も多分に受けている。その方法論は今では定着し、映像と両立した活動をしている世界的なミニマル音楽出身者として、たとえば『ピアノ・レッスン』のマイケル・ナイマンや『Mishima』のフィリップ・グラスがいる。久石もその一人だ。映画『キッズ・リターン』や『菊次郎の夏』の音楽といえばわかりやすいと思う。
バイオリンを習い始めた4歳のときから将来は音楽家になろうと決めていた。中学2年のときに作曲家になると決意。大学は作曲科に入ったが、すでにクラシックには興味が持てず、不協和音の多い難解な現代音楽にのめり込んでいた。そんな20歳の彼を圧倒したのがミニマル音楽であり、「ここはまだ音楽の可能性がある」と久石は直感した。
久石譲の名前を付けたのは21歳のころだ。友だちと酒を飲みながら、当時活躍していたクインシー・ジョーンズに漢字を当てて命名した。「特別好きなミュージシャンというわけでもなかったし、深い意味は何もないんですよ」と久石。
自分の音楽だけを探究する「芸術家」生活は20代の終わりまで続いた。理論と理屈にがんじがらめになって行き詰まるのだが、やるだけやった久石は迷わず商業ベースに転身し、CMや映画音楽、アルバム制作を少しずつ手掛けていた、そんな1983年のある日、『ナウシカ』準備室から声がかかったのだった。
宮崎、北野映画に与えた「5%の魔法」
すぐ彼に決まったわけではない。候補者には坂本龍一、細野晴臣、高橋悠治、林光といった錚々たる名前が並んでいた。前年に徳間グループ系列からアルバムを出していたので、その関係者の推薦でほとんど無名だった久石に声がかかったのだ。絵の作業に忙殺されていた宮崎駿監督の代わりにプロデューサーの高畑勲が音楽監督を務めていた。
「ずいぶん悩んでましたが、結局高畑さんの決め手は性格でしたね」と語るのはスタジオジブリのプロデューサー、鈴木敏夫である。「久石さんのそれまでに作った曲を聴いて、この人は高らかに人間信頼を歌い上げることのできる人だって見抜いたんです。賭けでした」
そこで高畑が久石に依頼したのがイメージレコードの制作だ。宮崎の書いたタイトルと詩に近いメモをもとにテーマ曲を書いてくれという宿題。
「届いたメインテーマを聴いて不安は吹っ飛びました」と鈴木。「間違ってなかったと思った。本人は否定していますが、だから、久石譲という作曲家を発見したのは高畑さんなんですよ。宮崎も絵を描きながらその曲を何度も何度も聴いていた」
それが『風の谷のナウシカ』(84年)のメインテーマとなった「風の伝説」である。それまでの久石のすべてが入っていてすべてが始まっている曲だ。映画は大ヒットした。この一作で久石は世に出た。
北野武監督との第1作は『あの夏、いちばん静かな海。』(91年)。こちらは請われて参画した。セリフのない映像に淡々と音楽が流れ、その映像と音楽の平行線が観客の頭の中で次第に交わっていく作品だ。その後に『ソナチネ』(93年)、『キッズ・リターン』(96年)、『HANA-BI』(98年)、『菊次郎の夏』(99年)と続く。いずれも北野映画の代表作である。北野映画では久石が20代のころ目指していた音楽がストレートに出ている。「偶然ミニマル同士が出会ったんですよ」。映画音楽ライターの前島秀国は言う。「北野さんも削ぎ落としていくミニマルな作風。北野ブルーといわれる空の色と久石さんの音楽のトーンがユニゾン(同調)するように、二人のミニマリストがユニゾンしていた」
北野は論理の前提に意識的な作家だ。「赤信号みんなで渡れば」式に、立てた論理の前提をひっくり返す。映画の外から来た彼は次々に映画の「前提」をひっくり返した。構造主義と時代的・手法的に通底しているミニマル音楽も西洋音楽、もっというと西洋中心主義・人間中心主義の前提を疑い、その袋小路から脱するための方法だったのではないか。前提に意識的な二人が組んだのだからあの数本の名作は成立していた。しかし、二人のコラボは『Dolls〈ドールズ〉』(02年)を最後に見られなくなった。
「最近の記事で北野さんが一種の音楽不要宣言をしていた」と前島は言う。「『自分は情緒とかいったものを音楽に任せないし、頼らない』と。だったら音楽家と上手くいくわけがない。しかし久石さんと別れたのは北野映画にとってすごい損失でしたね。久石さんの5%、つまり魔法の力を失ったわけですから」
「音楽が見えなくなった」時代の混迷に敏感に反応
一方『ナウシカ』以降、四半世紀以上続いているのが宮崎・久石コンビだ。個別に取材した話をもとに、ここで架空のシンポジウムを一つ組んでみたい。題して「久石譲と宮崎アニメの現場」。
宮崎駿 「久石さんには無礼の限りを尽くしました。『主題歌は別の人のを使います』とか。『ぼくは音楽家なんだから』と彼が言ったのを覚えている。『21世紀に新しい旋律なんて残ってないんだから前のでいいんじゃない』と言ったこともある。腹の中は煮えくり返りながら久石さんは笑ってごまかし、こっちも笑ってごまかしながら平気で言ってきた」
-『天空の城ラピュタ』(86年)のときはほかの候補者がいたとか。
宮崎駿 「その方は色数が少なかった。長編アニメは一種のカーニバルですからね。その側面は外せない。『となりのトトロ』(88年)のとき、久石さんの曲を聴いて『せわしいです』といったら、すぐその場で彼が一括りずつ音を抜いていった。すると見事に気分が合ったんです。そういう経験が何度かある。彼とはどこかで同期している」
高畑勲 「『風のとおり道』はどこか懐かしい、しかし古臭くない、これぞ日本的なものと現代人が思いたくなる曲です。歌謡曲で少しずつ市民権を得ていた二・六抜き短音階を、理想的な『自然』と結びついた新感覚として定着させたんじゃないでしょうか」
鈴木敏夫 「歌に関して言うと『トトロ』の主題歌は難産でした。久石さんは有線放送で子どもの歌を一日中聴いてたみたいですが、それでも出来なくて七転八倒していた。半年以上かかりましたね。『さんぽ』とともに今では教科書にも載っている名曲です。『ポニョ』は打ち合わせの場で閃いてパッと書きとめていた。本当です。でもすぐ発表すると否定されるからって隠していた(笑)」
宮崎アニメでは草木国土悉皆(そうもくこくどしっかい)が生きている。宮崎駿はアニミズムの作家だ。アニメーションのアニメート(生命を吹き込む)力を極限まで使ってカーニバルする宇宙を一つアニメートする。その映像と緊張をはらみながら交響するのが久石の音楽だった。
「しかし21世紀になって音楽が見えなくなるんですよ」。久石は言う。「その前は時代時代の語法があったんだけど、世界の混迷とリンクするように音楽も向こうが見えなくなった。時代を追いかけてもしょうがない、じゃあ確実に見えるところからやろうと、ぼくの原点であるミニマル音楽とクラシックに戻った。9.11も大きかった。それまで社会現象とは無関係に音楽を追究していたんですが、このままだと世界は大変なことになると思うようになって作ったのが弦楽合奏のための『DEAD』。エンターテイメントだけじゃ満足できなくなったんです」
いま彼がもっとも意識している作曲家はミニマル出身者でクラシック音楽とオーケストラを知り抜いているジョン・アダムズだ。「いつか彼のオペラ『ドクター・アトミック』を日本で指揮し、条件さえ整えば数年かけてじっくり自分のオペラを書きたい」
微妙にズレながら久石の音楽観は大きくグルッと一回転したのである。ミニマル音楽の可能性を掘り下げ、作曲家の視点でクラシックの交響曲を分析・解読し、実際にタクトを振るという作業が始まった。クラシックの巨匠たちがいかにカオスから秩序のミニマル(最小限)なパターンを発見し、織りなしていったかを読み込んでいく作業といってもいい。
前島によると久石の大転換点は『もののけ姫』(97年)だったらしい。宮崎監督の重い世界観を表現するために複雑なオーケストラ曲を本格的に書いたのがクラシック回帰のきっかけになったと。その後『千と千尋の神隠し』(01年)でユーラシア大陸をまたぐワールドミュージックを展開し、再びクラシックに戻ってシンプルなワルツのテーマ曲を変奏していたのが『ハウルの動く城』(04年)であり、ポニョの旋律を変奏していたのが『崖の上のポニョ』(08年)だった。ポニョの本名はブリュンヒルデだから、あの映画は宮崎版『ニーベルングの指環』といえなくもない。
「久石さんとは同じ時代を生きてきたと思う」。宮崎が語る。「作るに値する映画はいつの時代にもあるだろうという仮説のもとにやってきました。そのたんびにいっしょにやろうと。ここまで来たら最後までいっしょにやると思う。彼の音楽はぼくの通俗性と合っているんですよ。彼の音楽の持ち味は”少年のペーソス”です。それは彼のミニマルの底流にもあるし、『ナウシカ』のときからあった。映画によって隠したり、ちょっと出したり、うんと乾いて見せたり。手を替え品を替えやりながら生き残ってきた人だから、そう簡単に手札を見せるわけがない。でも”少年のペーソス”はずっと変わっていない。そこがたぶんぼくと共通している」
たぶんそれは北野とも共通していたと思う。彼の映画にはシャイな少年が隠れている。似ているから離れ、似ているから続く。似たもの同士、しかもそれぞれの5%で生き残ってきた作家たちの間ではそのどちらかしかないのだろう。
作曲、編曲、指揮、演奏 音楽の可能性を信じて
久石の少年時代は久石ではない。久石譲は20歳過ぎに付けた、いわば「芸名」だ。そう、地元・長野で高校教師をしていた父の映画館巡回に付き添って年間300本の映画を観たり、バイオリンからピアノにトランペット、サキソフォン、トロンボーン、打楽器までマスターし、アレンジに優れ、中高時代から難解な現代音楽に挑み、20歳のときにミニマル音楽を聴いて「ここにはまだ音楽の可能性がある」と叫んだのは久石ではない。本名の藤澤守だ。彼がそっくり久石の少年時代を占めている。久石は自分と藤澤守の関係についてこう語る。
「人間って元に戻りますね。ぼくはやっぱり藤澤守なんですよ。去年『ミニマリズム』を作るときに作曲者名は全部、藤澤守でやろうと思った。エンターテイメントは久石でやっているけど、作品は藤澤だろうと。2日に一遍はそのことを考える。今度の曲は絶対藤澤守で出してやるぞと」
-でもそうしたら売れない?
「うん。いつか作曲・藤澤守、指揮・久石譲でやりたい。それが理想ですね、ぼくの」
久石は二人分の人生を生きているのだった。時間が足りないわけである。
(雑誌「AERA 2010年11月1日号 No.48 文:岩切徹 より)
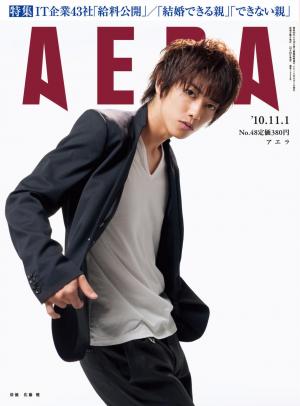
*この本文は、時を経て『人のかたち ノンフィクション短篇20/岩切徹』(平凡社・2015刊)にて連載をまとめて書籍化のなかにも収載されました。