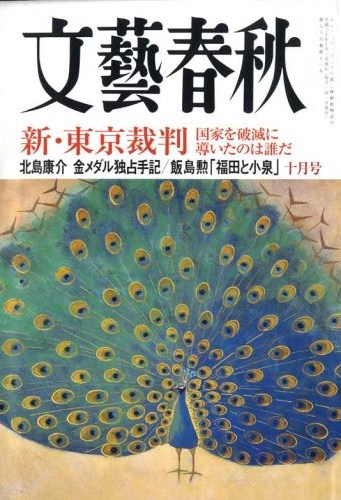Posted on 2015/1/31
2010年4月2日発売 ムック(書籍)
キネ旬ムック キネマ旬報特別編集 「オールタイム・ベスト 映画遺産 映画音楽篇」
映画情報誌としても有名なキネマ旬報の特別編集版ムックです。「オールタイム・ベスト 映画遺産200 《外国映画篇》」「オールタイム・ベスト 映画遺産200 《日本映画篇》」というそれぞれの書籍と同様に別枠で1冊にまとめられたのが「オールタイム・ベスト 映画遺産200 映画音楽篇」です。
300ページにおよぶ映画音楽年鑑のようになっています。
- 映画音楽が心にし残る映画 1位~20位紹介
- ジャンル別映画音楽ベスト10
- 心に残る映画歌曲・テーマ曲ベスト
- 好きな映画音楽作曲家ベスト
- 映画音楽の歴史
目次からの一部抜粋だけでもこういった感じです。もちろん洋画・邦画を総合的に扱っていますので、やや洋画が多い。錚々たる映画音楽作曲家が1ページごとに紹介されている項もあります。国内外問わず、そして年代を問わず、オールタイムな映画音楽の事典。
その中で、映画音楽作曲家インタビューで2人だけ取り上げられています。一人は冨田勲、そしてもう一人が久石譲です。8ページに及ぶロングインタビューです。
映画音楽のみならずTV・CM、そして現代音楽など、多岐にわたる作曲家としての顔をもつ久石譲ですが、ここでは《映画》そして《映画音楽》にフォーカスしてのインタビューですので、かなり映画音楽家としての久石譲に迫った内容になっています。
読み応えも満点です。感覚的に映画および映画音楽を楽しむのはもちろんのこと、「いろいろな背景や考えで、ここにこの音楽か」と作曲者の意図や思考に思いを馳せながら聴くのもまたおもしろいです。
70本以上の映画音楽を手がけてきた久石譲だからこそ、邦画からアニメーションまで、さらには海外作品まで手がけてきた久石譲だからこそ、語れる【映画音楽論】になっています。派生してインタビューで紹介されている、久石譲が印象に残っている映画や映画音楽も気になってきてしまいます。
別頁にて、同書籍より「映画音楽の歴史 ミニマルミュージック」も紹介しています。
Blog. 「オールタイム・ベスト 映画遺産 映画音楽篇 」 【映画音楽とミニマルミュージック】 コラム紹介
映画音楽 作曲家インタビュー 久石譲
いちばん重要なのは、映像と音楽が対等であること
(取材・文:前島秀国)
映画音楽とはいったい何か
「風の谷のナウシカ」(84)から今年公開予定の最新作「悪人」(10)まで、常に日本映画の最前線で音楽を手がけてきた久石譲。作曲家としての活躍に加え、指揮者・ピアニストとしても映画音楽に深く関わり続ける彼に、まずは映画音楽の本質について訊ねてみた。
久石:
「これまで70本近い映画音楽を書かせていただきましたが、自分の中で『映画音楽とはいったい何か?』という疑問が未だに続いています。そもそも、映画音楽というものは、映像に付くものです。ところが、映像の中で展開している日常のドラマでは、本当は音楽が鳴っていないのですよ。それに敢えて逆らうような、いちばん不自然な形で音楽が流れてくる。観客の情緒を煽るためかというと、そうでもない。オーケストラで素晴らしいスコアを書いたら、それがいい映画音楽になるとも限らない。『パリ、テキサス』(84)のように、ライ・クーダーが奏でるギター1本のほうが、オーケストラよりもずっと心に沁みる場合もあります。このように、映画音楽の定義は非常に難しいのですが、基本的な作曲スタンスとしては、やはり映像と音楽の新鮮な出会いを追い求めていくことではないかと。毎回新しい発見がありますし、今でも答えを探し続けているというところでしょうか」
映画音楽は大きく分けて3つのタイプに集約できる
久石によれば、映画に音楽が付くケースは、大きく分けて3つのタイプに集約することができるという。
久石:
「第1のタイプは、ハリウッド映画に象徴される”テーマ主義”。『スター・ウォーズ』(77)のように、登場人物ごとにテーマをあてはめながら、画面をわかりやすくしていく手法です。テレビの場合にも言えますが、万人に訴えかけるエンターテインメントを作ろうとする時、この方法は決して悪い手法ではないんですよ。第2のタイプは”メインテーマ方式”あるいは”ライトモティーフ方式”と呼ばれるもの。このタイプには2つのサブタイプがあって、ひとつは『ティファニーで朝食を』(61)を例に挙げると、『ムーン・リバー』のような主題曲を作ることで映画全体のイメージを凝縮してしまう手法。『あ、この曲が流れる。とてもよかったね』と観客を納得させる方法です。もうひとつは、音楽を”第三の登場人物”のように鳴らしていく方法。本編の中で流れる回数は少なくても、あるいは劇の動きと合っていなくても、『なぜこの映画に、このモティーフが鳴るのか?』と観客が違和感を覚えるくらい明確に音楽を鳴らし、台本の求めている世界を表現していく。これは、どちらかというと社会性を帯びた作品、あるいは知的レベルの高い作品に多い手法です。第3のタイプは、音楽なのか効果音なのかわからない、いわばトータルで映像と音楽の関係を問い直す手法。これは、むしろアートに近いですね。昔のATG映画のように商業路線から距離を置いた作品か、あるいは作曲家がよほど監督の信頼を得ていないと使えない手法です。以上の3つのタイプに付け加えるものがあるとすれば、場所の状況の中で鳴る音楽、つまり喫茶店や酒場で流れているBGMの類ですが、これが実は非常に重要だったりします。このように映画音楽のタイプを論理的にカテゴライズした上で、いま頂いている台本に対し、どのようなスタンスで書いたらいいのか、それを絶えず意識しながら作っているところがありますね」
ちなみに、かつて久石は『ムーン・リバー』を、”理想的な映画音楽”として挙げたことがある。
久石:
「あれが映画音楽のひとつの理想形だと思うのは、映画全編がひとつのメロディで有機的に結合しているからです。まず、冒頭のタイトルバックでコーラスが『Moon river, wider than a mile…』といきなり歌い始めるでしょう? そのメロディを劇中でオードリー・ヘップバーンが歌いますが、あのギターの弾き語りのシーンなど、永遠に頭に残りますよね。よく言うのですが、良い映画には”良い映画音楽”と”悪い映画音楽”がある。ところが、悪い映画には”悪い映画音楽”はあっても”良い映画音楽”は絶対にない。残念ですが、元の本編が悪かったら、音楽だけ生き残ることはないのです。映画音楽というものは、あくまでも映像との相乗効果で力を発揮してくものですから」
メロディは映画音楽を象徴する”顔”
その『ムーン・リバー』のように、主題歌や主題曲のメロディは映画音楽の代名詞といっても過言ではない。作曲家の視点から見て、映画音楽のメロディとはどういうものだろうか。
久石:
「メロディは”コンセプト”と同義語です。例えば、最初に台本を頂いた段階で『この作品は、どのような音楽でいこうか』と考えるとします。オケが合うのか、室内音楽が合うのか、あるいはエレキギター1本だけでいくのか、打楽器だけでいくのか。そうしたアイディアを練り上げていくうちに、自分の考えのいちばん象徴的な部分、人間の部位で言うと”顔”に当たる部分が、メロディの形を採ってくるのです。『崖の上のポニョ』(08)の場合ですと、ポニョのメロディが浮かんだ瞬間、バックの音もこういうオケの音が合う、というのが必然的に決まりました。多くの場合、観客の記憶にいちばん強く残るのは、作曲家のコンセプトが表面に出てきたメロディです。そのメロディの持っているムードが画面に合うか合わないかで、映画音楽の良し悪しが決まると言っても良いでしょう」
久石が、自身の音楽的ルーツであるミニマルミュージックの語法を用いて映画音楽を作曲する場合にも、基本的には同じことが言えるという。
久石:
「ミニマル系の短いリズムパターンを主体にして書く時も、そのパターン自体がひとつの音形というか、メロディです。いわば、いちばん短い形のライトモティーフ。そのパターンが、音楽の核となる最も重要な部分です。そうしたセンターに来る要素を、初めにきっちり捕まえておかないと、周りからじわじわ攻めていっても肝心なものを逃してしまうことになります。このようにメロディやミニマルのリズムパターンは、映画音楽を考えている時のいちばん象徴的な部分ですね」
映画音楽の95パーセントはテクニックで決まる
そうしたメロディに加え、映画音楽では歌やオーケストラ、バンドなど、さまざまなスタイルが重要になってくる。
久石:
「先ほども例を出したライ・クーダーは非常に優秀な音楽家ですが、ギター1本という彼の特殊な方法論は『パリ、テキサス』のような作品に対して有効なのであって、すべての映画に対応できるわけではない。そうすると、彼を果たして映画音楽家と呼んでよいのか、という問題が出てきます。映画音楽家という看板を掲げる以上は、いろいろな作品に対応しなければならない。自分固有の音楽スタイルを持つことは絶対に必要ですが、そのスタイルの中からシリアスなもの、コミカルなものを書いていかなければならない」
画面と音楽を合わせていく時、その95パーセントはテクニックで決まると久石は断言する。
久石:
「例えば、2時間の映画を手がける場合、1本につき30数曲、ややシリアスな作品で曲数を減らしても15~16曲を書かなければなりません。それらの曲を本編のどの部分に付けるのか。いわば、音楽が流れない沈黙の部分も含めた、2時間の交響曲を書くようなものです。メインテーマがひとつ、サブテーマが複数あるとして、それらのテーマをどのように配置していくか。同じテーマを悲劇的に使ったり、軽く流したりする場合も、画面と呼吸を合わせていかなければならない。それらをすべて構成し、組み立て、全体のスコアをどう設計していくか。その95パーセントは、テクニックで決まります」
まず、どの段階で作曲を始めるのか。台本を読んだ段階から始めるのか、それともラッシュを見た上で作曲するのか。
久石:
「その時の状況にいちばん左右されますね。どちらが難しいというものでもないです。例えば宮崎監督の場合は、先にイメージアルバムを作らなければいけませんから、画を見るまで待ってから書くというわけにはいきません。自分である程度予想しながら考えていかなければならない。『おくりびと』(08)の場合には、台本を読ませていただいた段階で、主人公がチェロ奏者だとわかっていましたから、おそらく彼が弾くチェロがメインテーマになるだろうと予測し、台本を読んだだけで曲を書き、結果的にそれが非常にいい結果を生み出したケースです。逆に、監督のラッシュを少しずつ見ながら、テンポやその他の情報を全部自分の中にインプットして書いたほうがいいケースもあります。『私は貝になりたい』(08)の場合がそうですね。ああいう作品の場合は、ラッシュを見てからでないと全く作れないですね」
映画音楽のテクニックで最も難しいのは、映像と音楽を合わせるタイミングだが、それは一般に”映像と音楽がぴったり合う”と考えられているような、単純なものではないという。
久石:
「最初の頃は楽譜も全部手書きで、ストップウォッチ片手に『ここは何秒くらい』とフィルムの尺の長さを計っていったのですが、実は誤差が激しいんですよ。当時はまだ若かったから『タイミングもきっちり合わせなければ』と相当無理をしました(笑)。その後(シーケンサー機能とサンプリング機能を備えた)フェアライトのような電子楽器が出てきて、予めフレーム単位の細部までシミュレーションしてからレコーディングに臨めるようになったことは大きいです。そうすると、合わせる必要のあるものと必要のないものの違いが、はっきりわかるようになる。若い頃は、俳優が驚いて表情がパッと変わった瞬間、音楽も同じタイミングで変える、というようなことをやっていたわけです。ところが実際には、表情の変化と同時に音楽を変えるよりも、少し時間が経ってから音楽を変えた方が、インパクトが強くなってカッコいいんですよ。後出しジャンケンみたいなものですね(笑)。そういうことをいろいろ経験していくうちに、なんでもかんでもフレーム単位で合わせるのではなく、音楽的な流れを事前に計算した上で、本当に合わせる必要のある箇所以外は逆に無視することができるようになる。そういう意味でも、映画音楽の95パーセントはテクニックだと思うのです」
特に久石が重視するのは、最後の仕上げ段階の微調整だという。
久石:
「監督と事前の話し合いをしっかり行い、シンセサイザーで作ったラフな段階で音を確認していただきます。実はその後、音楽をガラッと変えることもあるんですが(笑)。つまり、最後の仕上げ段階で、微調整にじっくり時間をかけていく。監督にシンセ音源で確認をとった後、何度も見直していくうちに『ここはまだテンポが早い』と感じたら、ほんの数小節削り、全体のテンポをゆったりさせながら、画に馴染ませていくのです。録音当日、そこまで監督が気づくことは、まずありませんが。あとはきちんとした譜面を書いておけば、録音そのものは早いです。書いてしまえば、それをオーケストラが演奏するだけですから。現場対応でなんとかするのではなく、すべて前もって周到に準備しておかないとダメですね。」
映画監督と作曲家の理想的なスタンス
映画音楽が他の音楽活動と決定的に異なるのは、音楽の最終決定権が監督もしくは製作サイドに属するということだろう。久石の場合はどうだろうか。
久石:
「普段、ひとりで音楽をやっている時は、他人の意見が介入してくると音楽が成立しなくなる可能性が出てきます。ところが映画音楽の場合は、幸運なことに、発想の基準は常に監督の頭の中にある、というのが僕の考えです。特に、映画は監督に帰属するという意識が強い邦画の場合は、そうですね。例えば、僕らが映画音楽を書く場合、その期間は長くて半年か1年くらいです。ところが監督に関しては、その人が職業監督でない限り、自分で台本を書く場合にせよ、脚本家に注文をつけながら撮影稿を練っていく場合にせよ、ひとつの作品にだいたい2、3年の時間を費やすわけです。それだけの時間をかけた強い思いが、監督の頭の中にある。その意図を考えながら作曲していくというのが、僕のスタンスですね。監督から注文されたことに対し、明らかにそれは違うと感じた場合は意見を申し上げますけど、それ以外は、監督の意図を自分なりに掴み、音楽的にそれを解決しようと努力します。すると、ひとりで音楽をやっている時には予想もつかなかった、新たな自分が出てくるんですよ。『俺にはこういう表現ができるんだ』という。もっとダークなやり方でも音楽がいけそうだとか、メインテーマさえしっかり書いておけば、30曲あるうちの5、6曲は実験しても大丈夫そうだ、といったことが見えてきます。そういう意味で、映画音楽というのは、普段気になっている方法を実験する機会を監督に与えていただく場所でもあるのです。自分にとっては、非常に理想的なスタンスですね」
そうした監督の中でも、特に宮崎監督は別格だという。
久石:
「やはり、いちばん大きな影響を受けた監督ですね。凄まじいです。知識としての音楽ではなく、ある音楽が自分の映像に合うか合わないか、それを瞬時に判断する感覚がずば抜けているのです。もちろん、今までご一緒させていただいた監督も、皆さん聡明な方ばかりですよ。僕は基本的に、映画監督という存在をリスペクトしています」
日本映画の作曲と海外作品の作曲の違い
21世紀以降、久石は「Le Petit Poucet」(01)、「トンマッコルへようこそ」(05)、「おばさんのポストモダン生活」(06、映画祭上映)など、海外作品にも活躍の場を広げてきた。
久石:
「邦画でも洋画でも、作家としての基本姿勢は一貫して保つようにしています。つまり、台本を読ませていただいて監督が描きたい世界を把握し、単に相手側の注文に即して書くのではなく、自分が何を音楽で書きたいのか、はっきり掴むこと。この姿勢は実写でもアニメーションでも、あるいは映画でもCMでも常に同じです。ただし、方法論的な違いは存在しますが」
その最大の違いは、非常に基本的な事柄だが、台本が書かれた言語にあるという。
久石:
「中国映画の台本を頂いた時は、最初に読むと3時間くらいの長さに感じるのですが、実際には本編が2時間以内に収まるのです。つまり、言葉の情報量が日本語の台本に比べて非常に多いのですね。英語の台本も、やはり文字の分量が圧倒的に多いです。ところが、英語の場合は言語の性質のせいか、文字の分量の割に読み手に伝わる速度が速いのですよ。英語は、26文字のアルファベットしかありませんよね。その26文字を組み換えていきますから、基本的に構成力で成り立っている言語なのです。ですから、英語の台本の場合、音楽を全編に付けたとしても、音楽があんがい邪魔にならない。ところが日本語の場合、言葉を独自に作り出すところがありますから、観客は1音1音を注意深く聴きとならければならない。しかも、俳優が台詞に感情をこめたりすると、なおさら言葉が聴きとりにくくなるという面もあります。そうした台詞を聴き取れるように音楽を作っていくと(英語に比べて)自然と制約が多くなってくるのです。その意味でも、映画音楽の95パーセントはテクニックだと思うのですよ」
指揮者・演奏家の視点から見た映画音楽
映画音楽の作曲活動に加え、ここ10年あまりの久石が精力的に取り組んでいるのが、オーケストラの指揮活動。特に2004年、新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ音楽監督に就任してからは、自作に加え、他の作曲家の映画音楽やクラシックの古典曲までレパートリーの裾野を広げている。
久石:
「映画音楽がクラシックと同じように演奏され、後世に残るかどうかは、実は非常に難しい問題です。原則的には残ると思いますが、そもそも映画音楽には多くの制約があります。これまで申し上げてきたように、映画音楽は映像から生まれますから、映像と一体化した時に初めて力を100パーセント発揮するものでないといけない。ですから、映画音楽を映像から切り離し、コンサート楽曲として演奏することが、必ずしも正しい在り方とは言いきれないのです。映像と独立した形で演奏が成立する音楽もあれば、そうでない音楽もありますから」
映画音楽をコンサート楽曲として成立させるために、久石が採っている解決法はアレンジという手段である。
久石:
「そもそも、楽曲にならないような素材を映画に使っても、決していい映画音楽には仕上がりません。映画音楽に限らず、どんな場合でもいちばん大切なのは、先ほど申し上げたメロディや、ミニマルのリズムパターンといった音楽的要素です。ですから、映画音楽は潜在的に、独立した音楽作品として成立し得ると思っています。ただし、本編で用いた楽曲をそのままコンサートにかけられませんから、核となるモティーフを使って新たにオーケストレーションを施し、作品として形を成すように努力します。一度作曲したものに手を加えるのは二度手間になりますから、大変な作業ですね。もともと、過去の作品を振り返ることに、あまり関心がないのです。コンサートの準備に3ヶ月を費やすと、その間、自分の曲が書けなくなってしまいますから、だんだんフラストレーションが溜まってくるのですよ。早く作曲に戻りたくて(笑)」
映画音楽作曲家を志す若手へのアドバイス
久石のような映画音楽作曲家を志す若い読者は、何を心がけ、勉強したらよいのだろうか。
久石:
「まず、映画音楽を書く書かないに関わらず、音楽家として多くを勉強し、自己の音楽スタイルを掘り下げて確立していく。その上で、映画音楽が書きたいのならば、映画を”仕事”として見るのではなく、とにかく映画を好きになって、出来るだけ多くの本数を見ることです。映画音楽のCDをたくさん聴いて、実際に本編で使われた曲とCDの収録曲がどのように異なるか、徹底的に分析することも必要でしょう。それから、本をたくさん読むこと。映画音楽というのは、やはりドラマが重要ですから、ドラマが理解できない人には無理なのです」
ただし、いくら努力しても映画音楽作曲家になれない側面が、ひとつだけ決定的に存在するという。
久石:
「残念ながら、その人の書いた音楽が映像を換起できる資質を持っていないと、映画音楽作曲家には向いていないかもしれません。鳴った瞬間に映像に寄り添える音と、そうではい音の違いは、決定的に存在します。それは仕方ないことですね。プロゴルファーに向いていても、野球選手に向いていないことだってありますから(笑)。誰でも野球選手になれるわけではない。同じように、クラシックの現代音楽に進むのか、あるいはジャズやポップスに進むのか、それとも映画音楽の作曲に進むのか、早いうちに見極める必要があります。非常に難しい問題ですけどね」
自己の音楽スタイルに関して言えば、久石自身は現在もミニマルミュージックの現代音楽を作曲している。
久石:
「ミニマルをやってきて今でも良かったと思っているのは、音楽を持続させるために『あれもこれも』とてんこ盛りにせず、ある一定の方向で統一感をとろうとする神経が強く働くようになったことです。その方向の中で許せる、ギリギリの変化というのは『風の谷のナウシカ』(84)以降、相当やってきましたね」
「ナウシカ」のテーマ曲『風の伝説』の冒頭部分は、ポップスのようにコード進行を頻繁に変えず、単一のコードを頑なに守っているが、これなどはミニマリストとしての久石の側面が顕著に表れた例と言えるだろう。
久石:
「例えば、ひとつのシークエンスで主人公の感情が高まっていく時、音楽がミニマルの語法で微細に変化していくと、大きな効果を生み出すことは事実です。だからといって、ミニマルの語法を映画音楽に用いるのは、自分が本気でミニマルに取り組んでいない限り、バーゲンセールに並ぶ大量生産品と同じで、非常に危険なことだと思います。よく、ラヴェルの『ボレロ』は同じパターンが続くから、あれもミニマルだと勘違いしてしまう人がいますよね。『ボレロ』はオスティナートで書かれていて、ミニマルとは違うのです。オスティナートの音楽が行きつく先は(ある種のカタルシスをもたらす)クライマックスですが、ミニマルはオスティナートではない。その違いがわかっていないと、最悪の結果をもたらしてしまう。フィリップ・グラスやマイケル・ナイマンといった人たちは、自分の本籍がミニマルにあることを充分認識した上で、映画音楽のメロディを書いていますから、そこに本物の自分が投影させているのです。グラスの『めぐりあう時間たち』(02)のスコアでも、彼は自分のコンサート楽曲と同じパターンを真剣勝負で出していますね。そのくらいの意気込みでやらないといけない。ミニマルの表面だけ見て、ひとつの音形を繰り返してズラせばいい、というのは単なるファッションに過ぎません」
迷った時はキューブリックに戻る
最後に、久石が好きな映画音楽もしくは影響を受けた作品について訊ねてみた。
久石:
「個別のケースを挙げていくとキリがないんですよね。『ブレードランナー』(82)の頃のヴァンゲリスが素晴らしいとか、『冒険者たち』(67)のピアノと弦楽カルテットなんて、それだけで音楽的に価値がありますよね。最近では『グラン・トリノ』(08)が圧倒的に素晴らしかった。あのテーマの旋律、だいたい流れが予測できるのですが、何度も繰り返されていくうちに、最後は『やられた!』と思って。いつも三管編成のオーケストラで音楽を書いていると、こういうシンプルな手法がすごく新鮮ですね」
久石が映画音楽の”教科書”として挙げるのは、なんとキューブリック作品であるという。
久石:
「キューブリックの全作品は、もう本当に衝撃的ですね。既成曲を映画の中できっちり使っていくのが彼の方法論ですが、音楽の意味が100パーセント発揮されるような音の使い方をしています。『2001年宇宙の旅』(68)や『アイズ・ワイド・シャット』(99)のワルツにしても、あるいはジョルジ・リゲティ現代音楽にしても。ただし、彼の方法論をそのまま採用すると、現役の映画音楽作曲家を否定してしまうことにも繋がりかねません。我々がキューブリックから学ぶべきいちばん重要な本質は”映像と音楽が対等であること”。対等であるということは、必ずしも音楽がしゃしゃり出ることを意味しません。僕は世間で俗に言う”劇伴”という言葉が大嫌いなのですが、映画音楽は、単に劇を伴奏するだけの”劇伴”であってはならない。精神的なレベルも含め、映画音楽はキューブリック作品のように映像と音楽が対等に渡り合う”劇音楽”であるべきです。ティンパニーが細切れに『トン・トン……』と叩くだけの場合でも、映像と音楽が対等であるかどうか。それが良い映画音楽の判断基準だと僕は思っています。単に『いいメロディが書けたから、スコアできれいにまとめよう』と安易な方法に走るのではなく、どうしたらそのメロディが各々のシーンと新鮮な出会いが出来るのか、それを毎日探し求めながら『おお、こんな表現が生まれた』と実験を重ねていくのが、おそらく映画音楽の正しいやり方だと思うのです。その意味で、迷えばいつもキューブリックに戻る、という感じですね」
(キネ旬ムック キネマ旬報特別編集 「オールタイム・ベスト 映画遺産 映画音楽篇」 より)
Related page: