Posted on 2015/6/27
6月1日発売 「味の手帖」2015年6月号 巻頭対談
オリックス シニア・チェアマン宮内義彦氏のゲストとして久石譲が登場しています。対談風景を収めた写真もまじえながらの全16ページにも及ぶロングものとなっています。
音楽通同士の多彩な音楽話は、あらゆる角度・視点・時代背景から、興味深い音楽のお話が飛び交っています。久石譲も、常に語っているクラシック音楽のこと、自身が目指す「アーティメント」のことなど読み応え満点です。久石譲の今を知るというよりも、久石譲の音楽知識人としての顔も垣間見ることができます。
宮内義彦対談:
久石譲 《今の時代に必要な「現代の音楽」を届けたい》
久石 譲(作曲家・指揮者・ピアニスト)
音楽大学在学中よりミニマル・ミュージックに興味を持ち、現代音楽の作曲家として活動を始めた久石譲さん。現在は、作曲家・指揮者・ピアニストと、ジャンルにとらわれない独自のスタイルを確立し、国内外で活躍されている。先人たちが生み出したアートを未来へと繋げるために、今の時代に必要な「現代の音楽」を演奏していきたいと語る。
宮内:
ようこそおいでくださいました。
久石:
お招きいただきまして、ありがとうございます。
宮内:
以前、「オリックス劇場」と、そこに隣接するタワーマンションからなる街区「大阪ひびきの街」の素晴らしいテーマ曲を作っていただきまして、ありがとうございました。おかげさまでとても好評でした。
久石:
2012年、『Overture -序曲-』という曲でしたね。オリックス劇場でコンサートをやらせていただきましたが、公園があってホールがあって、あの辺りは文化的な一画になりましたね。あそこは、もとは大阪厚生年金会館でしたね。
宮内:
旧厚生年金会館の大ホールをリノベーションしたのです。当初はなくなる予定だったのですが、残して良かったと思っています。
久石:
とても雰囲気が良くなりました。
宮内:
久石さんは、長野のご出身でいらっしゃいますか。
久石:
はい。長野市から車で北に40~50分ほど行ったところにある中野市です。長野は鈴木鎮一さんのヴァイオリン教室が盛んでしたので、小さい時に少し習っていました。
宮内:
音楽はそこから始められたのですか。
久石:
そうです。
宮内:
学校は作曲科を出られたのですか。
久石:
国立音楽大学の作曲科でしたが、当時は、現代音楽の一番尖ったことに夢中になっており、大学のほうはあまり一生懸命行っていなかった気がします(笑)。
宮内:
現代音楽から入られて、映画音楽を含め、今やっておられる曲を考えると、ずいぶん飛躍されましたね。
久石:
自分はメロディーメーカーだと思ったことはなかったのです。大学を出てからも、しばらくは「ミニマル・ミュージック」(現代音楽の一ジャンルで、同じパターンの繰り返しから成る音楽)をずっとやっていたのですが、たまたま映画音楽はどうしてもメロディーが必要になりますから、必要に迫られてという感じなのです。
日本の交響楽団
宮内:
現代音楽でお金を稼ぐのは大変でしょう。
久石:
そうなのです。ですから、大学を出る時に大概の人は教職課程をとるのですが、僕はとりませんでした。最初からずっと、映画やテレビの仕事をやりたいと思っていたのです。ただ、20代の頃は本当に食べられませんでした。
例えば、一大学から作曲家が15人ぐらい出るとすると、音楽大学や教育大学、専門学校なども合わせて、全国で150~200人の作曲家が毎年出てくることになります。10年間で、1500~2000人です。フルート奏者も一大学で4、5人以上、時によっては10人卒業し、日本全国だと年間200人近い人が出るわけです。ところが、各オーケストラにフルート奏者は3、4人いますが、いったん入団すると、よほどのことがないかぎり定年までそのままいます。毎年200人近い人がどんどん出てくるけれども、就職場所がないのです。これは不思議ですよね。
宮内:
聞いた話によると、音楽大学を出た若い人のレベルはどんどん高くなっているのに、就職場所がないといいますね。
久石:
時代と共に技術は上がっていますから、若くて優秀な人は大勢います。ただ、やはり経験は必要ですから、例えば、一つのオーケストラにオーボエが三管編成で3人いるとすると、まずトップの人がいて、三番目のポジションに若い人が入って、だんだん実力を付けていく中で、中堅どころが音楽性をサポートしながら教えていく、こうした循環が一番うまくいくのではないでしょうか。
宮内さんは、「新日本フィルハーモニー交響楽団」の理事長をずっとなさっていますね。
宮内:
久石さんにも、いろいろお世話になっております(笑)。ありがとうございます。
私どものグループ会社にプロ野球のチームがありますでしょう。野球をやっている人はとても多いですが、プロ野球まできている人は本当のトップですよね。しかも一年契約で、今年駄目なら来年は使ってもらえないし、成績が良ければ給料は上がります。高い・安いは別としても、プロフェッショナルとして実力主義というのはなるほどと納得できるわけです。しかし、新日本フィルは一度入団すると定年制ですね。プロの世界がこれでいいのかなという感じはします。
久石:
毎日一緒に音を出していると、例えば「彼の音は浮いているね」とか、そういったことが自然に出てくることもある。でも、辞めてくださいとは言えないわけです。みんな一国一城の主で、高い技術を持った一人ずつの集団ですから、オーケストラを扱うのはとても難しい。そういった話はよく聞きます。
編集部:
海外のオーケストラには必ず日本人の方がいますね。コンクールで良い成績をおさめる日本人も多い気がしますが、日本人は器用なのでしょうか。
久石:
コンクールに受かるという目標を立てると、日本人は勤勉で練習もよくしますし、そこまでは非常に頑張るので、良い成績をとるのです。多くの場合、問題はその後です。本当は、どういう音楽をやっていくかという目標を立てて、その過程でコンクールを受けるべきなのです。ところが、コンクールに受かるという目標を立てて、達成した後に自分の音楽をやっていかなくてはならないわけですが、それがわからずにはたと立ち止まるというケースが非常に多い。日本の大学受験と同じですね。大学に入ることが目標になって、そこまでは頑張るのです。
この間、ヴァイオリニストの五嶋みどりさんとお会いした時に、二人でこんな話をしました。小学校の段階でベートーヴェンの『運命』やドヴォルザークの『新世界より』などを知っているのは日本人の子どもくらいで、日本の音楽教育はとてもレベルが高い。でも、これだけ早いうちに教育を受けているのに、その人たちがそのまま音楽を聴く層になっているのかというと、実はあまりなっていないと。継続しないのですね。
宮内:
確かにその通りですね。
久石:
宮内さんは、よくコンサートホールでお会いしますが、クラシックは昔からお好きなのですか。
宮内:
子どもの頃に合唱をやっていまして、その経験からだんだんクラシックを聴くようになったのです。
久石:
コンサートは年間どのくらい行っておられるのですか。
宮内:
割とよく行きます。今週は3回。少々行き過ぎですが(笑)、週に1回くらいは行きたいですね。
久石:
それはすごいです(笑)。
二時間のシンフォニー
宮内:
映画音楽というのは、映画がまだ完成していない時からお作りになるのですか。
久石:
同時進行です。まず脚本を読み、どういう世界観なのかを掴んで監督とお話をして、撮り終えたラッシュ(未編集の状態の映画のポジフィルム)をいくつか見せていただくのです。というのは、ドアを開けて入って椅子に座るという動作だけでも、それをさっと撮る方とじっくり撮る方と、監督によってテンポが違うのです。その監督のテンポや人柄、そして、その作品の中で監督が何をやりたいのかを考えながら曲を作っていきます。
映画は、最近は少し長くて二時間半ぐらいのものもありますが、基本的には二時間ですから、「二時間のシンフォニー」を書くつもりで作ります。音楽を入れるところも大切ですし、逆に音楽を抜くところも大切ですから、それを頭から最後までテーマがうまく構成されるように作るという方法をとっています。
宮内:
それを制作期限の間に考えながら作っていくわけですね。
久石:
締切はそんなに遠くないところにあります(笑)。曲を書きだすと永久に終わらないので、締切が命です。映画は公開日が決まっていますし、コンサートも公演日が決まっていますから、いついつまでに仕上げてくださいと言われて、そこまでになんとか漕ぎ着けます。締切日がないと、完成できませんね。モーツァルトもそうですし、作家はみんな同じだと思います。締切日もないのに書いたのは、シューベルトとプーランクくらいでしょうか。プーランクは日常作曲家のようなもので、気が向いたら書くというようなタイプで、シューベルトは、曲を書いては仲間うちのサロンで発表していたようです。
宮内:
モーツァルトにも締切日があったのですか。
久石:
発注を受けて書く、あるいは、後期はあまり恵まれていませんでしたから、自分で書いたものを売り込むとか、そういった状況だったようです。美術もみんなそうではないでしょうか。
ショスタコーヴィチやシェーンベルクも、映画音楽を手がけていますね。
宮内:
シェーンベルクの映画音楽もあるのですか。
久石:
はい。コンサートで聴いたことがありますが、こんなふうに書くのだなと思って、とても良かったです。視覚と音楽が結びついたオペラなど、いろいろなものはもともとあったわけですから、もう少し前の時代に映画という産業がきちんとあれば、ショパンやラフマニノフなどもみんな書いていたと思います。映画は二十世紀に入ってから発展したものなので、その時代の人は結構書いていますね。日本ですと、武満徹さん(1930~96)もたくさん書いていらっしゃいます。武満さんはメロディーメーカーだった気がします。現代音楽でも、間が東洋的といいますか、聴きやすくて、とても良い歌曲があります。
宮内:
映画音楽を作っていて、これはとても良くできたなというものを、クラシックの組曲にしたり、別の作品にされることもあるのですか。
久石:
これはいけるなと思うものは、後でオーケストラ曲に書き直すこともあります。
宮内:
作曲されるのは夜ですか。
久石:
僕は昼間に書きます。やはり、根が作曲家なので、一日の一番良い時間を作曲に使いたいのです。ですから、朝11時頃に起きて、起きてから2、3時間後が一番頭が冴えるので、昼の1時半~2時頃から始めて、夜の10時~0時頃までオフィスで作曲をして、その後自宅に帰って、明け方の4時、5時頃までクラシックの勉強をしています。それから寝ると、起きるのは必然的に11時ぐらいになりますね。そして、また昼の1時半とか2時頃から作曲をすると。今は書かなければならない作品がずいぶん溜まっています(笑)。
宮内:
作曲というのは孤独な作業ですね。
久石:
そうですね。クラシックの指揮をする場合、スコアは見た分だけ勉強になってはかどるのですが、作曲は良いアイデアが浮かばないとまったく何もできないです。
宮内:
ピアノで作曲されるのですか。
久石:
ピアノも使いますが、今は量をこなさなければならないので、コンピュータを使うほうが多いです。
宮内:
コンピュータでオーケストラの音が出るそうですね。その影響で、音楽家がずいぶん失業したという話を聞いたことがあります。
久石:
それはありますね。以前、シンセサイザーは2600万円ぐらいでした。僕もそうですが、年収よりもはるかに高いその楽器をなんとか手に入れて曲を作っていました。でも今は、そう高くない金額でコンピュータが手に入り、デジタルを使えばあまりお金をかけなくても音楽が作れますし、音質も悪くないのです。誰でも家で簡単にコンピュータで作ることができますから、そうした人たちの音楽がどんどん出てきて、エンターテインメントに関していうと、プロとアマのレベルの差がなくなってきています。CDが売れなくなったなど、今あるいろいろな問題も、そういった影響がとても大きいと思います。
「アーティメント」の実現
宮内:
クラシックファンは若い人が少なくて、年配の方が多いですね。
久石:
観客が高齢化しているのは事実ですが、僕のコンサートの場合は、宮崎駿監督作品の音楽をやらせていただいたこともあって、最近は20代、30代の方が多くなっています。オーケストラを聴くのは初めてだという方も結構来られるので、そういった方々がクラシックを聴くきっかけになればいいなと思います。
宮内:
クラシックファンの啓蒙という点で、久石さんは、新日本フィルと「ワールド・ドリーム・オーケストラ(W.D.O.)」を結成して指揮をされたり、素晴らしい活動をなさっていますね。
久石:
ありがとうございます。今年は、「W.D.O.」の8年ぶりの全国ツアーが決定しまして、8月に、東京(サントリーホール・すみだトリフォニーホール)・大阪・広島・名古屋・仙台の6カ所で公演をします。終戦七十周年となる今年は、「祈り」をテーマにしたオリジナルプログラム『The End of the World』 『祈りのうた』のほか、『風の谷のナウシカ』のオーケストラ組曲などの初披露曲を盛り込む予定です。「W.D.O.」は、クラシックだけではなく、ジャンルにとらわれず魅力ある作品を多くの方々に聴いていただこうという想いで、僕と新日本フィルが2004年に立ち上げたオーケストラで、こういった機会をいただけるのは大変ありがたいです。
僕は、「アーティメント」というものを広げていきたいと思っているのです。これは僕が考えた造語で、「アート」と「エンターテイメント」を組み合わせたものです。作曲家が世に生み出したアートを、神棚に上げないで日常化させてエンターテイメントにする「アーティメント」をオーケストラでも実現していきたいなと。
現代音楽でいうと、聴く機会もあまりないし、解釈が難しそうといったイメージが先行しがちですよね。でも、僕がやりたいのは、現代音楽ではなく、今の時代に必要な「現代の音楽」を演奏していきたいなと。クラシック音楽を古典芸能にして、そこに留まってしまうのではなく、過去から今に繋がって、ここから先の未来に行くためには「現代の音楽」を人々が聴くチャンスを作らなければなりません。ですから、僕が指揮をさせていただくクラシックのプログラムを作る時は、新しい曲を入れるようにしているのです。
宮内:
日本はクラシックとクラシック以外の音楽に画然たる区別がありますね。
久石:
ありがたいことに、僕は映画を含めエンターテイメントもやらせていただいていますので、クラシックとクラシック以外の音楽、それぞれの良いところとちょっと良くないかなというところの両面を客観的に観ることができます。ですから、その辺をうまく橋渡ししていけたらいいなと思っているのです。

日本人に合う『第九』
宮内:
日本では、年末になると『第九』を聴きに行きますね。あれは日本独特のもので、海外にはないですよね(笑)。
久石:
おっしゃる通りです。あれは何なのでしょうね(笑)。『第九』はコーラスの方が100人ぐらいいますから、それぞれの家族や親戚だけで400~500人が聴きにくるでしょう。ですから、団員の餅代を稼ぐのが目的で始まったとも、一説ではいわれています。年を越して新しい年を迎えるための餅代を稼ぐには12月にこれをやるしかないということで始まったと。
もし、その話が本当で始まったとしても、これだけ定着するというのは何なのだろうなと思っていたのですが、自分で初めて『第九』を指揮した時にわかったのは、日本人のメンタリティーに合うのかなと。日本人というのは、耐えに耐えて待ったあげくのカタルシス(心の中に溜まっていた感情が解放され、気持が浄化されること)のようなものに非常に弱いのではないでしょうか。例えば、赤穂浪士もそうで、ずっと我慢して我慢して、最後に討ち入りをして日本人はほっとしますね。『第九』も、聴きやすいかどうかは別として、一、ニ、三楽章はとても良くできていますが、そこまでを耐えに耐えて聴いた後に、四楽章で「フロイデ!」とコーラスが始まった瞬間すっとカタルシスがあって、おそらく、その快感が日本人に大変合っているのですね(笑)。
宮内:
なるほど、そうかもしれませんね。それを年末に味わいたいと(笑)。
久石:
僕の指揮の先生が、秋山和慶さんなのですね。僕は65歳になりますが、この年でもレッスンを受けているのです(笑)。
宮内:
秋山先生は今年、指揮者生活五十周年を迎えられましたね。先生は、今おいくつですか。
久石:
74歳です。つい2、3日前にもレッスンを受けたのですが、その秋山先生は『第九』を振って、すでに400回を超えているのです。それだけでもすごいのに、毎回新しい発見があるとおっしゃっていて、驚嘆しています。
宮内:
新日本フィルでも『第九』は毎年やりますが、やはりあれは餅代になるのでしょうね。日本の交響楽団はどこも経営的に大変ですから。
久石:
2000~2500人のキャパのコンサートホールに、独唱者が4人、コーラスを入れて100人ぐらいの人たちが出演して、採算ベースでは成立しませんから、海外ではめったに演奏されませんね。
文化に対する意識のあり方
宮内:
そうでしょうね。本来、文化というのはみんなでサポートしなければならないのですが、日本で寄付を集めるのは本当に苦労します。
久石:
アメリカですと、ボランティアとか社会還元というのは常識としてありますが、日本はあまりそれがないのでしょうか。
宮内:
一つは、税制の問題でお金を出しにくいというのがあります。もう一つは、意識の違いです。欧米の場合、バブリック(公共的)なことはパブリックがサポートするものだという考え方ですが、日本人は、パブリックなことは全部官があるものという考えがあるのでしょうね。また官のほうも、我々が全部やりますからということでこれまでやってきた。本当の意味の市民社会になっていないのだと思いますね。
久石:
日本は文化を育てるという意識が少ないような気がしますね。
宮内:
アメリカは、どんどん開拓して国を作りましたから、官がまったく追いつかないし、国民もそれがわかっていてあまり期待しなかったのでしょう、自分たちでやるしかないという精神が自然にできていったのかもしれませんね。一方、日本の場合は明治以来、国民は全部国が面倒をみましょうというふうになって、それが逆効果になっているのかなと思います。
久石:
僕もよく考えるのですが、明治になった瞬間、いったん文化が分断されましたよね。その時に、文化に対する意識のあり方が少し変わったのではないかという気がします。文化というのは誰かが育てていかないとなかな定着しませんから。
宮内:
そのうちに邦楽は消えていくかもしれませんね。邦楽の音階は西洋のドレミとは微妙に違いますよね。ああいった感覚を持つ人がどんどん減っていくのかなと思います。
久石:
例えば、中国と日本を照らし合わせてみると、中国から伝来した五弦琵琶は、中国にはもうないのですが、奈良の正倉院には世界で唯一現存する古代の五弦琵琶がおさめられていますね。中国では、私はこうする、私はこちらのほうが良いと、みんなどんどん自分の意見で手を加えて変化させてしまうのです。それはそれで、ある意味では良いのですが、古典的なものをそのまま伝統として残していくという考え方は少ない気がします。一方、日本の場合、雅楽のように、海を渡ってきたあちらのものが見事にそのまま残るのです。伝統的なものはそのまま残していくという考え方と、自分が良いと思ったら変えてしまうという考え方、この民族性の違いはあるのでしょうね。どちらもそれぞれ大切で、この辺がとても難しいなといつも思うのですが。
宮内:
能と歌舞伎もそうですね。武士の上流階級が能や狂言へ行き、歌舞伎は大衆が観る。その両方が残っていますね。
久石:
クラシックの歴史を見ると、王侯貴族や協会のために演奏されていた高貴なものだったのが、一般市民が楽しむ大衆音楽へと変わっていった。文化の構造というのは、大概そういうふうになっていますね。
日本は、歌舞伎がありながら能もありますし、極彩色のものもあれば、片やあらゆるものを削ぎ落したものもある。必ず両方あるというのは、日本人を考える時に結構良いヒントになります。
宮内:
日本人は贅沢ができるわけです。日本文化と西洋文化、どちらも素晴らしいものを楽しむことができるという点で、とても恵まれていますね。私は時々歌舞伎も観に行きますが、日本というのはいろいろなものがあって、なかなか忙しいですよ(笑)。
久石:
そうですね(笑)。最近鑑賞された中で良かったのは何でしたか。
宮内:
2月に行きました「山田和樹 マーラー・ツィクルス」(Bunkamuraオーチャードホール)は良かったですね。山田和樹さん指揮による日本フィルハーモニー交響楽団の『交響曲第三番ニ短調』は素晴らしかったです。
久石:
山田和樹さんは指揮がきれいでうまいです。僕は1月に『交響曲第一番ニ長調「巨人」』を聴きました。2月に第二番、第三番の公演がありましたが、行かれた方がとても良かったとおっしゃっていました。九回シリーズで、マーラーの番号付きの交響曲九曲を、一年に三曲ずつ番号順に、今年、来年、再来年と三年かけて全曲を演奏するという、コンセプトが明解ですよね。しかも、マーラーの交響曲の前に武満徹さんの作品を組み合わせるという発想は、僕らのような作曲家が考えるべきことで、指揮者があのようなプログラムを組まれるのは素晴らしいです。
僕が行った時の武満作品は『オリオンとプレアデス』でしたが、宮内さんが行かれた時は何を演奏されましたか。
宮内:
三つの映画音楽(訓練と急速の音楽『ホゼー・トレス』より/葬送の音楽『黒い雨』より/ワルツ『他人の顔』より)でした。かなり短い曲でしたが面白かったですよ。次回のチケットもよく売れているらしいですね。
久石:
やはり評判が良いのですね。
宮内:
久石さんは、指揮はお好きですか。
久石:
はい、好きです(笑)。ただ、分厚いスコアを勉強するのはしんどくて、もうそろそろ嫌だなと思ったり、もう少しやらなくてはなと思ったり、絶えず葛藤している状態です。
宮内:
自分の曲をなさる場合と、クラシックの場合とでは、全然感じが違いますか。
久石:
違いますね。クラシックを指揮する時に暗譜するくらい頭に入ってしまうと、その期間中はまったく作曲ができなくなります。絶えずクラシックの曲が頭の中に流れてしまって、その影響が何らかの形で曲作りに出てしまうのです。例えば、映画音楽を書いている最中に、一方でブラームスの曲の指揮をするという時に、ブラームスの弦の動かし方などが作っている曲の中に無意識に出たりします。「あっ、やってしまった!」というような(笑)。もちろんメロディーまで同じにはしませんが、弦の扱いなどはかなり影響を受けますね。
宮内:
一生懸命、勉強なさっているのでしょうね。
しかし、作曲家、指揮者、ピアニストと、いろいろな面でご活躍ですね。
久石:
ちょっと手を出しすぎているので、気をつけないといけないですね(笑)。
音楽が面白いなと思うのは、どんなに頑張ってもその先にまだ音楽はいますね。音楽というものの内容をもっともっと知りたいと思っていつも取り組んでいるのです。
「歌う」ことは音楽の原点
宮内:
この間いただいたCDを聴かせていただきました。女声合唱の曲はとても素晴らしいなと思いました。
久石:
高畑勲監督のアニメ映画『かぐや姫の物語』の合唱曲ですね。
宮内:
私は合唱が好きなので、ぜひ合唱曲をお願いしたいです(笑)。今頃の日本の合唱団は、新しい曲をやるのですが、教訓を賜るというような思想的な曲が多いのです。それよりもっと良い曲があるでしょうと思うのですが、きれいな曲はなかなか出てきません。
久石:
アマチュアの人が音楽に接する一番の近道は「歌う」ことですよね。歌うというのは音楽の原点かもしれません。ですから、合唱ももっと盛んにならないといけませんね。
宮内:
おっしゃる通りです。独唱は好きに歌えばいいのですが、合唱はきっちり合うまで相当時間をかけて練習しなければなりませんから、時間のある人にとっては良い趣味になります。ですから、年配の方の合唱団は、世の中にたくさんありますね。
久石:
例えば、三枝成彰さんが団長の「六男」(ろくだん)(六本木男声合唱団倶楽部)とか(笑)。「六男」からお誘いはきませんか。
宮内:
実は、最初の結成時に「宮内さんは昔合唱をやっていたのだから、入ってくださいよ」と三枝さんから声をかけられまして、一度はお受けしたのですよ。その後しばらくして、「六男」の制服を作るからということで、コシノヒロコさんの事務所から採寸の方がいらっしゃったのですが、家内にこの話をしましたら、仕事も忙しいのにと反対させまして、それでお断りしたのです(笑)。
久石:
そうでしたか(笑)。この間、1月にBunkamuraオーチャードホールで公演をされましたよね。
宮内:
アマチュアの合唱団ながら、なんと『ウェスト・サイズ・ストーリー』というオリジナルミュージカルの公演をしまして、私も出演しました。特別出演で、団員として出たわけではないのですよ。三枝さんと食事をご一緒した時に出演交渉されて、飲んだ勢いでイエスと言ってしまったようです(笑)。
久石:
そういえば、うちの奥さんと娘が観に行って、「宮内さんが出ていらしたわよ」と言っていました。皆さん、うまかったというか、なりきっていたと言っていましたよ(笑)。メンバーには各界の錚々たる方々が名を連ねておられますよね。
宮内:
約140人が所属していて、団員の平均年齢は62歳ぐらい、最長老は83歳です。そのうち半分は女性の役で女装して出ていたのですから、それは相当なものですよ。ミュージカルですから、歌だけでなく踊りもあるでしょう。最初は絶望的だと言われていたものを、一年間相当な時間をかけて特訓して、昨年の夏には合宿までしてなんとか観られるものにしたらしいです。観客の皆さんは何を観せられるのかと思っていたでしょうが、期待値よりも少し上だったのでしょう、極めて好評でした(笑)。
久石:
宮内さんは踊られなかったのですか。
宮内:
私はひょいと出て自分のところを少し歌っただけですよ。
久石:
何を歌われたのですか。
宮内:
『チムチムチェリー』です。三枝さんに、むやみに高い音で歌わされました(笑)。
久石:
それは惜しいものを見逃しました(笑)。
宮内:
あれをご覧になっていたら、今日の対談はお受けいただけなかったと思いますよ。あのレベルの人と音楽の話はできないと(笑)。
久石:
昔と違って、今は年齢は関係ないですね。映画界でいえば、山田洋次監督は83歳ですし、高畑勲監督も79歳ですが、とてもお元気で、しゃきっとしてお仕事されていますから、皆さんすごいなと思います。日本は少子化で人口が減っていますから、年配の方々にもどんどん活躍していただきたいですね。
宮内:
それでは今日はこの辺で。お忙しいところ、ありがとうございまいした。ぜひまたオリックス劇場でコンサートをお願いします。
久石:
こちらこそ、ぜひお願いいたします。今日は楽しい時間をありがとうございました。
(麻布十番・七尾にて)
(味の手帖 2015年6月号 より)
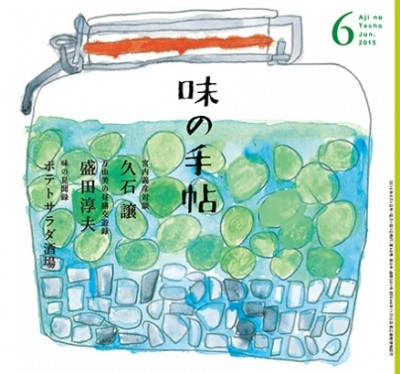
公式サイト:味の手帖
