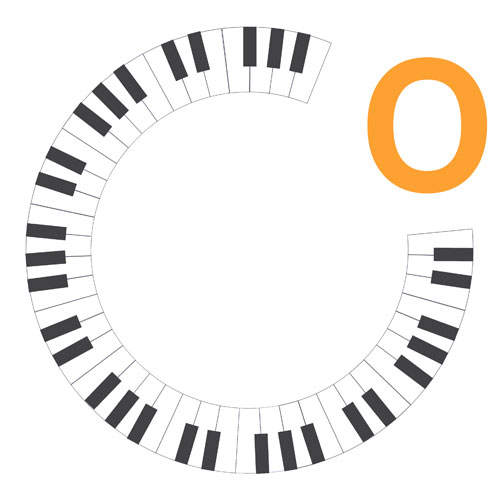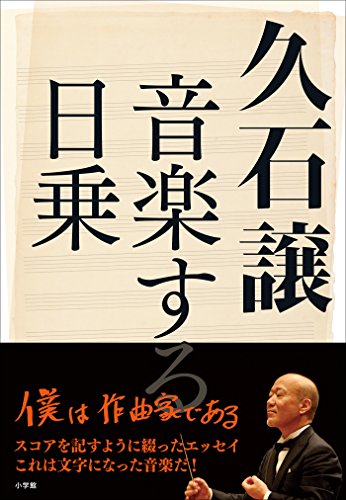Posted on 2017/11/15
ふらいすとーんです。
今回はちょっと音楽的にがんばって掘り深めていきたいと思います。ピアノの音のつくり方、響きのつくり方です。ピアノに限らずどの楽器にも言えることですが、たとえ同じ楽器でたとえ同じ楽曲を演奏したとしても、弾く人によってその音・響きは大きく異なります。なぜそうなるのか?それを言葉で説明することはとても難しい、説明する以前にどこまで本質的に理解しているかというステップもあり。
久石さんのピアノもまさに説明不可能な領域を多く含んでいて、たとえ自分が作曲したものでなかったとしても、久石さんがピアノを弾けば、やっぱりそこには久石譲独特の音や響きが広がります。この魔法はどうやってかけられるのか?
CDを聴くたびに、コンサートで体感するたびに、いつもこの不思議な魔法に魅了されます。そんなところに、とてもわかりやすいコラムを読むことができたので、それをもとに学びを深めていきたいと思います。クラシック音楽専門誌「モーストリー・クラシック MOSTLY CLASSIC 2017.2 Vol.237」に連載されている小山実稚恵さん(ピアニスト)によるエッセイです。
![]()
クラシック音楽専門誌「モーストリー・クラシック MOSTLY CLASSIC 2017.2 Vol.237」
ピアノと私 第33回 小山実稚恵
他の楽器・声との共演 ”合わせもの” ②
声楽、そして弦・管楽器で出来るのに、ピアノで出来ない2つの大きなことがあります。それはビブラートをかけること、そして音程を作ることです。この2つをピアノでも自由に使うことができるなら、ピアノの演奏ももっともっと自在になるのにと、声楽家や他の楽器の奏者を羨ましく思うことがあります。
ビブラートは音楽表現の大切な手段。声楽家が言葉に感情を込める時、ビブラートを上手く使うことができるかどうかで、感情表現はずいぶん違ってきます。限られた母音の中に、如何に自分の気持ちを託すことができるか。それが個性となり、音楽の表現手段となるのです。ビブラートのかけ方ひとつで、歌詞が胸に飛び込んできたり、感情が揺さぶられたり。
ビブラートの振れ幅、細かさ、長さやタイミング、音楽性がそこから見えてくると言っても過言ではありません。大胆で劇的なビブラートもあれば、品格の高いビブラートもある。時には、全くビブラートを使わないほうが良い場合だったあるわけですから。声楽家、弦楽器や管楽器の奏者が使うビブラートは、自分の気持ちを表現するための大きな手段なのです。
残念ながらピアノはビブラートをかけることができません。一度出してしまうと音の修正は効かない。無念に思いますが、その分、気持ちでビブラートをかけようと思います。「ここでビブラートをかけたい」と強く願って鍵盤をタッチするなら、ピアノから出るさまざまな倍音が、多少であってもビブラートをかけてくれる、そんな気がするのです。タッチは気持ちで作る、というのが私の持論ですが、「こんな音を出したい」とタッチに気持ちを込めるなら、指(というよりも身体)はそういう音を作ってくれると信じています。
そしてもうひとつ、音程について。現代のピアノは平均律で調律されています。1オクターブは12音で、音は鍵盤通り。ドの鍵盤を弾いたらド、レならレの音が鳴ります。ところが声楽や弦楽器は、自分自身で音を作るから、全ての音と音との間に音が存在する。音程は無限大なのです。音程を取る(作る)難しさがある代わりに、最高に美しい音程を作り出すこともできる。偉大な声楽家や演奏家たちの、何とも言えない音程感覚を耳にすると、私はいつも痺れてしまいます。平均律にはない響き、ハッとするような美しいハーモニーを感じた瞬間に鳥肌が立ち、そういう音程を何とかピアノでも作り出せないかと思うわけです。
一般的にはピアノの音程は決まっているものなのですが、私はピアノであっても、演奏次第で微妙な音程調整ができる気がしています。鍵盤にふれる時に、どの倍音を強く出すかを意識してタッチし、ペダルを踏むタイミングやペダリングの工夫をすれば、物理的にも音程は微妙に変化します。また和音を弾く場合でも、どの音に力点を置くのか、そして、それぞれをどのような音色バランスで鳴らすのか等、倍音の響き具合を上手に利用すれば、美しい音程を作り出すことができると思うのです。音程の決まっているピアノであっても、音程を作ろうと努力することは大切なことなのです。
合わせものをする時には、ソロとは違う判断力が必要となります。タッチを変え、相手の音程との関係を探る。バランスよく、相手と素敵な響きで音程を合わせることができると、最高の感覚に包まれます。共演者の方は、ピアノの音を聴きながら自分の音を判断して音程を作っているはずです。こちらもビブラートを感じ、音程を感じて、お互いを聴き合い、感じ合う。”合わせもの”をすると、音楽の初心に戻ることができるのです。
(「モーストリー・クラシック MOSTLY CLASSIC 2017.2 Vol.237」より)

![]()
いかがでしたか?
このお話を何回も何回もくり返し読むと、なにかわかったような見えてくるものがあるような気がしてきます。なるほど、ビブラートと音程に対するピアノの制約があったとして、それを克服し表現しようとするペダリングやタッチの強弱、そこから生まれる響きと倍音。
このあたりが掘り下げていくキーワードになりそうです。
お題1. ドビュッシーにみる和音と響き
ドビュッシーの和音はとても緻密に計算されています。左右両手の和音が乱れることなくピッタリ合うと、きれいな倍音が鳴るようにできています。ショパンやドビュッシーなどペダルや響きにこだわりの強かった作曲家は、楽譜に細かいペダル奏法の指示も残していたと言われます。ピアノという楽器の発達も影響しているのですが(バッハの時代はペダルがなかった、だから音を伸ばす効果をピアノは持っていなかった、トリルという隣り合うふたつの音を連打するのは、音を伸ばす代替とも言われています)、以降の印象派ロマン派においてもペダルを獲得したこと、イコール響きの可能性や多彩な表現力の追求へとつながっていきます。
ピアノ曲ではないですが、「牧神の午後への前奏曲」/ドビュッシー という管弦楽作品について。久石さんがTV音楽番組「読響シンフォニックライブ」(2012)で演奏したときのインタビューでもドビュッシーについて興味深く語られています。
「この曲は小節数にするとそんなに長いものではないんですが、この中に今後の音楽の歴史が発展するであろう要素が全部入っていますね。音楽というのは基本的に、メロディー・ハーモニー・リズムの3つです。メロディーというのはだんだん複雑になってきますから、新しく開発しようとしてもそんなに出来やしないです。そうすると「音色」になるわけです。この音色というのは現代音楽で不協和音をいっぱい重ねて特殊楽器を使ってもやっぱり和音、響きなんですね。そうするとそっちの方向に音楽が発達するであろう出だしがこの曲なんだと思います。20世紀の音楽の道を開いたのはこのドビュッシーの「牧神」なんじゃないかなと個人的にすごく思いますね。」
(読響シンフォニックライブ より)
![]()
お題2. 倍音
ここは通りたくないけれど通らないと進めない。久石さんの力を存分にお借りしたいと思います。
「まず音の問題。音とは空気の振動である。もう少し厳密にいうと、空気の圧力の平均(大気圧)より高い部分と低い部分ができて、それが波(音波)として伝わっていく現象である(『音のなんでも小事典』日本音響学会編)。まあ太鼓を叩くとそれが振動し、周りの空気も振動し、それが我々に伝わるということだ。」
「そして楽音を含め自然界の音はすべて倍音というものを持っている。それも限りが無いくらい。」
「では実験。今あなたはピアノの前に座っている。ちょうどおへその辺りにあるドの鍵盤を右手で音が出ないように静かに押さえる。そしてオクターヴ低いドの音を左手で強く弾いて、あるいは叩いてみよう。すると、あら不思議!強くて低いドの音が消えた後に弾いていない上のドの音がエコーのように聞こえるではないか!これは下のドの音に含まれている倍音と上のドの音が共鳴したために起こることである。つまり下のドの音には、第2倍音としてのオクターヴ上のドの音、第3倍音のオクターヴと5度上のソなど、限りなく色々な音が鳴っているのだ。もちろん上に行くほど音は小さくなり音程の幅も小さくなる。」
「実は人類はこの倍音を長い年月をかけながら発見していくのだ。例えば真ん中のドの音を男の人と女の人がユニゾンで歌うと、この段階でもうオクターヴ違うのであり、先ほどの第2倍音の音を歌ったことになる。これは整数比で1対2だ。そして500年くらいかけて(という人もいるが定かではない)人類は第3倍音であるソを発見する(整数比で2対3)。」
(講義はまだまだつづく…)
(Blog. 「クラシック プレミアム 39 ~ドビュッシー~」(CDマガジン) レビュー より抜粋)
*この音楽マガジンに2年間連載された久石譲エッセイは再構成・加筆され「音楽する日乗」(小学館)として書籍化されています。
TV音楽番組「題名のない音楽会 久石譲が語る歴史を彩る6人の作曲家たち」(2016年5,6月2週連続)に出演した際にも、実際にピアノに座って倍音の作り方を実演されていました。百聞は一見に如かず、とてもわかりやすかったですね。
![]()
お題3.ピアノと調律
現在久石さんが愛用しているピアノはスタインウェイ。初期の頃はベーゼンドルファーに比重が大きく、このふたつの銘器を楽曲ごとに使い分けていたほどです。
「レコーディングには約3年程かかりました。1986年秋、ロンドンのサームウェストスタジオで、Resphoina、Lady of Spring、Green Requiem、そしてInnocentの4曲をベーゼンドルファーのピアノで、残りの曲はその後1988年1月、東京でスタインウェイのピアノで録音することが出来ました。」
「ストリングスはロンドン・シンフォニーとロンドン・フィルのメンバーに協力してもらいました。ロンドンの──特に弦の音は、僕の求めている音に合うんです。録音はアビィ・ロード・スタジオ。あそこはね、ルーム・エコーが非常にいいんですよ。ピアノのパートは日本で録音しました。ピアノはベーゼンドルファー・インペリアル。低音部分にこだわってみたので」
ピアノの好みの響きについて、こんな興味深いインタビューもあります。
「僕のスタジオにあるスタインウェイがすごく気に入っています。今のスタインウェイってペダルがきつくて、カクンカクンと持ち上がるんですが、今僕が使っているモデルは、どちらかというと昔のタイプなので、ペダルのスプリングがすごく弱いんです。だから自然にペダル操作ができる。あと、音もきらびやかじゃなくて、ホワンとしています。僕がアルバムでピアノを弾くときは、ほとんどそのピアノですね。ただ、楽曲によってもっと派手な音が欲しいときは、別のスタインウェイを用意してもらうこともあります。あと、好きなのはアルバム『ETUDE』などで使ったオペラシティのスタインウェイ。あそこのピアノはすごくいいですよ。最近はベーゼンドルファーを全然弾かなくなっちゃいました。低音鍵盤があるモデルではその分響きが豊かだから、昔は好きだったんですけどね。理想のピアノは真ん中から低い音がベーゼンで、高い音がスタインウェイ(笑)。」
(Blog. 「キーボード・マガジン 2005年10月号 No.329」 久石譲 インタビュー内容 より抜粋)
ここまでこだわってます!
「やはり僕はピアノがメインなので、”これしかない”という響きのピアノに出会いたいといつも思ってます。「アシタカとサン」では生ピアノのマイキングに凝って録りました。マイクの位置をミリ単位で変えてみたり、蓋を外したりしていろいろ実験してみたんです。ピアノは譜面台を外すだけでも音は変わりますからね。調律師には”果物が腐る直前のような音”にしてくれと頼みました。ピッチがズレる直前というギリギリの感じですね。」
(Blog. 「キーボード・マガジン Keyboard magazine 1997年9月号」久石譲インタビュー内容 より抜粋)
ほかにもピアノにまつわるエピソードはたくさんあるのですが、お題「ピアノと調律」に振り返ると、楽器選びから、演奏や録音時のセッティングやマイキング、調律による音のニュアンス。自分の求める音に対して、自分のなかで響いている確固たる音に対して、実際の音や響きを近づけようとする過程を読みとることができますね。音程がつくれないピアノに対して、久石さんならではの音程のつくり方、生まれる響きや倍音の土台づくりとも言えるのかもしれません。奥が深い。
![]()
お題4. 久石譲ピアノは再現できるのか?
たとえば、久石さんの演奏CDを機械を介して数値化できたとします。音の強さも音の伸ばし方も音符ごとにすべてきれいな数値に表されたとします。じゃあこのとおり弾けば久石譲と同じピアノの響きになるかと言われると、近づくことはできるかもしれませんが、きっと同じにはならないですね。それは上に書いたピアノという楽器選びもあります。同じブランドであったとしてもグランドピアノは一台一台に性格があり個性としての響きがあります。
もっと大切なこと、それはやはり弾く人そのものが音として表れるからです。根本的にいえば、手の大きさ・手のかたち・指の曲げ伸ばし、このあたりが鍵盤のタッチに影響してきます。指使い・姿勢・椅子の高さ・体と鍵盤の距離感、このあたりが強弱や力のかけ方に影響してきます。それにペダルなどを加えると響き方や倍音に影響してきます。、、と勝手に思っています。
つまり弾く人に注目したとしても、いろいろな要素が絡み合って、素性・テクニック・感性の集合体として一音が生まれる。その人の音をつくっている。僕はこれを総称して”手クセ”と言っています。久石さんの指10本のそれぞれの指力の差、指使いのクセによるメロディの強弱、ドミソという和音を弾くにしても、3つの音のどの音にアクセントを置きたいかで、響き方や倍音の強弱にも影響してくる。一番強く叩かれた音が倍音効果も高いからです。
指使いのクセと書くとなんだか染みついてしまったもののように聞こえるかもしれません。それもあります。もうひとつ大切なのは、メロディーラインからみて模範的な指使いがあったとしても、ここの音でこんなニュアンスを出したいから、この音は小指が適している。といった、自分の指1本1本のタッチの特徴や長所を知っていいるからこその、”手クセ”です。
今回題材とさせてもらっているコラムにもわかりやすくありましたね。おさらいでもう一度。
「タッチは気持ちで作る、というのが私の持論ですが、「こんな音を出したい」とタッチに気持ちを込めるなら、指(というよりも身体)はそういう音を作ってくれると信じています。」
「一般的にはピアノの音程は決まっているものなのですが、私はピアノであっても、演奏次第で微妙な音程調整ができる気がしています。鍵盤にふれる時に、どの倍音を強く出すかを意識してタッチし、ペダルを踏むタイミングやペダリングの工夫をすれば、物理的にも音程は微妙に変化します。また和音を弾く場合でも、どの音に力点を置くのか、そして、それぞれをどのような音色バランスで鳴らすのか等、倍音の響き具合を上手に利用すれば、美しい音程を作り出すことができると思うのです。音程の決まっているピアノであっても、音程を作ろうと努力することは大切なことなのです。」
(「モーストリー・クラシック MOSTLY CLASSIC 2017.2 Vol.237」より)
深い、深すぎる。
自ら作曲した楽曲だからこそ、つくりたい音・つくりたい響きが明確にある。そしてCDやコンサートでも、ピアノをフィーチャーしたい楽曲は必ず久石譲自ら演奏する。伴奏やパートのひとつに徹している管弦楽作品や、指揮との両立で指揮台とピアノの行き来やタイミングが難しい場合などをのぞいて。
CDによる演奏も、コンサートによる演奏も、ニュアンスの違いこそあれ、楽曲を大きく包む響きはまさに久石譲ピアノそのものです。作曲当時の演奏と時を経て今の演奏、そのときどきの想いや年を重ねてきた年輪によっても紡ぎ出される音は変化しています。ライブであれば、観客の反応やその場の特別な雰囲気によって一期一会の音楽がうまれます。
「One Summer’s Day」の最後、たっぷりと響かせた低音の上に、高音がやさしくかけ上がっていきます。もともと久石さんは低音をたっぷり聴かせることが多い奏法だと思います。土台としてどっしり安定するからというのもあるでしょうし、低音の響きや倍音効果もあるのだと思います。作曲家としてピアノのみならずオーケストラ楽器やオーケストレーションを熟知した久石さんだからこその奏法であり響きです。
広がる水面に大きな音滴(低音)がどっぷり沈みこみ緩やかで厚みのある波形を生みだす。そこに小さな音滴(高音)が降りそそぎ細かい波形が幾重にも広がる。そして大小さまざまな波形がおり重なり交錯しまたぶつかり新しい波形をつくる。こうやってできた水面のゆらぎの瞬間こそが響きであり、倍音である。──というのは僕のイメージの世界です。
![]()
お題5. 管弦楽における響きと倍音 *宿題
ラヴェル「ボレロ」は、同じメロディーが楽器構成を変化させ、繰り返され徐々に盛り上がりクライマックスへむかう名曲です。この楽曲にも倍音効果を巧みに意図したオーケストレーションが施されているとなにかで読んだことがあります。
ベートーヴェン「交響曲第7番」第4楽章では、従来ベース伴奏のような役割の多かったコントラバスという低音弦楽器、ベース伴奏ではなく独立した旋律をあたえ、そのフレーズがくり返されることで独特なうねりとなって、緊張感や高揚感をもった響きとなっている。とこれもなにかで読んだ記憶です。
とすると、ミニマル・ミュージックというのは、フレーズを反復させる・フレーズをずらすわけですから…。同じ音がくり返される、同じ音の倍音もどんどん増幅されていくことになり…。和音じゃないにしても響きがかさなりハーモニーのようになり、倍音をうみやすい、それが独特の響きやうねりという覚醒効果をもたらし…。
これ、宿題です。いつかまた、いつかきっと。
![]()
今回は、だいぶん役不足なお題に足を踏み入れてしまいました。結局答えは導き出せたのか?と言われたらもちろんそんなことはありません。小さな、でもたしかなきっかけをひとつ学んだような気はしています。答えは見つからなくても学びや好奇心がもらたすもの、今まで聴こえていた音にも変化が起こっている、そう思える瞬間がきっとあります。
僕は最近思うんです。久石譲音楽についてリスト的な資料的なことであれば紙平面上である程度把握できたとして。それってあまり大切なことではない。情報を知るのと知識を深めることの差のように。ひとつを掘り深めること、たくさんに広がりを持たせること、深さ広さその両方が音楽の豊かさを二次元から三次元へ、平面から立体へとかたちづくられていくように。
久石譲とはこういう音楽だ、こういう傾向だ、と軽くかんたんに手で丸めてしまえるものではない。もっと知りたい、もっと感じとりたい、なにか新しい発見があるのかもしれない。このほうが楽しいですね♪
わかった気になることはそこで学びや感受性の限界をつくってしまうことになる。それはとてももったいないことです。そんな安易なものでは決してないのが久石譲音楽だとも思っています。わかった気になること、わからないとさじを投げること、好奇心の最大の敵だ!──と言い聞かせながら。久石さんの音楽の魅力を語りたい、でも言葉でうまく表現できない、このやきもき感が得も言われぬ醍醐味なのかもしれません(マニアックなファン心理 笑)。果てしないフィールド、これからも四方八方紆余曲折Overtoneしていこうと思います♪
それではまた。
reverb.
「久石譲 in パリ」(11/18再放送・NHK-BS)で聴くことのできる「One Summer’s Day」久石譲ピアノソロ極上の響き、今の久石さんだからこそ紡ぎだされる音。とびきりの魔法をぜひ♪
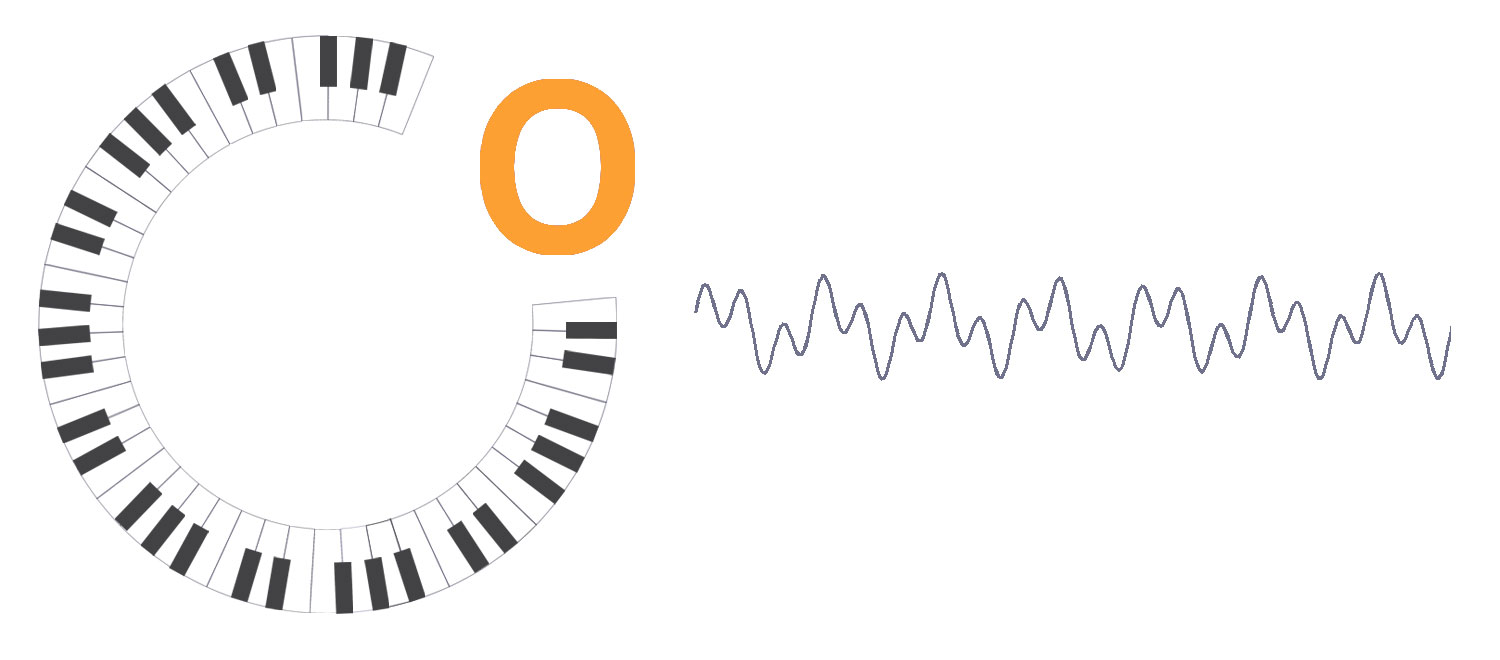
*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]
このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪