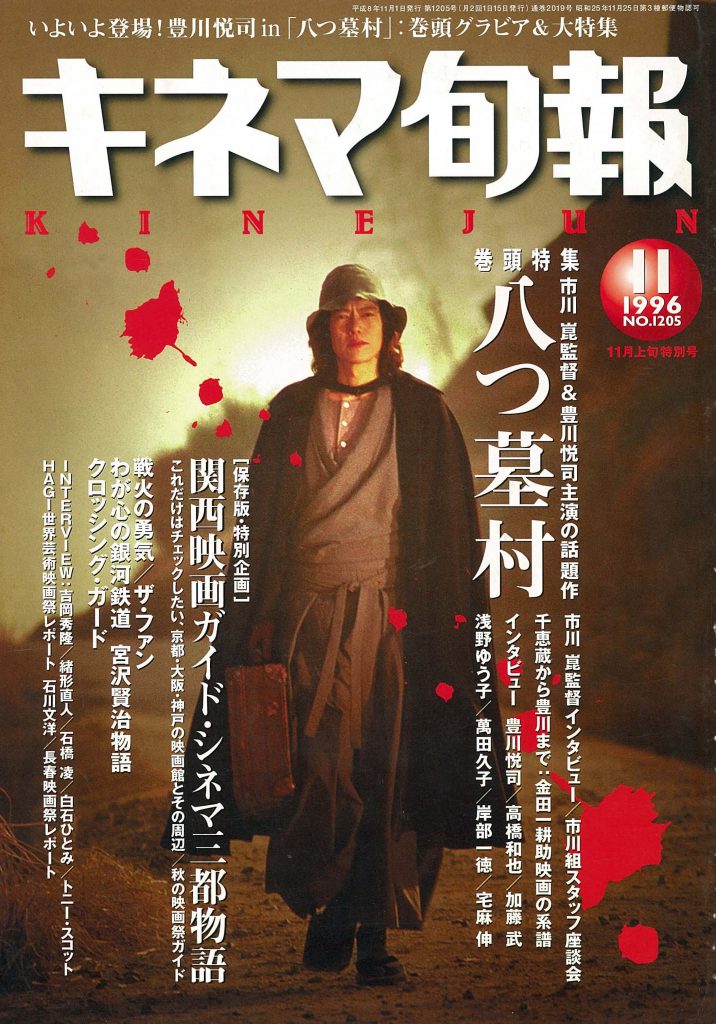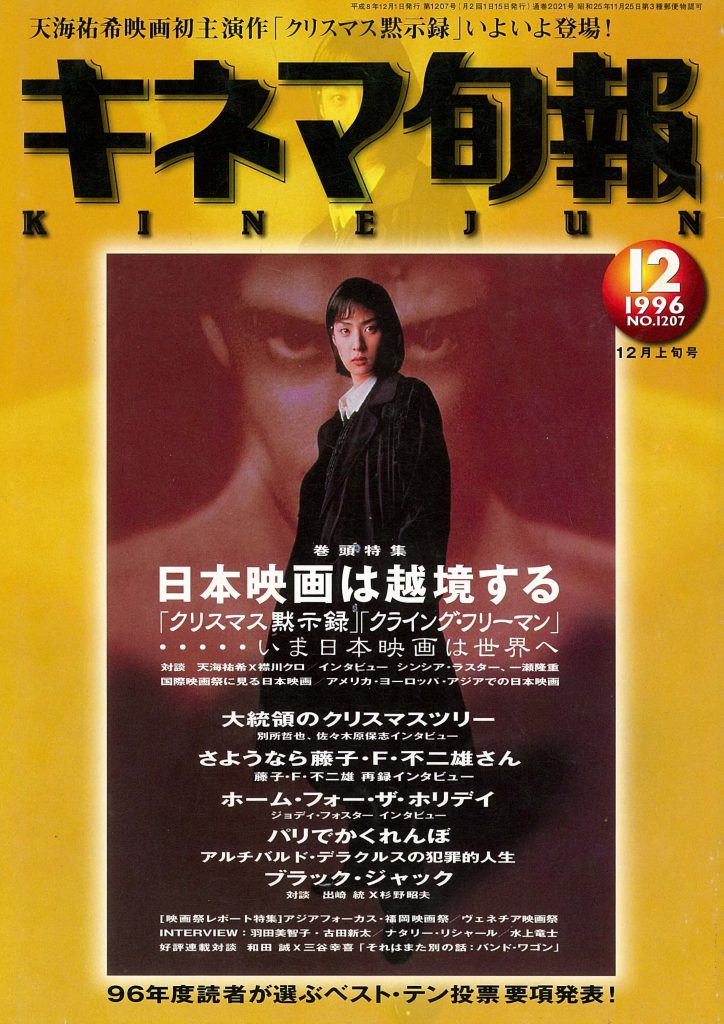Posted on 2018/03/03
映画情報誌「キネマ旬報 1996年11月上旬特別号 No.1205」に掲載された久石譲インタビューです。なお、本記事は本分に欠落部分があったため「キネマ旬報 1996年12月上旬号 No.1207」にて後半部を完全なものを再掲載したという経緯があります。ここでは両誌をまとめて完全版としてご紹介します。
ソロアルバム『PIANO STORIES II -The Wind of Life-』の楽器編成の話から、『もののけ姫 イメージアルバム』についてなど盛りだくさんな内容になっています。
SOUNDTRACK HOUSE INTERVIEW
取材:賀来卓人
常に第一線にいる危険な作曲家でありたい
久石譲が走っている。一昨年の大林宣彦監督作品『女ざかり』を最後に、スクリーンから遠ざかってファンをヤキモキさせた才人が、北野武監督の『キッズ・リターン』で復帰したのが今年の夏。それに前後してオリジナル・ソロアルバム『銀河鉄道の夜』、来年夏の大作『もののけ姫』のイメージアルバムを同時にリリース。さらにこの秋にはヒット・アルバムの続編『PIANO STORIES II -The Wind of Life-』の発売に加え、全国約20ヶ所をまわるコンサートを準備中と、猛烈な活動が展開しつつある。”僕らの時代の終焉”を叫んで迎えた充電期の真意は、そして、そこから得たものとは、何だったのか。新たな野心に燃えた彼に、じっくり聞いた。
この10年間で初めてだった台本のない生活
久石:
「映画でいうと『風の谷のナウシカ』以来ですか? ずっととぎれることなくやってきて、それは並行して自分のソロ活動を続けてきて、どこか自分の中で立ち止まらなければいけないという気持ちがあったんですね。もちろん、立ち止まったからといって結論が出るものではないし、出るわけがない。そういう意味では、忙しい仕事をして日常を埋めていく方がよほど楽なわけです。では立ち止まるとはどういうことかといえば、これはもう音楽家が音楽をやらなくなったら日常をどう過ごすか、ということ。一応、音楽プロデュースとかレコーディングとかの映画以外のものは続けていたことは続けていたんです。ただ、自分がそれまで重要にしていたソロアルバムや映画を1年間全くやらなかった。精神的な葛藤というかプレッシャーはあって、相当キツかったというのが本音です。」
-離れてみて初めて見えたと?
久石:
「ええ。映画はもう生活に染みついてるんですね。映画をやらないことがどんなに自分にとって苦しいことか分かりました。実はハリウッドからの話もあったんです。それは煮詰める必要もあったし、何よりも今までの日常のルーティーン・ワークから外れてみたいという、そんな気持ちが強かったんですね。」
-『キッズ・リターン』が映画復帰の直接のきっかけになったんですか?
久石:
「武さんの話と宮崎さんの『もののけ姫』がほぼ同時に来たんです。去年の秋ごろですか。それで「う~ん、これ以上わがままは言えないぞ」と(笑)。映画は独特の世界で、やり方を忘れちゃうというか、あまり休んではいけないので、テレビの仕事をやったりしてたんですが、現実にその二つが来た。作家はわがままなもので「こういうものは人に渡したくない」と思うじゃないですか(笑)。それもあって、そろそろかなと。」
-やはり久石さんが生来持ってらっしゃる映画好きの性がそうさせた節もあるのではないですか。
久石:
「ありますね。台本のない生活ってやったことなかったんですよ、この10年間。だからビックリしました。スヌーピーでいうとライナスの毛布みたいなもので、「ああ、自分が映画音楽をやってないって、こういう感じなんだな」と。新鮮を通り越して怖くもありましたね(笑)。逆に今は、映画をやっていられる喜びを客観的に考えられますね。そういう意味では『キッズ・リターン』はすごくいい映画だったし、宮崎さんの『もののけ姫』もホントにスゴイですから。だから前にも増してやりがいを感じています。」
-個人的には、久石さんのためにそういう舞台が何か自然と用意されていたような気さえします。
久石:
「もしそうだとしたら、うれしいですね。今年は不思議な縁で、1998年の長野のパラリンピックの総合プロデュースも引き受けることにもなって。もういろんなものがゴチャンと来て「これでしばらく走らなきゃ」と思ってるんです。」
今までで宮崎さんの存在が最も大きかった時期
久石:
「去年というのは、作曲家として音楽を作っていくという意味が見えなくなってた時期なんです。単にいいメロディを書けばよしというのは、もともと現代音楽をやっていたせいもあって、個人的にはそれでは納得できないわけです。じゃあ自分の原点では、自分が音楽を作り続けるというのは一体何なのだろうと、そこへハマっちゃってね。例えば宮崎さんはすごく自分の作品に対していいポジションをとってらっしゃる。今までの中で宮崎さんの存在が最も大きかった時期でしたよ。これまで僕は都会生活者の漂流感覚みたいな、いわゆる根無し草的な人間像に固執してソロアルバムを作ってきた。つまり世紀末感と一緒になったね。しかし、こんな時代や社会が堕ちてしまったら、そんな漂流感ではなく、もっと夢のあることをしなければいかんのだと、すごく思ったのが正直なところです。で、ニヒリズムに走らない夢のあることを考えていったら、宮崎さんがそれをずっとやってる。それがすごくショックだった。だから、宮崎さんが愛読されてきた堀田善衛さんとか司馬遼太郎さんの作品を読んだりしましたよ。もはや宮崎さんはアニメの作家というよりは時代のオピニオン・リーダーでしょう。それを宮崎さんは望んでいないんだけれど、ああやってキチンと日本を見つめて発言できる人が少なくなってきている。そんな人が自分のそばにいて仕事を一緒にできる。すごく幸せな反面、僕は僕の視点を持たなければいけない。それがやっと分かってきたということです。」
-この秋のコンサート・ラッシュにも何かつながってくるものがありますか。
久石:
「結局、自分の原点を確認するためのものですね。ハッキリ言って。11月のはアンサンブルでやるんですが、これが大事なんです。僕と弦楽四重奏、コントラバスにマリンバに木管という編成ですが、これは何をやりたいかというと、ミニマルをやるための編成なんです。もう僕の原点というか総決算で、大変な内容になりそうですね。オーケストラで、こちらもミニマルをやろうと思ってる。今までのメロディ主体の音楽もやりますが、同時に今の時代に対して自分にしかできないことを明確にしたコンサートをやろうと。《DA・MA・SHI・絵》なんて僕の曲は5拍子で、これをオーケストラでやるとなると、180何小節もあってリズムが命だし、とてもできるとは思えない。思えないけど、やめちゃうよりは悪い結果が出るだけでもハッキリする。だからやるべきなんですね。」
今後10年間をどう生きるべきか
-そういうコンサートへの意気込みは、例えば『PIANO STORIES II -The Wind of Life-』という新しいソロアルバムにも顕著ですね。一昨年の取材の折にはピアノ主体でシンプルに徹するという話でしたが、実際には弦に重きを置いた音楽になってます。
久石:
「難しかったんだよね。それまでガッチリとコンセプトを組んできたんだけれど、最後の最後で自分を信じた感覚的な決断をしたということです。あの弦の書き方って異常に特殊なんです。普通は例えば8・6・4・4・2とだんだん小さくなりますね。それを8・6・6・6・2と低域が大きい形にしてある。なおかつディヴィージで全部デパートに分けたりして……。チェロなんかまともにユニゾンしているところなんて一箇所もないですよ。ここまで徹底的に書いたことは今までない。結果として想像以上のものになってしまって、ピアノより弦が主張してる……ヤバイ……と(笑)。」
-それは基本を踏まえた上での久石さんのさらなる欲の表れでは?
久石:
「僕は戻りって性格的にできないし、オール・オア・ナッシングなんですね。時代って円運動しながら前へ進んでいると思うんですが、自分にとってのミニマルとか弦とか、原点に立ち返るというのは前に戻るのではなく、そのスタイルをとりながら全く新しいところへ行くことだと。そうでなければ意味がない。単なる懐古趣味に終わってしまうでしょう。ピアノというコンセプトでソロアルバムを作るということに変わりはなかったけれども、思い切りターボエンジンに切り替える必要があったわけです。」
-コンサートも含めて、単なるアイデンティティの確認の場ではないと。
久石:
「やっぱり、今後10年をどう生きるかということだよね。何かを引きずりながら次へと進んでいくようでは生き着けないんです。そのために断ち切らなければいけない部分と、まるで学生のように一から練習し直して自分を鍛え直さなければいけない部分がある。それをこの1、2年やってみて、考え方や技術を含めて、やっと可能性が見えるところへ行き着けたかなと。別の意味でスタート・ラインにつけたんじゃないかな。」
宮崎監督のためだけに作った『もののけ姫』
-『もののけ姫』のイメージアルバムを聴くと、そういった久石さんの燃え上がる魂が感じられますね。
久石:
「作るのに6ヶ月もかかっちゃったんだよね。予算は飛び出すわ、ソロアルバムより時間がかかるわで(笑)。でもあれって、たった一人に聴いてもらうために作ったんですよ。だからCDなんて出なくてよかったんだよね。」
-それは宮崎さんのことですか?
久石:
「そう。宮崎さんが聴くこと以外は何一つ考えなかった。宮崎さんが早く聴きたいって望んだ、じゃあ作りますっていう非常にシンプルな関係なわけ。それと半年という期間は、『ナウシカ』以来の良い面もあるけどそうじゃない部分も含めたいろんなものを洗い流す意味で必要な時間だったんだよね。ただ、僕が宮崎作品のために書いてきた音楽を聴いてきた人からすると、何か不満みたいね。」
-不満、ですか。
久石:
「愛とか感動とかロマンとか一切感じないでしょう。だから宮崎さんもすごく戸惑われたと思う。ただ、よく分かってる人達からは「ついに新しいところへ行ったね」と言われましたね。『もののけ姫』のイメージアルバムは僕にとってかなり大きかった。自分という人間をすごく考えましたね。」
-胡弓や琵琶といった楽器が絡んできてますが、この辺りの感触は?
久石:
「宮崎さんはああいう和楽器を使うことは望まれてなかったんです。和楽器って難しいの。例えば尺八がポーンと鳴ると、それだけで世界ができちゃうでしょ。そうするとそのクサ味みたいなものが嫌われる。大体作家の方は嫌いますね。武さんの作品にも実はエスニックなアフロヴォイスをいっぱい入れたんですよ。でもほぼカットしてしまいました。」
-わずかに残ったあのヴォイスがギリギリだったんですね。
久石:
「ギリギリだね。宮崎さんの場合の和楽器も一度途中で聴いてもらったら、「あの和楽器が……」と真っ先に言われましたね。いわゆるクサ味のある楽器以外は残しましたけどね、結局。」
日本人であること、チャレンジャーであること
-その『もののけ姫』のイメージアルバムのコメントにもありましたが、「日本的なものを目指す」というのが久石さんの新しさの一つだと思うのですが。
久石:
「そのスタンスというのは、今年の頭にパラリンピックのメインテーマを作ったときにすごく考えたのね。パラリンピックは日本では有名ではないですが、世界的には国際的なイベントなんです。そこでキチンと世界に向けて言える音楽って何だろうと考えたときに、すごくドメスティックなことが逆にインターナショナルになると。そこへやっと行き着けた。その辺りのやり方が今一番納得できるし、これをそのままキチンと出していかなければならない。日本の政治も映画もアイデンティティを失ってますよね。なかなか方向を定められないんです。何かほかに道があるのではと視点がいつも揺れてる。一つ方法を決めたらどんなに苦しくてもそれをやり通すこと。それが今の日本に必要なことじゃないかな。」
-その気迫が『もののけ姫』の迫力の正体ですね。
久石:
「途中でかなり悩んだんです。「間違ったかな」と思うこともあった。だけど「僕はこれで作る」と宣言したんだから変えなかったんです。その作家としての姿勢を貫けるかどうかで半年かかった気がしますね。」
-私事ですが、堀田さん、司馬さん、宮崎さんの鼎談集『時代の風音』に非常に啓蒙されたんです。
久石:
「僕も2、3回読みました。」
-あのお三方はインターナショナルであることが、あるいはその前に、日本人であることにこだわってらした。そういった部分から駆り立てられるものが、今の久石さんにも感じられますが。
久石:
「あの本を読んだ結果、日本の歴史の本をずいぶん読みました。そうして思ったのはやっぱり日本人ってカッコイイやと。平家の時代の人って海洋貿易の先駆者じゃないですか。信長だってポルトガルのとんでもない服を着て戦争やってたわけでしょ? ということは日本人って進んでたのね。おかしくなったのは明治以降でしょう。僕らが何か日本って嫌だなあと思ってることは、実はたかだかこの100年くらいの話かと気付くわけです。台湾へ自分のコンサートに行ったときに、ある記者に「あなたはヨーロッパ人になりたいのか」という挑発的な質問を受けたのね。でも、「僕は日本人は大好きだけど、日本という国は大嫌いだ」と答えたんです。それは宮崎さんの本に出てくるけれども、それが借りてきた言葉でなくて、自分の気持ちとしてキチンと言えるようになったらいいよね。」
-そういった意識の変化を含めて、久石譲はやはりニュー久石譲へと大きく変わったんでしょうか。
久石:
「変わってないと思うんですよ。いつも楽じゃない道を選んできた僕は一昨年も、そして今もまた楽じゃない道を歩こうとしている。そういう意味では変わってない。でもそれは言い方は変だけど、新しいことだと思うんです。つまり巨匠と呼ばれるよりは、常に第一線にいる危険な作曲家でありたい。いつも一等賞をとれる位置にあと5年はいるぞと。僕のことをベテランなんて書く奴がいると、バカヤローと思う。まだ何もやってないのに何がベテランですか。僕なんかこれから何を書くかわからないんですから、そういう意味ではいつでもチャレンジャーの側にしかいないと思うんです。」
インタビューではもう一本の新作『パラサイト・イヴ』への意気込みも熱く語られた。作家としての模索を経て、あくなき情熱と気力を得た名手は、果たしてこの世紀末にどのような夢と活力を銀幕にたたき込もうというのか。期待は募るばかりだ。今、久石譲が走り始めた。
(「キネマ旬報 1996年11月上旬特別号 No.1205」「キネマ旬報 1996年12月上旬号 No.1207」より)