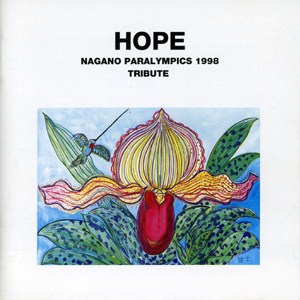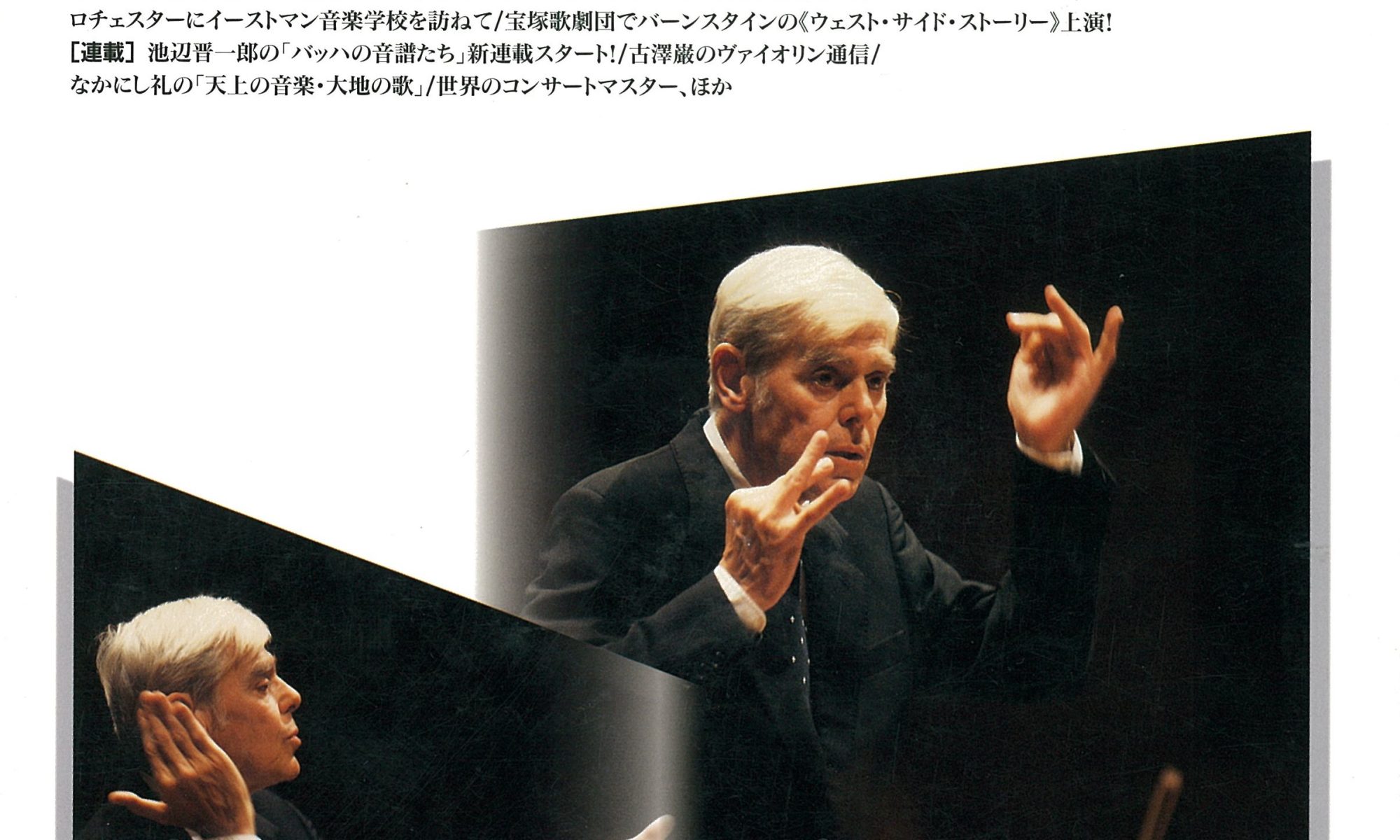Posted on 2021/09/03
クラシック音楽誌「音楽の友 1998年4月 特大号」に掲載された久石譲インタビュー内容です。連載コーナー「この一曲が好き!」に登場しました。久石譲が選んだのは「マーラー:アダージェット」、そして当時公開されたばかりの映画『HANA-BI』の話まで。
この一曲が好き!
第37回 マーラー/アダージェット 久石譲(作曲、演奏、プロデューサー)
各界の著名人に、自分の一番好きな「この一曲」について、熱い告白をしていただこうという好評連載!今月は、現代音楽の作曲家として出発しながらも、ポップス、映画音楽のフィールドで高い支持を得ている久石譲さんです。
昔、学生時代はマーラーはあまり好きではありませんでした。ところが、ロンドンに2年ほどいたときに『水の旅人』という映画のサウンド・トラックを、ロンドン・シンフォニー・オーケストラで、フルの3管編成でレコーディングしようとした(93年4月)んですが、いわゆる管弦楽法の本とかはみんな東京に置き忘れてきてしまった。そのとき手元にあったのは、マーラーの5番のスコアだけだったんですよ。そのスコアをずっと参考にして、ヴォイシング、音の配置を舐めるように見た。それで、マーラーの5番に親しんだのがとても記憶に残っています。
特にアダージェットは、『ヴェニスに死す』という映画のテーマ曲になりましたね。これだけ映画を見ているし、映画音楽をやってきたにもかかわらず、実は『ヴェニスに死す』は見ていなかったんですよ。で、去年、北野武さん監督の『HANA-BI』という映画がベネチア国際映画祭で金獅子賞を取りました。それでその前後であわてて『ヴェニスに死す』を見たんです。とても恥ずかしかったんですが、ヴィスコンティのあの映画に圧倒されて、同時にアダージェットという曲の持っている凄さに、もう一度心酔したんですね。
今回、長野パラリンピックのトリビュート・アルバム『HOPE』を作ったときに、ポップスの人から、ジャズ、クラシック、いろんなジャンルから参加していただきました。クラシックでは藤原真理さんと、オーボエの茂木大輔さん、カウンターテノールの米良美一さん、和太鼓の林英哲さんです。
で、どの曲をやろうかという段階で、チェロとピアノでは不可能かなと思いつつ、アダージェットをやってみたいという提案をしたんですね。真理さんと改めてもう1回聴いてみて、はたしてこれはチェロとピアノになるんだろうか、どうなるかわからないけれども、とにかく置き換えてみます、と編曲を始めたんです。
ところが、弦のスタティックな曲だから、音符がのびないとサマにならないんですね。弦は音を延ばすことは可能だけれども、ピアノはどうしても音が減衰していっちゃいますからね。原曲の響きや世界観をいかに変えずにピアノに置き換えるかで、ずいぶん苦しんだんですよ(笑)。そのレコーディングは相当うまくいって、これからきっとチェロの人のレパートリーに入るんじゃないか、それくらいのアレンジはできたし、自分も納得してるんです。もちろん原点にあったのは、あのアダージェットという楽曲の持っているすばらしさです。
これを書いた時のマーラーは、おそらく精神的に相当きつい状況だったと思うんです。メロディ自体はメイジャーの曲ですよね。でも、心底落ち込んだ、精神状態が最悪のときに、かえってメイジャーなメロディを書くというのは、何段階か人間として器が大きくなるというのでしょうか。辛いときに辛い曲、悲しい時に悲しい曲を書くほど、つまらないことはないんで(笑)。それをつき抜けた絶望の渕の明るさ、そして何かを求めるというようなところが、この曲にはある。ある意味でシューベルトの《白鳥の歌》に近いような、とても死を見据えた強さを、このアダージェットには強く感じるんです。第9番の第4楽章もすごくいいんですが、あれはオーケストラとしても劇的に構成され過ぎている。それに較べると第5番の第4楽章は、ハープと弦だけですよね。シンプルな中に本当に突き抜けた世界観をもっている。そういう意味でもこれはすばらしい。
もともとはブラームスがすごい好きなんです。ブラームス独特の、重たくなるくらいに低音を重ねてしまう、そういうもののほうが本当は好きなんですけれども、ただやっぱり、マーラーは指揮者としても一流でしたよね。ですから、小手先に走る、オケの効果に走る、構成上の弱さを持っているんだけれども、基本的には、オケの鳴らせ方、響かせ方に関しては、作曲部屋にこもって作っている人と、毎日オケの前でやっていた人との違いはある。マーラーの場合、譜面上では、えっ、これで大丈夫なのかな、というのが、実際音を出してみるととてもいいんですよね。この辺は、机上の作曲とまったく違うものがあって、ものすごく参考になります。
ブラームスは、彼の引き裂かれ方が好きなんです。体質はロマン派のくせに、頭の中は構成がっちりの古典派のベートーヴェンなんかに憧れきってる。そのバランスの悪さは、いつ聴いても面白い。第4シンフォニーなんて、音型、モティーフという捉え方でどう頑張っても、メロディにはロマンの香りがしちゃいますよね。ブラームスは一生そのことで闘って悩んでいた。そのことが露骨に見えるのが、ブラームスの一番破綻しているところでもあり、僕が好きなところでもあるんです。
人間の中にも、物事を論理的に考えたいというところと、ものすごいエモーショナルに動きたいというところと、みんな持っているじゃないですか。だからそれを大きなタームで捉えてみると、クラシックの流れ自体が、古典派、ロマン派、新古典派、十二音技法、現代音楽と、絶えず人間のなかの感覚的な部分と、理性的な統御の部分とが、交互に揺れ動いて来ていますよね。
僕の学生時代は、ミニマル・ミュージックが最先端の音楽だったんですね。1964年くらいですね。僕らはそれまではペンデレツキやクセナキスの流れで、不協和音を重ねるクラスターという書き方をしていました。あれは正直言ってだれもわからないんですよね。もっといえば、だれでも書ける。ものすごい大きなスコアに、「第1ヴァイオリン」という表記ではなく、ひとりひとりの奏者のヴァイオリン何10本に半音だ4分音だとぶつけていけばいいんだから。そんなに苦労はない。あれは机上の音楽でしかなかった。
実際に創造してるものとは違うはずなんです。それをちゃんとやりきれている作曲家は基本的にいないと思うんです。そういうものをただただ追求していくことが作曲の指南になり、あれだけの大量の音符の量を不確定理論とかでやっても、それが飽和状態まできてるような気がしていた。そこへ、ポンとミニマルを聴いたときに、あの形になってるというのは、僕にとって、ものすごく新鮮だったのね。ミニマルの方が自分たちのリアリティがあった。もちろん、スティーヴ・ライヒたちはいきなりそれを作ったんじゃなくて、いろんなムーヴメントのなかでやってきていますが。
当時、作曲家どうしが集まったときに話すことは、他人の批評ばかりだったわけです。あれはだめだ、これもだめだ、と。つまり、彼らの言い方というのは、他のものはすべてだめ。だから自分が正しい、という理論。赤ちょうちんで飲んで課長の悪口言ってるサラリーマンと何ら変わらない。だから体質的に現代音楽の連中のもっている雰囲気が大嫌いだったんです。音符で証明すればいいのに口で証明しているような奴らとやってもしようがない、と思った。そのときにふっと横を見ると、ロキシー・ミュージックから出てきたブライアン・イーノが、芸術論なんかぶたなくても、充分やっているという姿がすごくうらやましかったんですよ。それならこのまま現代音楽をやっているよりはポップスのフィールドに行った方が自分はいいと。
そこで「作品を書く」というのはやめたんです。そのかわり、ポップスのフィールドに行ってからはもっと自由にできるようになった。あっちは面白ければ正義ですから。もうひとつは売れなければ正義にもならないんだけど。それさえきちんとしていればやりたいことはやれる。だいたい我々の世代でも、才能のあった人物が、ほとんどみんなポップスとか、他のフィールドに流れちゃいましたよね。
映画音楽を作るときは、よほどのことがない限りは、台本を読んで、ラッシュを見て、それからどういう世界観にするかを通常決めて行きます。『HANA-BI』のときは、わりと早い時期から、北野さんから大体の内容は聞いていたし、「今回はアコースティックで行きたい」と言われていた。北野さんとやってきた映画音楽は、『HANA-BI』で4本目なんですけど、それまでのものは実はミニマル的な扱いが多かったんですよ。感情表現というよりは引いてしまって、最少単位の音型が繰り返されるような。具体的にいうと、シンセサイザーをだいたいメインにして作ってきた。『HANA-BI』の場合は、暴力的なシーンでも、弦とかできれいな音楽が流れているようなのはどうですか、という話があった。それがキーワードになりました。ただ、弦を使っていると、どうしてもメロディラインがついて、エモーショナルな部分に走りやすくなるんですよ。北野さんの世界では、おいおい泣いたりするような、感情表現の場って少ないんですよ。そういうところにエモーショナルな音楽を付けると、ものすごくダサくなったり、かえって北野ワールドを壊してしまうんじゃないか、というのが一番心配だったですね。弦を使ってやっていくときに僕が大事にしたのは「格調」。一、二歩引いて、主人公たちの精神状態を奏でるというところから全体を構成していった。通常僕らが映画音楽を書くときは、映画1本で25~30曲くらい、各シーンに入れていくんです。だけど今回は10曲だった。短くなったと喜んでいたんですが、1曲1曲が8分だったり6分だったり長いんですよ。だから、音楽全体の長さは結局45分くらい、いままでと全く変わっていなかった。その分、入れるときはドンと入れる。抜くときは思い切り抜く。映画としての音楽的なメリハリはつけられたという気がします。
以前見たスティーヴ・ライヒの《ザ・ケイヴ》はすごくショックでした。いつかこういうのにチャレンジしてみたいというのはありましたから。ただ、彼は現代音楽のフィールドだけど、僕は、ポップスのフィールドだから、斬新なもの、それでいてエンターテインメントとして楽しめるもの。そういう作品をこれから作っていきたいですね。変に芸術家というと、山の中に篭っていて自分の気にいった音符を書いていれば成り立つかもしれないけれど、僕がいまいる世界は、人様に見て聴いていただいて初めて成立する世界だから。自己満足では完結しないんですよ。それに対して出資してくれる人がいたり、レコード会社や映画会社がいる。そういう人たちは資本をしっかり回収し(笑)、なおかつ人々をただただ楽しませるだけでじゃなくて、もうひとつ上のランクのもの見せられるというのが理想ですから。それを一番やっているのはたぶん宮崎駿さんです。その人とずっと仕事させてもらったし。身の回りに北野さんとか凄い人が大勢いるもんで、いまでもいろいろ勉強させてもらっています。
(「音楽の友 1998年4月 特大号」より)