Posted on 2022/05/20
ふらいすとーんです。
怖いもの知らずに大胆に、大風呂敷を広げていくテーマのPart.1です。
今回題材にするのは『若い読者のための短編小説案内/村上春樹』(1997/2004)です。
村上春樹と久石譲 -共通序文-
現代を代表する、そして世界中にファンの多い、ひとりは小説家ひとりは作曲家。人気があるということ以外に、分野の異なるふたりに共通点はあるの? 村上春樹本を愛読し久石譲本(インタビュー記事含む)を愛読する生活をつづけるなか、ある時突然につながった線、一瞬にして結ばれてしまった線。もう僕のなかでは離すことができなくなってしまったふたつの糸。
結論です。村上春樹の長編小説と短編小説と翻訳本、それはそれぞれ、久石譲のオリジナル作品とエンターテインメント音楽とクラシック指揮に共通している。創作活動や作家性のフィールドとサイクル、とても巧みに循環させながら、螺旋上昇させながら、多くのものを取り込み巻き込み進化しつづけてきた人。
スタイルをもっている。スタイルとは、村上春樹でいえば文体、久石譲でいえば作風ということになるでしょうか。読めば聴けばそれとわかる強いオリジナリティをもっている。ここを磨いてきたものこそ《長編・短編・翻訳=オリジナル・エンタメ・指揮》というトライアングルです。三つを明確な立ち位置で発揮しながら、ときに前に後ろに膨らんだり縮んだり置き換えられたり、そして流入し混ざり合い、より一層の強い作品群をそ築き上げている。創作活動の自乗になっている。
そう思ったことをこれから進めていきます。
![]()
村上春樹バイオグラフィー的なものは飛ばします。とても音楽に造詣が深いことでも有名です。ジャンルはジャズ、クラシック、ロックと広く、自身がDJを務めるラジオ番組では愛聴曲たちをたっぷり紹介しています。音楽にまつわる文章も、ジャズ本・クラシック本・エッセイ・雑誌インタビュー・対談本と数多く発表しています。視点を本業の小説活動に移しても、ほんと音楽が体に染みついている人なんだなだとわかります。多くの小説にバラエティ富んだ楽曲が登場し、小説によって音楽がリバイバルヒット、はたまた廃盤CDが復刻される現象も起こるほどです。小説を発表すると、出版業界から音楽業界まで賑わせてしまう人。
今回題材にするのは『若い読者のための短編小説案内/村上春樹』(1997/2004)です。
この本は、実際のアメリカでの講義にも沿っているようですが、村上春樹が自作ではなく他作を取り上げ、短編小説を深く読んでみよう、こういう読み方もできると思う、とかなり深く突っ込んだ内容になっています。
取り上げたいのは、2004年文庫化のときに加えられた「僕にとっての短編小説──文庫本のための序文」からです。約20ページからなるこの項に、僕がテーマとして紐解きたいことがたっぷり語られているのですが、すべては紹介できない。でもぶつ切りな切り貼りはしたくない。自分が読んだあとなら、要約するようにチョイスチョイスな文章抜き出しでもいいのですが、初めて見る人には文脈わかりにくいですよね。段落ごとにほぼ抜き出すかたちでいくつかご紹介します。そして、すぐあとに ⇒⇒ で僕のコメントをはさむ形にしています。
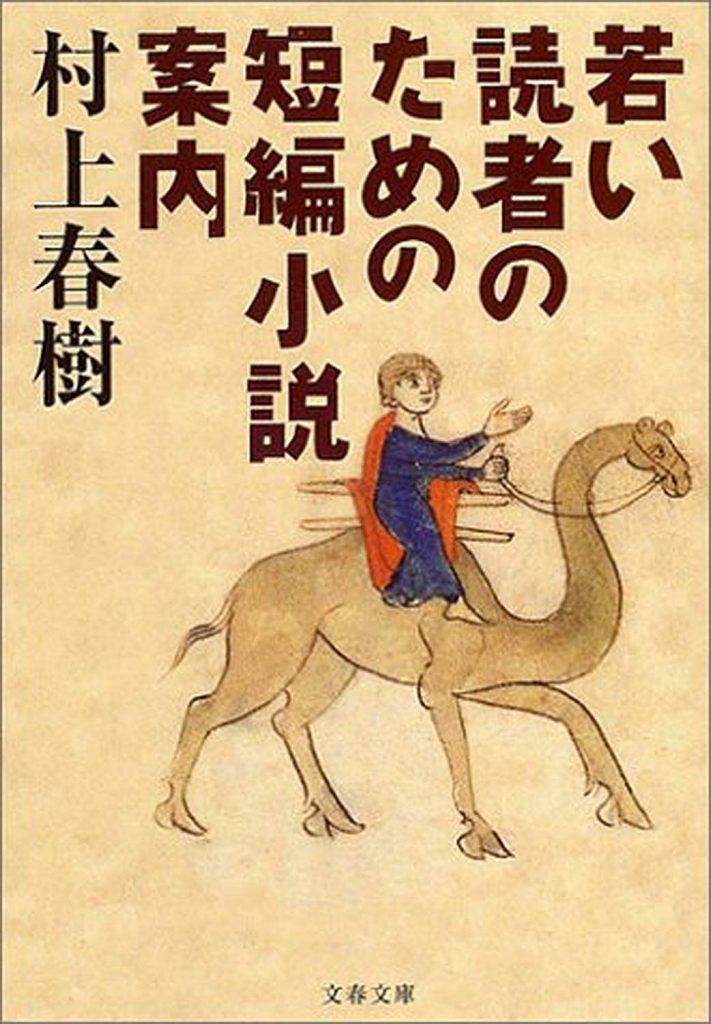
“僕は自分自身を、基本的には長編小説作家であるとみなしています。僕は数年に一冊のペースで長編小説を書き(更に細かく分ければ、そこには長めの長編と、短めの長編の二種類があるわけですが)、ときどきまとめて短編小説を書き、小説を書いていないときにはエッセイや雑文や旅行記のようなものを書き、その合間に英語の小説の翻訳をやっています。考えてみれば(あらためてそういう風に考えることはあまりないのですが)守備範囲は広い方かもしれません。ジャンルによって文章の書き方も少しずつ変わってきますし、長編・短編・エッセイ・翻訳、どの仕事をするのもそれぞれに好きです。要するに早い話、どんなかたちでもいいから、文章を書くという作業に携わっていることが、僕は好きなのです。またそのときどきの気持ちに応じて、いろんなスタイルで文章を書き分けられるというのはとても楽しいことだし、精神バランスの見地から見ても、有益なことだと思っています。それは身体のいろんな部分の筋肉をまんべんなく動かすのに似ています。”
~(中略)~
⇒⇒
久石譲もオリジナル作品(そこにも大きめの作品と小さめの作品の二種類があります)を発表しつづけていますね。映画・TV・CMなどのエンターテインメントのお仕事も話題が途切れることはありません。コンサートも久石譲プログラムからクラシック演奏会まで多種多彩にしてすべて久石譲指揮です。あらためて言うまでもなく守備範囲は広いです。エンターテインメントな大衆性とアーティスティックな芸術性のバランスをとりながら。そして、すべての仕事が長編小説の肥やしとなり結実しているように、すべての仕事がオリジナル作品(たとえば交響曲)の肥やしになり結実しているように思います。
![]()
もちろん読者の中には、「いや、村上さんの書くものの中では短編小説がいちばん好きです」という人もいらっしゃいますし、「村上の小説は苦手だけど、エッセイは好きだ」という人もおられます。それはそれでもちろんありがたいのですが(お前の書いたものはどれもみんな同じくらい嫌いだ、と言われるよりはずっといいですよね)、でも僕自身としては、小説家になって以来二十五年間、長編小説という形体にもっとも強く心を惹かれ続けてきたし、また実際にもっとも多くの労力と時間を長編小説の執筆に投入してきたのだ、ということになります。生意気な言い方かもしれませんが、僕より上手な優れた長編小説を書く作家はもちろんいるけれど、僕が書くような長編小説を書ける作家はほかに一人もいないはずだ、という自負のようなものもあります。自分の書く長編小説に、ささやかではあるけれど自分だけのシグネチャー(署名)を残すことができるのだ、という自負です。もちろん僕が書いた長編小説は好まれたり好まれなかったりするし、評価されたりされなかったりもします。しかしそれとはべつに、長編小説というのは、作家としての僕が一生を通して真剣に追求しなくてはならない分野であると、僕自身は感じているわけです。”
~(中略)~
⇒⇒
「僕が書くようなオリジナル作品を書ける作曲家はほかに一人もいないはずだ」、ご本人がそう思っているかどうかはわかりませんが、ミニマルな要素と日本的な要素をしっかりと作品に刻みこむことで、久石譲だけのシグネチャーをたしかに残しています。大いに自負していただいてしかりです。独自性をもった交響作品・現代作品を系譜として発表しつづけている稀有な人です。
![]()
“それに比べると、短編小説を書くことは多くの場合、純粋な個人的楽しみに近いものです。とくに準備もいらないし、覚悟みたいな大げさなものも不要です。アイデアひとつ、風景ひとつ、あるいは台詞の一行が頭に浮かぶと、それを抱えて机の前に座り、物語を書き始めます。プロットも構成も、とくに必要ありません。頭の中にあるひとつの断片からどんな物語が立ち上がっていくのか、その成り行きを眺め、それをそのまま文章に移し替えていけばいいわけです。もちろん「短編小説なんて簡単に書けるんだ」と言っているわけではありません。ひとつの物語を立ち上げていって、それを完成させるというのは、なんといっても無から有を創り出す作業なわけですから、片手間にひょいひょいとできることではありません。ときには呼吸することを忘れてしまうくらいの──実際に忘れることはたぶんないでしょうが──鋭い集中力が、そしてもちろん豊かなイマジネーションが、要求される作業ではあります。”
~(中略)~
⇒⇒
宮崎駿監督から渡されたメモや絵をきっかけに。原作小説の印象やイメージをきっかけに。あの楽器を使ってみようというアイデアをきっかけに。ひとつのメロディをきっかけに。音楽を立ち上げていく過程にもいろいろありそうです。
![]()
“「その女から電話がかかってきたとき、僕は台所に立ってスパゲティーをゆでているところだった」という一行から短編小説を書き始めたことがあります。それ以外に僕の中にはとくに何のアイデアもありませんでした。ただの一行の文章です。一人でお昼にスパゲティーを茹でているときに電話のベルが鳴る、というイメージが頭にふと浮かびます。それは誰からの電話だろう? 彼は茹でかけのスパゲティーをどうするのだろう? そういう疑問が生まれます。そういう疑問を招集して、ひとつの物語に換えていくわけです。それは『ねじまき鳥と火曜日の女たち』という短編小説になりました。400字詰め原稿用紙にして八十枚くらいの作品です。
その短編を書き上げて、雑誌に発表して、単行本に収録して、五年ばかり経過してから、僕はその短編『ねじまき鳥と火曜日の女たち』をもとにして長編小説を書き始めました。時間が経過するにつれ、その物語には、短編小説という容れ物には収まりきらない大きな可能性が潜んでいるのではないかと、強く感じるようになったからです。その可能性の重みを、僕はしっかりと両手に感じとることができました。そこには未知の大地に足を踏み入れていくときのような、わくわくした特別な感覚がありました。二年の歳月ののちに、それは『ねじまき鳥クロニクル』という作品として結実しました。二千枚近い枚数の、かなり長大なフィクションです。考えてみれば、「その女から電話がかかってきたとき、僕は台所に立ってスパゲティーをゆでているところだった」という一見なんでもない一行から、思いもかけずそのような大柄な作品が生まれることになったのです。
そのように僕は短編小説を、ひとつの実験の場として、あるいは可能性を試すための場として、使うことがあります。そこでいろんな新しいことや、ふと思いついたことを試してみて、それがうまく機能するか、発展性があるかどうかをたしかめてみるわけです。もし発展性があるとしたら、それは次の長編小説の出だしとして取り込まれたり、何らかのかたちで部分的に用いられたりすることになります。短編小説にはそういう役目がひとつあります。長編小説の始動モーターとしての役目を果たすわけです。僕はほかにも同じように、短編小説をもとにしていくつかの長編小説を書きました。『ノルウェイの森』は『螢』という短編小説を発展させて書きました。『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』という長編小説は『街と、その不確かな壁』という百五十枚程度の作品が下敷きになっています。
もちろん短編小説に与えられているのは、そういう役目だけではありません。僕は長編小説にはうまく収まりきらない題材を、短編小説に使うことがよくあります。ある情景のスケッチ、断片的なエピソード、消え残っている記憶、ふとした会話、ある種の仮説のようなもの(たとえば激しい雨が二十日間も降り続けたら、僕らの生活はどんなことになるだろう?)、言葉遊び、そういうものを思いつくままに短い物語のかたちにしてみます。たとえば『トニー滝谷』という短編小説は、マウイ島の古着屋で買ったTシャツの胸に「トニー・タキタニ」という名前がプリントしてあったことから生まれました。「トニー・タキタニっていったいどんな人なのだろう?」と僕は想像し、それでこの作品を書き始めたわけです。「トニー・タキタニ」という言葉の響きひとつから、物語を作っていったわけです。”
~(中略)~
⇒⇒
少し長い引用でしたけれど、一番伝わりやすいと思い選びました。短編小説が長編小説へと膨らんでいくさま。短編小説をエンタメ音楽に、長編小説をオリジナル作品に、置き換えてみてもう一度読んでみてください。──おもしろいですね。ちょっと遊んで枚を秒にしてみます。80枚の短編が2000枚の長編になる=1分20秒(80秒)の小曲が約33分(2000秒)の長大な作品になったりするわけですね。おもしろいですね。
![]()
“そのような様々な試みがあって、中にはうまくいったと思えるものもありますし、残念ながらあまりうまくいかなかったものもあります。しかし短編小説というのは基本的にそれでいいのではないかと、僕は考えます。極端な言い方をすれば、「失敗してこその短編小説」なのです。うまくいくものもあり、それほどうまくいかないものもあって、それでこそ短編小説の世界が成り立っているのだと僕は思います。何から何まで傑作を書くことなんて、どんな人間にもできません。波があって、それが上がったり下がったりします。そして波が高くなったときに、そのタイミングをつかまえて、いちばん上まで行くこと、おそらくそれが短編小説を書く優れた作家に求められることです。僕は短編小説を書くときには、いつもそんな風に考えています。
逆の言い方をすれば、作家は短編小説を書くときには、失敗を恐れてはならないということです。たとえ失敗をしても、その結果作品の完成度がそれほど高くなくなったとしても、それが前向きの失敗であれば、その失敗はおそらく先につながっていきます。次に高い波がやって来たときに、そのてっぺんにうまく乗ることができるように助けてくれるかもしれない。そんなこと長編小説ではなかなかできません。一年以上かけて行われる大事な作業ですから、「まあ今回これは失敗でもいいや」というわけにはいかないのです。その点短編小説だと、危険を恐れずに、ある程度まで自由に好きなことができます。それが短編小説のいちばんの利点であると思います。たとえば僕は長いあいだ三人称で長編小説を書くことがうまくできなかったのですが、短編小説で三人称を書く訓練をして、それに身体を馴らしていって、その結果かなり自然に違和感なく三人称を使って長いものが書けるようになりました。”
~(中略)~
⇒⇒
”短編小説は実験の場、可能性を試す場”と語っています。アイデアをかたちにしてみる、新しいことに挑戦してみる機会とも言えます。なるほど、「ダンロップCM音楽」からオリジナル作品へと発展させた「Variation 57 for Two Pianos and Chamber Orchestra」なんかもあります。また久石譲が追求している単旋律(Single Track Music)手法は、小さな曲や小さな編成から試されながら、手応えと磨きあげをもって交響作品でしっかりとのこされています。
![]()
“このようにして短編小説をいくつかまとめて書くと、僕の場合、必ずその次に長編小説が書きたくなる時期がやってきます。短編小説を書いているのは楽しいのですが、だんだんそれだけでは足りなくなってくるのです。もっともっと大きな物語に取り組んでみたいという思いが高まってきます。そういうエネルギーが、雨水がちょっとずつ桶に溜まるみたいに、身体に次第に蓄積されてくるわけです。そのエネルギーの溜まり具合から、「この感じだと、あと三ヶ月くらいで長編小説を書き始めることになるだろうな」というようなことも予測できます。それがどれくらいの厚さの本になるかということだって、だいたい見当がつきます。
そのように、短編小説は、長編小説を書くためのスプリングボードのような役割も果たしています。もし短編小説を書くことがなかったら、僕がこれまで書いてきた長編小説は、今あるものとはずいぶんかたちの違うものになっていたのではないかと思います。短編小説である種のものごとをうまく書ききってしまえるからこそ、僕はそのあとまっすぐ長編小説に飛び込んでいくことができるわけです。あるいはまた短編小説で書ききれないものごとが見えてくるからこそ、長編小説の世界に挑みたいという気持ちも高まってくるわけです。そういう意味あいにおいても、短編小説は僕にとってきわめて大事なものであるし、それはまたなにがあろうと、うまく自然に書かれなくてはならないわけです。”
~(中略)~
⇒⇒
「エンターテインメントの仕事をするなかでの葛藤やフラストレーションが、自分の作品をつくることへと向かわせてきた」久石譲スタンダード語録です。作家同士のシンパシーを感じてしまう一面でした。短編と長編、エンタメ音楽とオリジナル作品。
![]()
“そのように短編小説には、時間をおいて手を入れる、書き直すという喜びもあります。長編小説を書き直すとなると、ものすごくエネルギーと手間が必要になりますし、一部を書き直すと全体のバランスが違ってくることもあるので、まずやりませんが、短編小説の場合は比較的簡単に書き直すことができます。もちろんすべての短編小説にそういうことが可能だというわけではありません。もはや書き直せないというものもありますし、書き直す必要を認めないというもの(完璧な出来だということではなく、あくまでその必要がないということです)もあります。でも「これは書き直した方が明らかによくなるな」というものもやはりあるわけです。短編の書き直しは、主として技術的な見地から行われます。しかし全体から見れば、「これは書き直したい」と思わせる作品はそれほど数多くありません。「この作品は、技術的にはいくらか不備があるかもしれないが、下手にいじらず、このままそっと置いておいた方がいいだろう」と感じるものの方がずっと多いのです。そういう意味では、短編小説というのはきわめてデリケートな成り立ちなのです。一筆加えるだけで、過去の作品が生き返ったり、あるいは逆に勢いを失ったりもします。何がなんでも技術的にうまく書き直せばいいというものではありません。”
~(中略)~
⇒⇒
ふむ深い。「これは書き直したほうがよくなる、これは書き直したい」そう思って映画のために書いた曲を再構成してオリジナルアルバムへ収録された曲もたくさんあります。
ここには出てきていない話題ですけれど、村上春樹さんは雑誌掲載用と書籍収録用と長さの違う2つの短編を用意することもあるそうです。これは雑誌に載せるときの文字数の問題で、削ったものと削っていないものです。のちに書籍化するときは完全版のほうを収録する。どちらも成立するからそれでいいとも言っています。久石譲に置き換えると、文字数の制約は台詞のかぶる音数の制約だったりカット割りの分数の制約だったりでしょうか。そうしたことから解放される音楽作品の再構成。いろいろなケースがありそうです。
![]()
“このように、様々な意味合いにおいて、短編小説は作家である僕にとって重要な学習の場であり、探求の場でもあり続けてきました。それは画家にとってのデッサンのようなものだと言えるかもしれません。正確で巧みなデッサンをする力がなければ、大きな油絵を描ききることはできません。僕は短編小説を書くことによって、またほかの作家の優れた短編小説を読むことによって、あるいは翻訳することによって、作家としての勉強をしてきました。”
~(中略)~
⇒⇒
村上さんは毎日必ず机に向かってなにかしら書くというサイクルを守っているそうです。久石さんも毎日なにかしら音楽をつくる(音楽的断片であっても)サイクルを守っているといいます。お互いに何十年ものあいだこの習慣を維持している。そこには強い基礎体力と精神力の自己管理や鍛錬も必要になってくるわけで、本当にすごいことです。日々のデッサンが、培われたデッザン力こそが、ついには大きな作品を誕生させているのだろうと、簡単に言ってしまうのも恐れ多いほどひしひしと感じます。
(以上、”村上春樹文章”は「僕にとっての短編小説」項より 引用)
![]()
少し追加します。
同書からは離れて、同旨なことを語っているものです。いろいろな方向から眺めてみると、いろいろな言い回しから触れてみると、吸収しやすくなったりすることあるなと僕なんかは思います。
“『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』という長編小説を書きあげたのは一九八五年のことだ。この小説のもとになったのは、その五年ばかり前に書いた「街と、その不確かな壁」という中編小説である。この「街と、その不確かな壁」という作品はある文芸誌に掲載されたのだが、僕としては出来がもうひとつ気に入らなくて(簡単に言ってしまえば、その時点では僕はまだ、この話をしっかり書き切るだけの技量を持ち合わせていなかったということになる)、単行本のかたちにすることなく、そのまま手つかずで放置されていた。いつか適当な時期が来たらしっかり書き直そうという心づもりでいたのだ。それは僕にとってとても大きな意味を持つ物語であり、その小説もまた僕によってうまく書き直されることを強く求めていた。
でもいったいどうやって書き直せばいいのか、そのとっかかりがなかなかつかめなかった。この小説にとって必要なのは小手先だけの書き直しではなく、大きな転換であり、その大きな転換をもたらしてくれるまったく新しいアイデアだった。そして四年後のある日、何かのきっかけで(それがどんなきっかけだったのかは今となっては思い出せないのだけれど)僕の頭にひとつのアイデアが浮かんだ。「そうだ、これだ!」と僕は思って、さっそく机に向かい、長い書き直し作業に取りかかった。”
(『村上春樹 雑文集/村上春樹』「自分の物語と、自分の文体」項より 一部抜粋)
⇒⇒
「書き直し」という点では「MKWAJU 1891-2009」も浮かびます。曲名にあるとおり、発表時には技術が足りなくてうまく実現できていなかったものを時を経て直しています。もうひとつ思い浮かべたいのは、「交響曲第1番 第1楽章」として未完のまま発表したきりになっていたものを5年後に「THE EAST LAND SYMPHONY」として完成させた事例です。しかも村上春樹さんの「街と、その不確かな壁」という中編作品は文芸誌で一度発表されて以後どの著作にも収録されることなくお蔵入りです。久石譲さんの「交響曲第1番 第1楽章」も演奏会で一度披露されたきり、直して引き継がれた「1. The East Land」はあるものの、その原型を聴けることはもうありません。
“ある種の短編は、書き上げられて発表されたあとに、僕の心の中に不思議な残り方をする。それは種子のように僕という土壌に落ちつき、地中に根をのばし、やがて小さな芽を出していく。それは長編小説に発展されることを求め、待っているのだ。僕はそういう気配を感じることができる。
どのような短編小説が長編小説の母胎として根を下ろすのか。どのような短編小説が根を下ろすことなく完結していくのか。それは自分でも予測がつかない。とにかく書き終えて、発表して、ある程度時間がたつのを待っているしかないのだ。時間がたてばそれはわかるし、たたなければわからない。”
(『村上春樹全作品 1990~2000』第4巻「ねじまき鳥クロニクル1」解題より 一部抜粋)
“いくつか手を入れてみたいとも思った。内容を大きく書き直すのではなく、文章的に「ヴァージョンアップ」してみたいと思ったのだ。短編小説に関しては僕はよくそういうことをする。長編小説に手を入れることは一切しないが(そんなことをしたらバランスが崩れてしまう)、短編小説には現在のポイントから書き直す余地が往々にしてあるからだ。レイモンド・カーヴァーも同じようなことをしていた。前のヴァージョンをオリジナルとして残しながら、新しい版をこしらえていく。それは文章家としての自分自身の洗い直し作業でもある。おそらく「前のほうがよかったよ」と言われる方もおられるだろうが、僕としては二十一年ぶりに、またひとつ違う可能性を追求してみたかったのだ。ご容赦願いたい。
そのようなわけでオリジナルの版と区別するために、こちらの作品はタイトルを『ねむり』と変えた。”
(『ねむり/村上春樹』あとがきより 一部抜粋)
![]()

村上春樹にみる短編小説と長編小説。久石譲にみるエンターテインメント音楽とオリジナル作品。だぶるように透けるように、うっすら見えてきたのならうれしいです。ちょっとこじつけが過ぎるよ!抜き出し方が作為的だ!……そんなことにはならない印象で自然にすうっと入ってくるとうれしいです。
村上春樹は長編小説を一番大切にしていますが、同じように短編小説がないと今あるかたちの長編小説は生まれてこなかっただろうとも語っていました。久石譲がオリジナル作品を一番大切にしていると公言はしていないです。でも公言はしなくとも、作家として自作品を残すことが一番大事と思っている、これはしごく当然なことです。
僕らファンは、あの映画がなかったら、あのCMがなかったら、エンタメオーダーがなければ生まれなかった名曲たちがたくさんあることを、深く愛おしく理解しています。そこからオリジナル作品へと発展したものもある。聴き手がわかるものもあれば作曲家本人しか知りえないものまで。深いところでつながっている作品たち。
ひとりの作家が生みだす全ての創作物はつながりをもっているという尊さ。思えば、これはクラシック音楽時代からそうです。小曲から交響曲へとなっていったもの、ひと楽章まるまるカットされた改訂、弦楽四重奏曲から弦楽オーケストラ作品となったもの。作品系譜という年表のなかで遺ってきた作品たち。
そんななかで、村上春樹と久石譲、このふたりにしか見当たらない共通したフィールド、他の追随を許さない強力な武器があるとしたら。実践することで自身の作家性をより広げ深めているもの。それは、翻訳と指揮です。Part.??まで続くかわかりませんが、ぜひ楽しみにお付き合いいただけたらうれしいです。
-共通むすび-
”いい音というのはいい文章と同じで、人によっていい音は全然違うし、いい文章も違う。自分にとって何がいい音か見つけるのが一番大事で…それが結構難しいんですよね。人生観と同じで”
(「SWITCH 2019年12月号 Vol.37」村上春樹インタビュー より)
”積極的に常に新しい音楽を聴き続けるという努力をしていかないと、耳は確実に衰えます”
(『村上さんのところ/村上春樹』より)
それではまた。
reverb.
次は翻訳と指揮について深めていけたら。
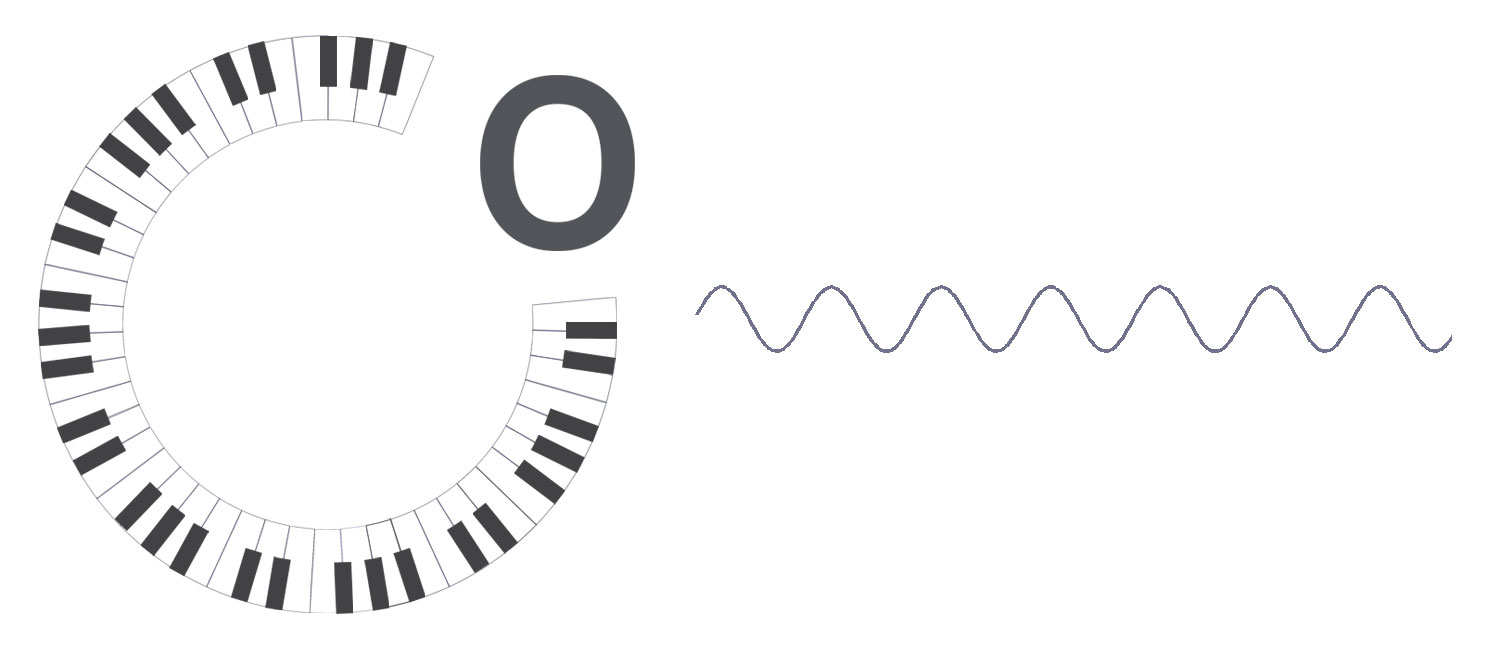
*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]
このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

