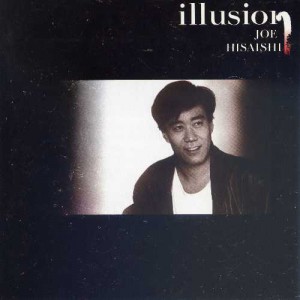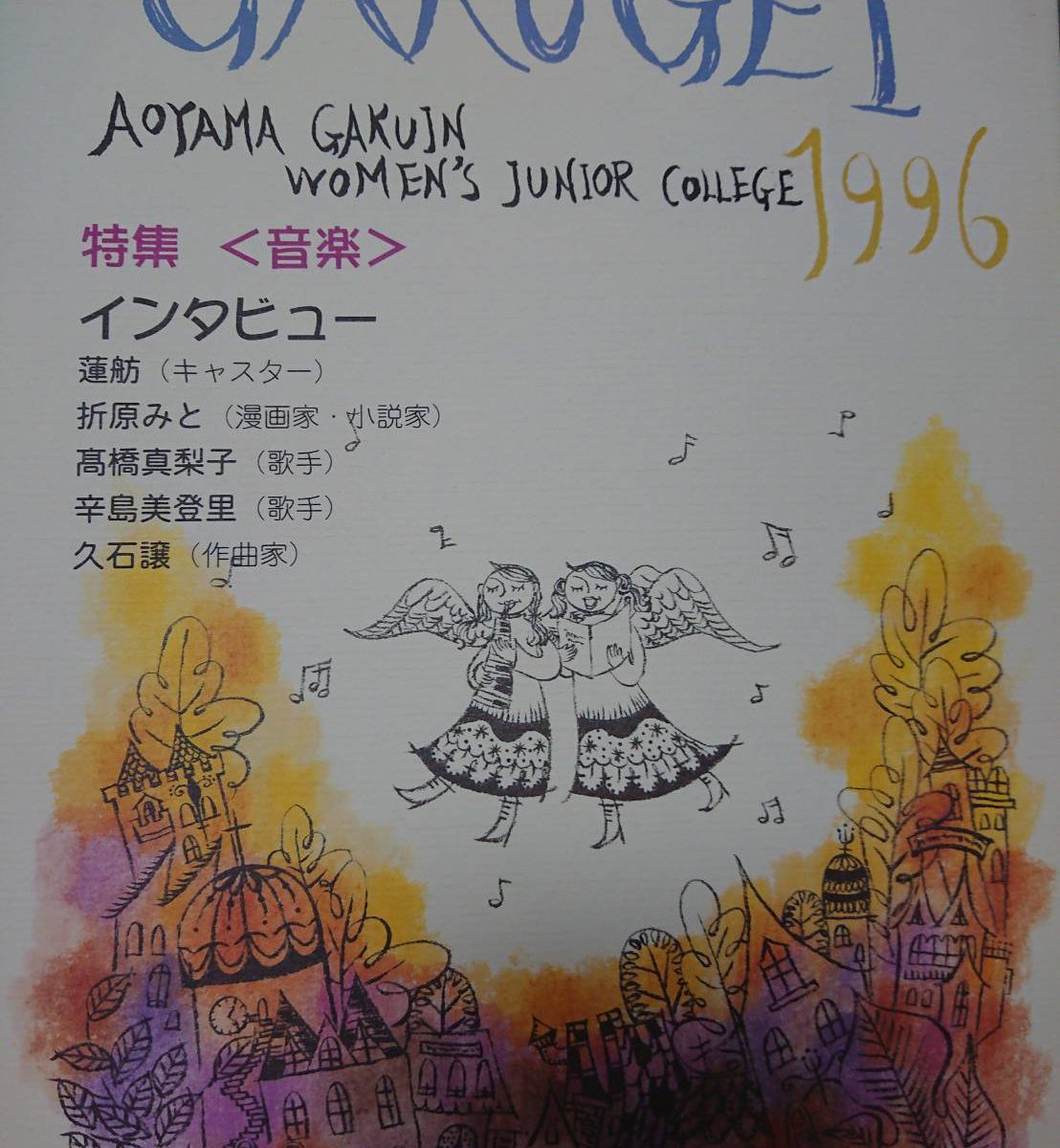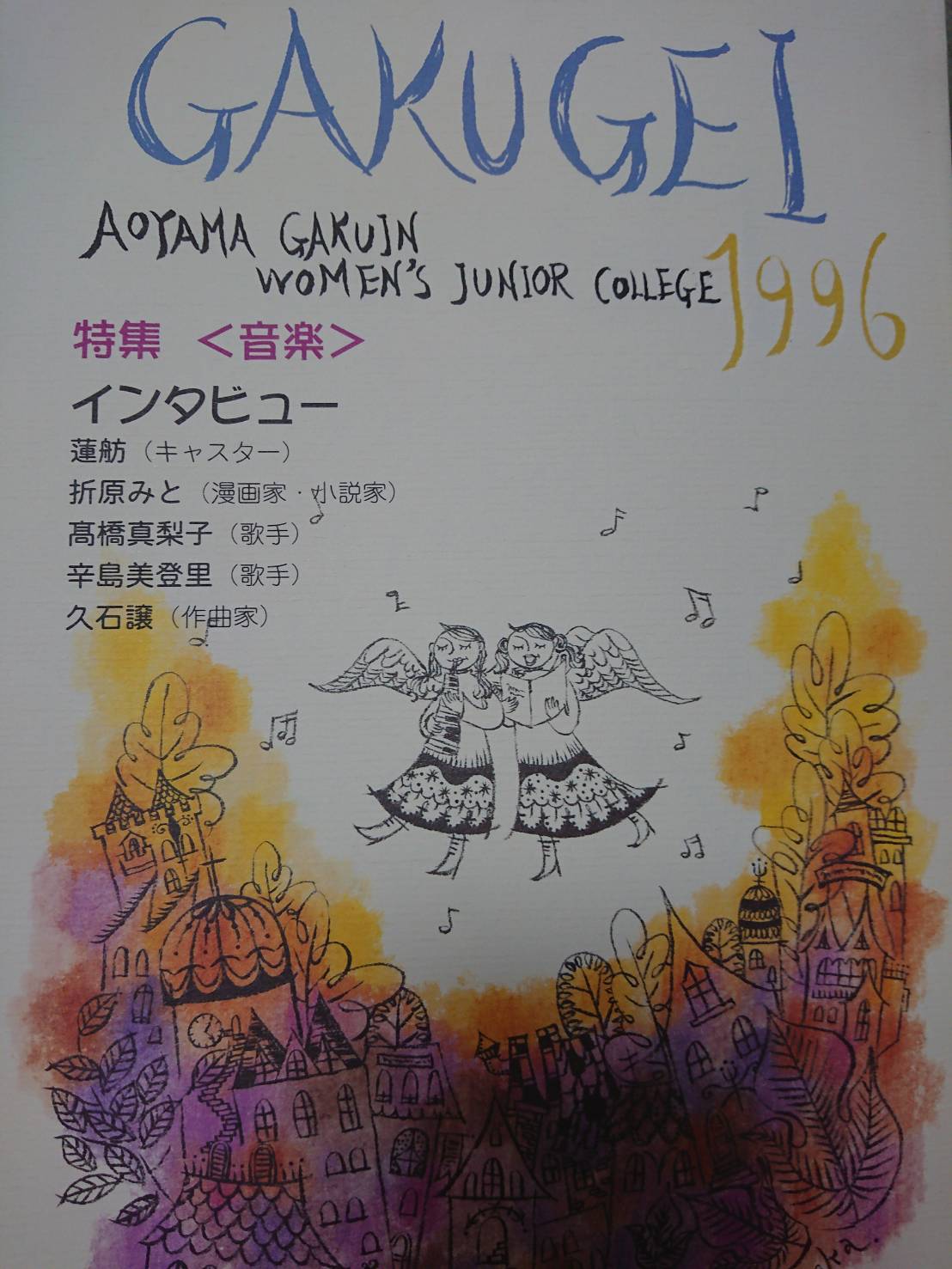Posted on 2020/12/03
2020年11月3日、映画公開当時はLPでは発売されていなかった「千と千尋の神隠し」「ハウルの動く城」の2作品のイメージアルバム、サウンドトラックに、あらたにマスタリングを施し、ジャケットも新しい絵柄にして発売されました。「千と千尋の神隠し」「ハウルの動く城」各サウンドトラック盤には、前島秀国氏による新ライナーノーツが書き下ろされています。時間を経てとても具体的かつ貴重な解説になっています。
2020年6月に久方ぶりに劇場で再上映され、3週連続興行成績第1位を記録した『千と千尋の神隠し』のリバイバルを見てきた(2001年の初公開時以来、現在も日本歴代興行成績第1位の座を維持し続けている)。感染症対策で定員が約半分に減らされた座席を埋めていた20代から30代の女性客のほとんどは、おそらく初公開当時は生まれていないか、テレビ放映やDVDなどでこの作品に慣れ親しんできた世代ではないかと思う。その彼女たちが、本編冒頭で流れる《あの夏へ》のピアノのアルペッジョに耳をすまし、食い入るように画面を見つめ始める姿を眺めていると、初公開時の19年前の記憶がいろいろと甦ってきた。この映画が公開されてから2ヶ月後に9・11同時多発テロが発生し、世界はそれまでの日常とは異なる”異界”に突入してしまった。そして今、彼女たちは”異界”の真っ只中に身を置きながら、いわゆる新しい生活様式を日常として受け入れている。19年前と同じように映画館に鳴り響いた《あの夏へ》のリリカルなピアノは、時を越え、彼女たちにしっかりと寄り添っていた──困難な時を生き抜く”千尋の物語”は、昔も今も変わらないと言わんばかりに。
第75回アカデミー賞長編アニメ映画賞受賞や第52回ベルリン国際映画祭金熊賞受賞をはじめ、世界各国で高い評価を受けた『千と千尋の神隠し』は、宮崎監督と久石譲のコラボレーションの中でもひときわ大胆かつ斬新な音楽作りを試みた作品と位置づけることが出来る。久石自身の言葉を借りれば、「スタンダードなオーケストラにないものを音楽の中に持ち込んで、新しいサウンドにチャレンジする」実験である。だからといって、いわゆる現代音楽のような難解な音楽になっているかというとそうではなく、メインテーマ《あの夏へ》をはじめ、親しみやすい歌謡的な要素をスコアの随所に聴き取ることが出来る。それらをすべて一体化させることで、久石は宮崎監督の世界観を巨大な音伽藍として表現したのである。
まず、久石は全体の音楽設計について、本作完成後の2001年7月の時点で次のように筆者に語っている。
「物語自体は、千尋という少女がさまざまな困難に立ち向かっていく話なので、彼女の心情に寄り添うべき部分は、極力静かな音楽で通しました。もともと、キャラクターごとに音楽を作っていくハリウッド的な手法はあまり好きではないのですが、この作品に限って言えば、ハリウッド的な扱い方をしている部分もあります。そもそも、この作品は設定そのものが凄いじゃないですか、湯屋という場所の世界観が。その世界観を音楽で表現するため、通常のオーケストラにはないエスニックな要素をカラフルに加えていくというアプローチをとることにしました」
「千尋の心情に寄り添う極力静かな音楽」に関しては、久石は詩情豊かなピアノのテーマを作曲し、それをスコア全体のメインテーマに据えることで、物語を貫く千尋の視点を明確に打ち出している。このメインテーマは本編の中で計4回流れてくるが(①本編オープニング、②ハクから渡されたおにぎりを千尋が食べるシーン(すぐ後のボイラー室のシーンまで曲は続く)、③ハクを救うべく銭婆の許へ向かうことを決意した千尋が釜爺から電車の切符をもらうシーン、④本編ラスト)、本盤では《あの夏へ》(①のシーンに使用)、《あの日の川》(②③)、《帰る日》(④)にメインテーマの旋律を聴くことが出来る。あたかも10歳の少女が口ずさむような繊細なメロディで書かれた《あの夏へ》は、わかりやすく言えば”千尋のテーマ”の役割を果たしている。
これに対し、千尋以外の登場人物に関しては、久石はそれぞれのキャラクターに特徴的かつ印象的なテーマを与えることで、一癖も二癖もある登場人物たちをバラエティ豊かに表現している。本盤収録曲では《湯婆婆》、《おクサレ神》、《ボイラー虫》、それにハクを表す《竜の少年》などの楽曲がそれらのテーマに当たる。さらに興味深いのは、本編作曲に先駆けて制作されたイメージアルバム収録のヴォーカル曲に由来する楽曲が、やはりキャラクター表現のテーマに用いられているという点だ。本盤収録曲では、湯屋を訪れる神々を表す《神さま達》(イメージアルバムでは《神々さま》)、湯屋の従業員たちを表す《仕事はつらいぜ》(イメージアルバムでは《油屋》)、そして曲名通りの《カオナシ》(イメージアルバムでは《さみしい さみしい》)などが、いずれもイメージアルバムのヴォーカル曲にその原型を見出すことが出来る。
「イメージアルバムにヴォーカル曲が多い理由のひとつは、イメージアルバムとサントラ盤のリリース時期が非常に接近していたという事情があります。つまり、イメージアルバムが発売されてから1、2ヶ月後には、サントラが出てしまうという(注:イメージアルバムは2001年4月発売、サントラは2001年7月発売)。2枚とも似たような内容になってはならないと考えていたのですが、宮崎監督からいただいた映画のための説明内容が、どれも詩的に書かれていたんです。『ならば、これを全部歌詞に用いて、歌にしてしまおう』と。そこでイメージアルバムのほうは、どちらかというと映画と切り離した”歌もの”というコンセプトで作ったんです」
本編のスコアにおいては、当然のことながらイメージアルバムの歌詞は用いられていない。どのテーマも、あくまでもインストゥルメンタル(器楽曲)として登場する。にも拘わらず、たとえ歌詞がなくても《神さま達》を聴くと、湯に浸かる八百万の神を歌った”民謡”のユーモアが伝わってくるし、あるいは《仕事はつらいぜ》を聴くと、いつまでも仕事から解放されない労働者たちが”仕事歌”に込めたボヤキが聴こえてくるだろう。このように、いくつかのテーマは、もともと”歌”として書かれた痕跡をしっかりと残しながら、結果としてスコア全体に”歌謡的”な要素をもたらしている。もう、ほとんど潜在的な”ミュージカル”と呼んでもいいくらいだ(《カオナシ》については後に詳述する)。
そうした”歌謡的”な要素と拮抗あるいは融合する形で登場するのが、本作で久石が試みた実験、すなわち通常のオーケストラにエスニックな音楽語法や民族楽器(のサンプリング)を混ぜていくユニークな手法である。
本編冒頭、久石はオーケストラの管弦楽法を西洋音楽の常識的な用法にとどめておくことで、千尋と我々観客が共有するところの日常的な現実世界を表現する。ところが千尋がトンネルの向こうの不思議な世界、すなわち”異界”に足を踏み入れていくと、オーケストラは常識的な管弦楽法から逸脱し始め、夜の闇のように闖入し始めたエスニックな要素が、次第に幅を利かせるようになってくる。物語の最後、すなわち《帰る日》でメインテーマが回帰すると、オーケストラは再び元の聴き慣れた響きを取り戻す。このような一連の変化を通じて、久石は”日常”と”異界”の違いを明確に描き分けているのである。
「オーケストラの中にエスニックな要素を入れるのは、すでに『風の谷のナウシカ』から始めた手法ですし、特に『もののけ姫 イメージアルバム』では、かなり意識的に邦楽器を使っています。『千と千尋の神隠し』の場合は、”モダニズム”という表現が適切かどうかわかりませんが、日本というものを別の視点から捉え直していくためにエスニックな要素を入れていった感じですね。スコアの中では、五音音階や邦楽器を使っていますが、それらは決して日本そのものを表現しているわけではない。確かに映画の舞台は日本ですが、我々が慣れ親しんでいる日常の日本とはずいぶん違います。むしろ、台湾の夜市に行くと、人が通れないくらい混雑していて、その中で売り子さんたちが威勢よくモノを売っていたり、夜中の1時か2時ごろまで子供がいたりするような感じに近いですね。ああいう”アジアの雑踏”のイメージが非常に強かったので、この映画も”アジアの中にニッポン”という位置づけで、スコアの中にアジアン・テイストを採り入れていったのですが、それを推し進めていくと、東南アジアだけでなく、シルクロードも中近東も同じアジア、つまりユーラシアという大きな文化圏に属しているのだと。そんな風に”アジア”を捉え直すことで、ふだん共存することがあり得ない西洋のオーケストラとエスニックな楽器を対等に鳴らす方向に向かっていきました。はじめから頭で考えて作ったというより、『あれもこれも”アジア”だろう』という感じでどんどんエスニックな要素を足していったと言うほうが正確ですね」
《神さま達》における琉球音楽やケチャのリズム、あるいは《おクサレ神》における雅楽など、文字通り八百万の神のように次から次へと登場してくるエスニックな要素は、枚挙に暇がない。さらに”アジア”の響きに触発されるかのように、いわゆる西洋音楽の要素も通常の表現を逸脱し始め、極端な方向に向かっていく。ピアノの高音域と低音域を同時に鳴らして金属的に響かせる《湯婆婆》などが、その例だ。
そうした音楽的実験の中でも、特にリスナーを驚かせる楽曲が、20世紀前半の新ウィーン楽派もかくやと思わせる重厚なオーケストラと、バリ島のガムランに基づくリズム・セクションが衝突することで凶暴さを際立たせた《カオナシ》であろう。だが驚くべきことに、その《カオナシ》さえも歌謡的な要素を含んでいるのである。イメージアルバム収録の《さみしい さみしい》をすでにお聴きのリスナーなら、異形の響きに満ちたオーケストラの中に《さみしい さみしい》の旋律の呟きを聴き取ることが出来るだろう(つまり、カオナシが抱える孤独と、彼の凶暴性が表裏一体の関係にあることを暗示している)。
このような作曲の方法論は──久石自身の捉え方と異なるかもしれないが──実はグスタフ・マーラーの交響曲の方法論に非常に近いのではないか、というのが筆者の考えである。マーラーは、彼以前の交響曲では用いられなかった珍しい楽器をオーケストラに採り入れることで音色のパレットを拡張し、自身の世界観を巨大な編成の交響曲で余すところなく表現しようとした。しかも彼の音楽の根底には、民謡や彼自身が作曲した歌曲に由来する”歌謡的”な要素が一貫して流れている。同様に久石のスコアにおいても、イメージアルバムの”歌謡的”な要素を踏襲しながら、”アジア”を拡大解釈していくことでエスニックな要素を次々に投入し、”異界”のリアリティを見事に音楽化してみせた。しかも本作の場合は、観客が理解しやすいハリウッド的なキャラクター表現をもスコアに含めることで、普遍的かつ全方位的に宮崎監督の世界観を音楽で表現しているのである。それが、本作の映像表現と音楽表現に対して全世界的な称賛が寄せられた理由のひとつではないかと思う。
最後になるが、本作のスコアにおいて、特に久石の音楽性が美しく刻み込まれた印象深い例を2曲だけ挙げておきたい。ひとつは、千尋が海原電鉄に乗るシーンにおいて、久石がニュアンス豊かなピアノをしっとりと奏でる《6番目の駅》。もうひとつは、千尋とハクが大空を飛ぶシーンで流れる壮麗なオーケストラ曲《ふたたび》だが、イメージアルバムでの曲名《千尋のワルツ》が示しているように、この楽曲はワルツ形式で書かれた事実上の”愛のテーマ”である。《ふたたび》が流れる時、ハクは千尋の記憶によって自分の真の名前をふたたび取り戻す=回復するのだが、このような”回復”という主題をワルツ形式に託して表現する試みは、宮崎監督と久石の次作『ハウルの動く城』のメインテーマ《人生のメリーゴーランド》において、さらに深く掘り下げられていくことになるだろう。
本盤最後に収録された《いつも何度でも》は、覚和歌子が作詞を手掛け、木村弓が作曲・歌・ライアー(竪琴の一種)を担当した主題歌。初公開時には、前述の《あの夏へ》に覚が詞を付けたヴォーカル版(本盤未収録)をカップリングしたマキシシングルとしてリリースされた。
※「」内の久石の発言は、筆者とのインタビューに基づく。
前島秀国 サウンド&ヴィジュアル・ライター
2020/8/5
(LPライナーノーツより)
千と千尋の神隠し/サウンドトラック

音楽:久石譲 全21曲
新日本フィルハーモニー交響楽団のフルオーケストラにより、ホール録音されたサウンドトラック盤。 主題歌「いつも何度でも」(歌/木村 弓)も収録。
品番:TJJA-10028
価格:¥4,800+税
※2枚組ダブルジャケット
(SIDE-A,B,Cに音楽収録 SIDE-C裏面には、音がはいっておりません。)
(CD発売日2001.7.18)