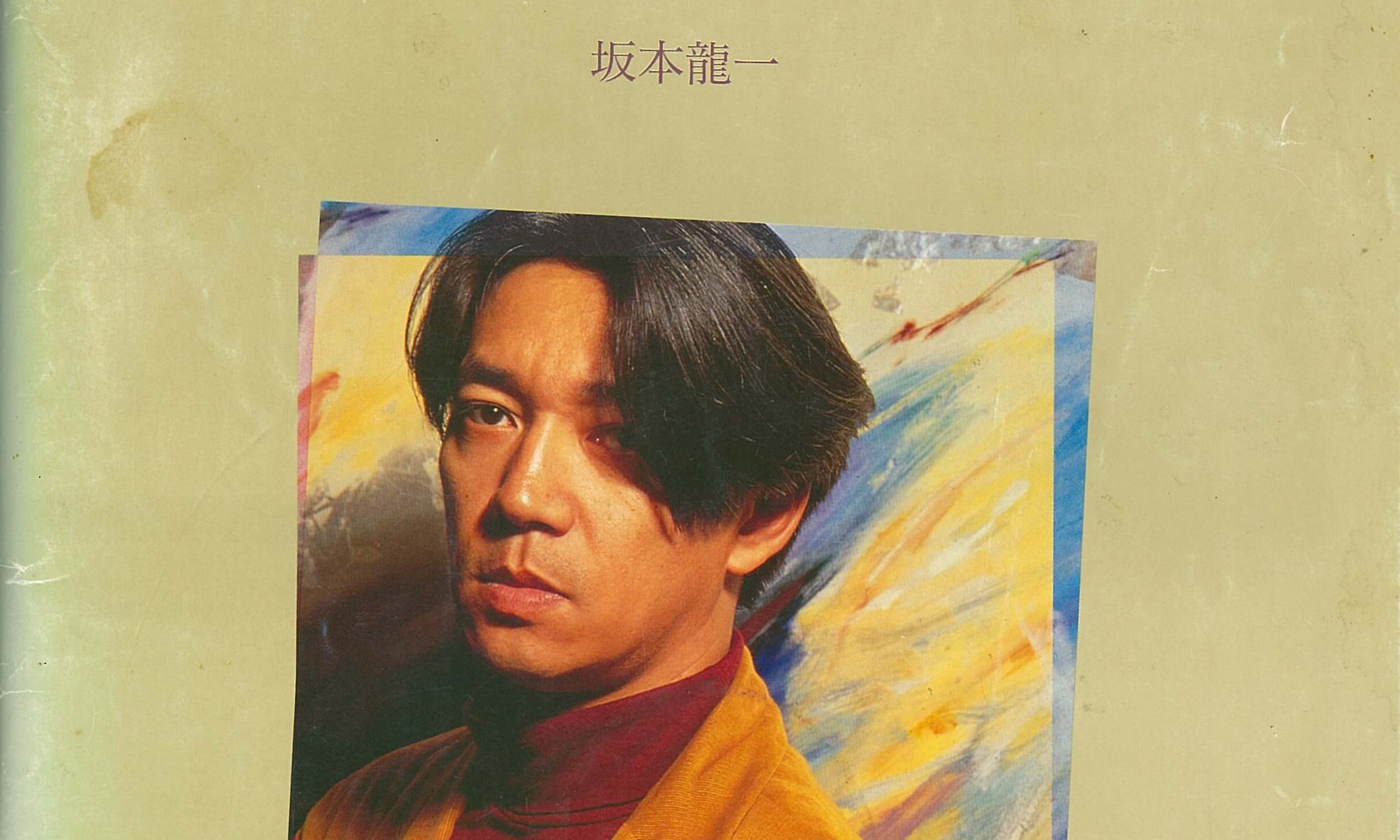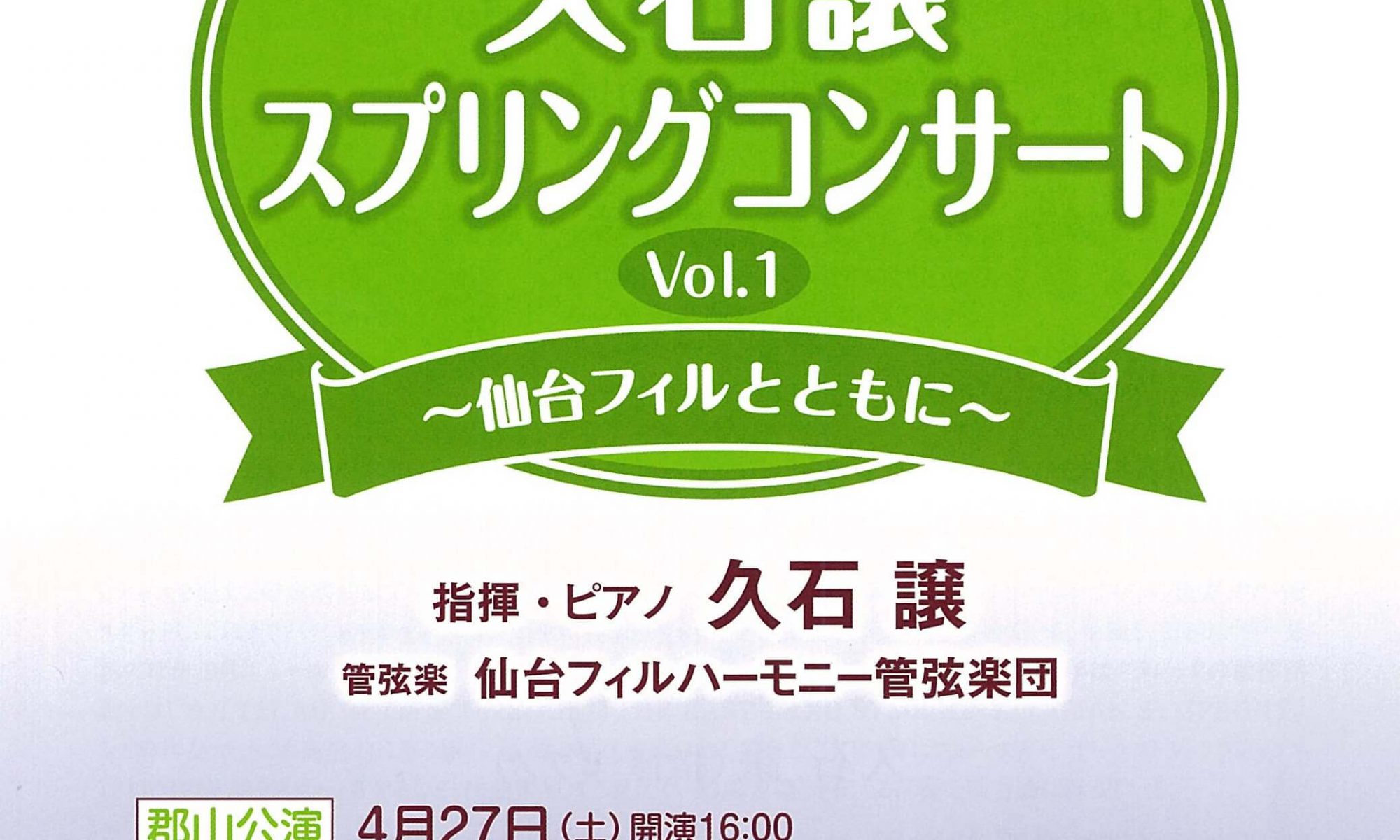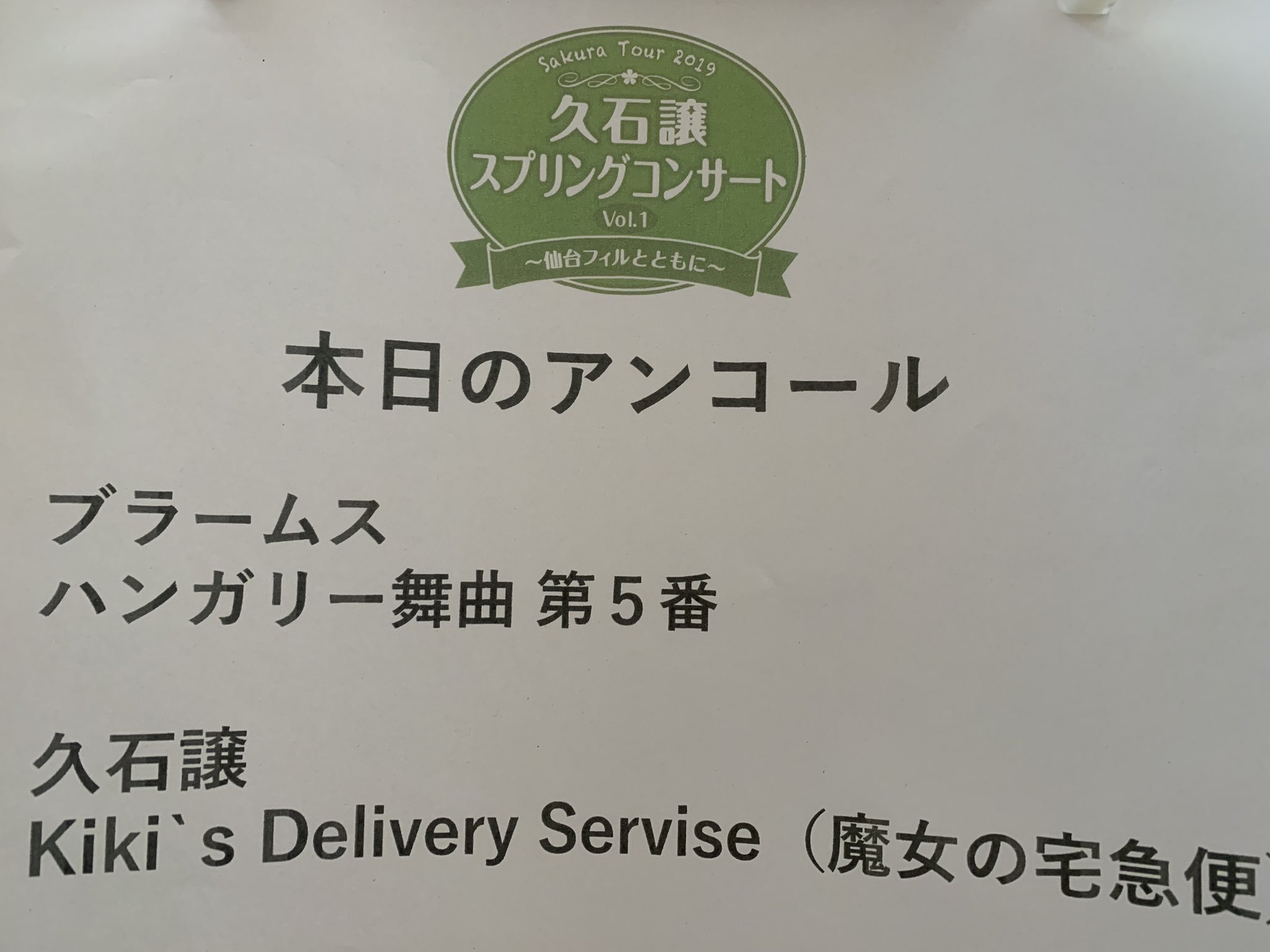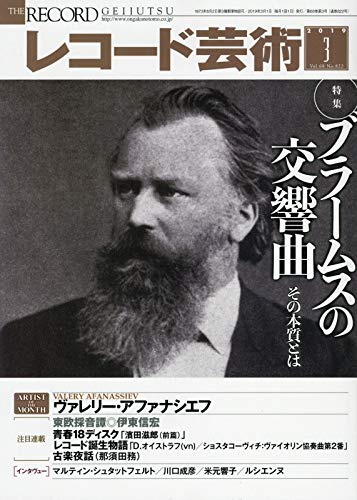Posted on 2019/06/04
書籍「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ 3」(2013)に収録された久石譲登場回(2008)です。この本は同ラジオ番組を単行本シリーズ化したものです。
久石譲
「ジブリアニメとの25年」
ジブリアニメと言えば、久石譲さんの音楽。雄大で、リリカルで、繊細で。そして、時に、ほのぼのとユーモラスに奏でられるその音楽は、ジブリ作品の”肌ざわり”と、切っても切れない関係にあります。『風の谷のナウシカ』(1984年)以来の、両者の永い付き合いは、どのように始まり、どのように発展していったのか……? 『崖の上のポニョ』(2008年)の音楽を作曲中だった久石さんと鈴木さんとのトークに、耳をすましてみましょう。
(ゲスト参加:読売新聞〈当時〉・依田謙一)
「駆け引き」はいらない
依田:
初めて宮崎駿監督に会った時は、やっぱり印象深かったんじゃないですか?
久石:
いやあ、それがね……(笑)、全然ドラマチックじゃないからね。阿佐ヶ谷のスタジオ(トップクラフト)でしたね。
鈴木:
はい、そうです。阿佐ヶ谷です。
久石:
壁にいっぱい、『ナウシカ』の絵コンテが貼ってあって。そしたら、宮崎さんがいらして、いきなり説明を……(笑)。「これは腐海といって」とか、「これは王蟲で」って、ワーッと説明された時に、ぼくは、「あれっ!? この人、誰だろう?」と思っちゃって(笑)。
鈴木:
あははは(爆笑)。
久石:
いや、これはあまり言っちゃいけないんだろうけど、実はその時点では、宮崎作品としては、もちろん、『ルパン三世』は知っていましたよ。だけど、それ以外は、そんなに知らなかった。『ナウシカ』も、大まかなストーリーだけ聞いて行ったら、延々と説明されて。もう、ずーっと、1時間くらい、作品のことを全部説明するんですよ(笑)。驚きましたねえ……
●
久石:
あのね、今作っている『崖の上のポニョ』では、主人公の男の子(宗介)は、5歳の子供でしょう。
鈴木:
はい。
久石:
男の子と女の子(ポニョ)が出会う。そうすると、「好きだ」っていう感情は、もうそのまま、「好きだ」でしょ。普通は、その気持ちが揺れたり、何だかんだ思ってくれたりすると、そこに映画音楽って入れやすいんですよ。
鈴木:
なるほど。
久石:
だけど、その子は、全然悩んでないんですよ。
鈴木:
宮さん(宮崎駿)は、いつもそうですよ。
久石:
もう、スパッと、「好き」(笑)。
鈴木:
あのね、男女関係で宮さんが一番嫌いなのが、”駆け引き”なんです。
久石:
ああ……
鈴木:
会った瞬間、相思相愛。普通だったら、ねえ……打算とかいろいろあって、「ぼくはこんなに好きなのに、彼女はどうなんだろう?」って、いろいろ思い悩むじゃないですか。
久石:
そう。
鈴木:
ないんですよね、あの人の場合は(笑)。
久石:
あははは。キャラクターが思い悩んでくれると、音楽って、そこに入りこむ余地があるんですよ。それがストレートに、「好き」。もうすぐに言っちゃう。追いかけちゃう。そうすると、どうやって曲をつけたらいいのかって悩む。
鈴木:
今に始まったわけじゃないですよ。宮崎作品では、本当に毎回、そうですから。
久石:
そうなんですよ。今回も、見事にスポーンとしてるから……
鈴木:
「現実で、男女はそういうこと(駆け引き)をしょっちゅうやってるんだから、映画の中ぐらい、そういうのがないほうがいいよ」っていう、宮さんの声が聞こえてきそうでしょ?(笑)
久石:
もう、完全にそうですね。
●
久石:
だから逆に、音楽のほうも割り切った、新しいスタイルでできないかなと思って、今、取り組んでいるんですよ。というか、どちらかというとぼくは、長く曲をつけるのが好きだったんですよ、今までは。入り出したら2分とか、長く続けるのが好きで、その方式をとってきたんだけど、今回は逆に、5秒とかね。
鈴木:
ああ、短いんですよね。
久石:
すごく短い。ようするに、「はい、始まった。終わった」っていうよりも、(音が)「あった」。そのかわり、間もあるんだけど、「また、あった」みたいなね。まあ、理想で言うと、どこから音楽が始まって、どこで終わったか、あまりわかんない方式をとれないかなと思って。
鈴木:
いろいろ考えてますねえ。
久石:
いやいや……(笑)。
鈴木:
絵のほうが、もう、90何パーセントできちゃってるんですよ。
久石:
すごい早いですね。
鈴木:
そう。いつもより余裕がある。だからもう、宮さん本人もね、「あとは音だ」って言ってて。
久石:
あっ……
依田:
プレッシャーが、来た、来た、来た(笑)。
鈴木:
あははは(笑)
音楽が果たせる役割
依田:
そもそも、最初に『ナウシカ』をおやりになった時は、どうやって曲を作っていったんですか。
久石:
あの作品では、高畑(勲)さんがプロデューサーだったんですよ。
鈴木:
宮さんは、当時、公言しておりましてね。「おれは歌舞音曲には無縁だ」「おれには音楽はわからない」って。だから、「高畑さん、全部よろしく!」って(笑)。そこからスタートなんですよ。「高畑さんが選んでくれたら、おれは、それでいい」と。それで、率直に申し上げると、当時いろんな作曲家の名前が候補にあがって、久石さんを選んだのは、実は高畑さんだったんですよ。で、ぼくも一緒になって、久石さんの作った曲を、とにかく聴きまくった。高畑さんが、「久石さんがいい」って言った時の言葉を、ぼくはよく覚えてる。
依田:
何て言ったんですか?
鈴木:
「この人の曲は、無邪気だ。宮さんに似てる」って。
久石:
ああー……
鈴木:
その時はもちろん、久石さんに会ってないわけですよ。だけど、「この無邪気さ、天真爛漫さ、そして熱血漢ぶりなら、二人は絶対にうまくいくはずだ」って。それで会って、そして、期待に応えていただいたっていうことなんです。
久石:
うーん……いやもう、本当に幸運な出会いだったよね。ぼくはあの時、『ナウシカ』の曲のあと、安彦(良和)さんが監督した『アリオン』というのも担当した。これも同じ徳間書店さんの製作で、やっぱり大作だったわけですよ。『ナウシカ』『アリオン』と、二本続けて音楽を作らせていただいた。だからもう、『天空の城ラピュタ』は(オーダーが)来ないだろうと。「なんか嫌だな、ぼく、やりたいのにな」「ああ、『ラピュタ』できないのかなあ」とずっと思っていたら、連絡があって、うれしかった。あの時は、もう、泣いちゃいましたよ。
鈴木:
高畑さんと二人で、すぐ伺った。で、この音楽が、宮崎アニメの音楽の方向性を決める決定打だったと思うんですね。続いて、『となりのトトロ』ですもん。その時はね、高畑さんも『火垂るの墓』を作ってるから、今度は音楽を、宮さん自らやらなきゃいけないわけですよ。
久石:
そう(笑)。
鈴木:
ぼく、忘れもしないのがね、トトロとサツキとメイが、雨のバス停で出会うシーン。あそこは、すごい大事なシーンでしょ。なのに、宮さんは久石さんに言ってるんですよ、「音楽はいらない」って。でね、しょうがないんで、宮さんには内緒で、『火垂る』を作ってる高畑さんに相談に行ったんです(笑)。そしたら、高畑さんって決断が早いから、「いや、あそこは、音楽があったほうがいいですよ」って。「ミニマルでいくべきだ。久石さんだから、絶対できる」って言った。
久石:
だから、いわゆるメロディーでいくんじゃなくて、ミニマル・ミュージック的な……
鈴木:
そう。で、曲ができました。で、宮さんっていう人は面白いんですよ。聴いた瞬間、「これはいい曲だ!」って(笑)。「あそこは音楽いらない」って言ったのは、かけらも覚えてないわけ。
一同:
あははは(笑)。
鈴木:
とにかく、あの映画の一番のポイントはね、バス停でのトトロとの出会い。子供は、それを信じてくれますよ。だけど、大人が果たして信じてくれるのか。それを、あの曲によって実現した、とぼくは思ってるんですよ。大人も、トトロの存在を信じることができた。そういう意味でね、あの音楽は、本当に大事な曲だったと思います。
久石:
だから、言い方は変なんだけど、何ていうのかな……目の前が霧で何も見えない感じの中で、何か、「あっ、これはいけそうだ」と思うことがある。たとえば、フルートの音だったり。「あっ、こういう感じ!」とか、「あっ、もっと丸いイメージだ」とか、何かピンと来そうなものを頼りに探して歩いてる、っていう感じなんですよね。
だからこそ、映画音楽を作る時に一番気にしなきゃいけないのは、そのストーリー的な流れを邪魔しないようにピッタリ寄り添う時と、あえてそれを無視して、メロディーでそのシーンを押していく場合と、そのバランスですよね。『ポニョ』でも、やっぱり一番気にしてるところなんだけどね。だから、絵コンテをものすごく読み込みますね。それから、映像を観る。で、「どこに音のきっかけがあるんだろう?」と思うのと同時に、「あれっ? ここってもしかしたら、メインテーマや何かとまったく無関係なもので行くべきなのか?」「いや、そんなくだらないことを考えてはいけない(笑)。そうじゃなくて、ここはこういうふうに」とか、ゴチャゴチャ考えながら作っている。音楽に関しては、まず、自分が最初の観客であるわけだから。
映画音楽を書いてるとわかることなんですけど、映画って、もともと”作りもの”なんですよ。フィクションなわけです。で、「あっ、そんなのあり得ない」って思うようなことをやってても、それが逆に、もっと本当らしい現実を表現したりする。だから、映画を観て、みんなワクワクするわけですよね。そういう虚構性の中で初めて存在するわけだから、音楽って、やっぱり必要なんだろうと。
鈴木:
いや、だからね、さっきの、バス停での出会い──やっぱりあそこに音楽がなかったら、あの映画がほんとに名作になったのかなって思う。そのぐらいの力を、音楽は持っている。トトロの存在を大人の観客に信じさせるためには、あの音楽は必須でしたね。
久石:
えっと……ごめんなさいね、今、頭の中が『ポニョ』でいっぱいなもんで……何ていうか、何を話してても、『ポニョ』に気がいっちゃうんですよ(笑)。
一同:
あははは(笑)。
久石:
『ポニョ』ってね、言葉の語感がいいの。そう思いません?
依田:
ああ、音楽的いっていうことですか?
久石:
うん。まず、「ポ」が破裂音じゃないですか。それを、「ニョ」が受けとめる。「ポ」、「ニョ」でしょう。そうするとね、これ自体が、もう音楽なんですよ。
鈴木:
なるほど!
ラストシーンを決めた音楽
鈴木:
今回の『ポニョ』では、久石さんに作っていただいた曲がね、ラストシーンを決めました。
久石:
あははは(笑)。
鈴木:
いや、そういうことがあるんですよ。あの音楽によって、「ラストは、こうやればいいんだ」と、宮さん本人もわかったっていう……
久石:
いやあ、責任重大ですね。
鈴木:
どうやってお客さんに観てもらったらいいか、それが見えたんですよ、宮さんには。だから今回、早く作ってほんとに良かったなって(笑)。
久石:
いやあ、ぼくは逆にね、宮崎さんは、非常にすぐれた作詞家だと思ってるんですよ、で、本音を言うとですね、音楽の究極は、やっぱり歌ですよ。
鈴木:
うーん……
久石:
だって、人に何かを伝える時に、まず言葉があって、でも、言葉だけでもダメで、それと音楽とが響き合って、瞬時に人生を感じちゃったりとか、いろんなことがすべて見えたりする可能性があるわけで……。そうするとね、最後に行き着くのは、歌なんですよ。
鈴木:
歌も音楽も、生きものなんですね。
久石:
うん。結局は、そこに行き着いちゃう。生命の世界というかね……
鈴木:
何ていうのかなあ……自分の、意識の下のほうにね、太古の昔から続いてる遺伝子みたいなものがあるんじゃないかな、なんて思ってるんですよね。
久石:
うん。今回、もう本当に、「一人で作ってるんじゃないな」っていう感じがして(笑)。鈴木さんとも、しょっちゅうメールしたり、話したり。宮崎さんとも、本当に、すごくコミュニケーションをとったというか、よく話したんですよ。今までは、どちらかっていうと、わりと勝手にこっちで作って、「できました。聴いてください」っていうスタンスが多かったんですよ。
鈴木:
そうですね。
久石:
それがね、今回は本当に出だしからなんで、「ああ、一人で作ってるんじゃないな!」っていう感じが、すごく気持ち良かったんです。
鈴木:
いろいろ注文して、すみませんでした(笑)。でも20何年もお付き合いして、久石さんとこんな話するの、初めてだなあ。いや、貴重な機会でした(笑)。
2008年4月11日収録@れんが屋/4月27日放送
(「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ 3」より)
*本書には本文下にいくつかの注釈があります。割愛しています。
内容紹介
5年半をこえる大ロングラン。TOKYO FMの名物番組「ジブリ汗まみれ」(日曜23時~)から、今回もベスト・オブ・ベスト回を厳選収録。書籍シリーズ・第3弾が、『かぐや姫の物語』の公開にあわせて11月発売。天真爛漫でちょっぴり硬派な鈴木トークと、各ゲストの十人十色の個性が魅力。「巻を重ねるごとに面白い」「読みやすく、たっぷり楽しめ、しかも、心に沁みる快著」と、各界で大評判です!
●豪華11大ゲスト(順不同・敬称略)=尾田栄一郎(漫画家)「忘れまじ、任侠のこころ」/細田守(アニメーション映画監督)「”肯定していく力”を描きたい」/山口智子(女優)「日本人の“もの作り”と『かぐや姫』」/久石譲(作曲家)「ジブリアニメとの25年」/矢野顕子&森山良子(ミュージシャン)「ふたりで歌えば」/大塚康生(アニメーター)「追想・ルパン三世」/瀧本美織(女優)「『風立ちぬ』―菜穂子の素顔!?」/三池崇史(映画監督)「映画の息吹、その伝承」/きたやまおさむ(精神科医・作詞家)「“駅裏”のなくなった現代」/川上量生(ドワンゴ会長)「〈鈴木道場〉 其の三・風雲篇」
絶賛発売中
●第1巻:ゲスト=庵野秀明/宮崎駿/阿川佐和子/坂本龍一/志田未来・神木隆之介/山田太一/太田光代/ジョージ・ルーカス/辻野晃一郎/川上量生
●第2巻:ゲスト=浦沢直樹/松任谷由実/押井守/手嶌葵/井上伸一郎・髙橋豊/竹下景子/岩井俊二/宮崎吾朗/川上量生/号外・ジブリ2大最新作製作発表!
(書籍インフォメーションより)
*2019年6月現在、「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ」単行本シリーズは第5巻まで刊行されています。